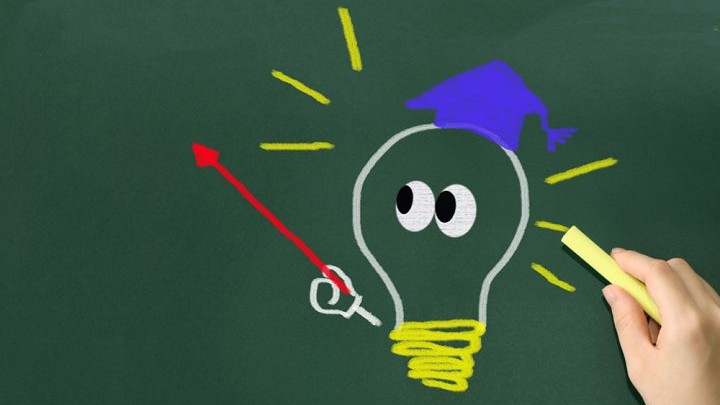読書体験における主体的判断と失敗の意義

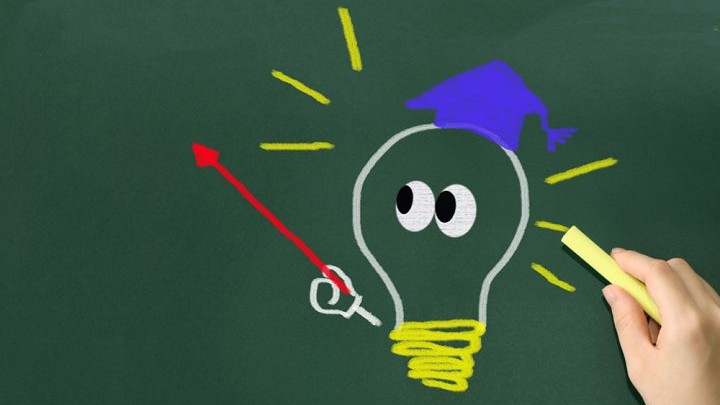
読書という行為は、単に書籍を購入することから始まるものではあるが、その本質は、書店において手に取った瞬間に何らかの感情が動かされた場合、即座に購入するという決断にあると言える。
しばしば「積ん読」と呼ばれる、購入後に未読のまま本を積み上げておく行為でさえ、読書体験の一部を成しているのだ。しかし、「あとで考えよう」や「明日でも構わない」といった逡巡が生じた瞬間、その書籍との縁は切れてしまうものと考えざるを得ない。
そもそも、その場で即決できない理由の一つとして、購入の失敗を恐れる心理が挙げられる。すなわち、せっかく手に入れても、読んでみて期待外れであった場合の損失を懸念するのである。しかしながら、読書において「失敗」は避けるべきものではなく、むしろ経験すべき過程である。「つまらない」と感じること自体、読書を通じて自らの価値観や判断基準が形成されている証左にほかならない。
したがって、「つまらない」と判断できたことを誇るべきであり、失敗を恐れるよりも、つまらない本を面白いと錯覚してしまうことの方こそ警戒すべきであろう。
また、「せっかく購入したのだから」と無理に最後まで読み続ける必要はなく、自身の判断を信じて途中で読むのをやめることも重要である。一方で、世の中には、初めはとっつきにくいものの、読み進めるうちに徐々にその面白さが明らかになる書籍も少なくない。
かつては理解できずに放り出した本であっても、何かの折に再び手に取ると、かつてとは異なる新たな面白さを発見することもある。そのような経験を重ねることで、読書の楽しみは一層深まるのである。実際、夏目漱石の『吾輩は猫である』のように、人生の各段階で異なる味わいをもたらしてくれる作品も存在し、繰り返し読むたびに新たな発見があるのだ。