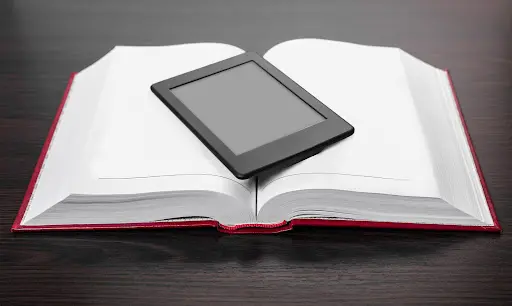NHKはことし9月から10月にかけて全国の県庁所在地、中核市、政令指定都市、東京23区の合わせて106の自治体に点検の結果などをアンケート調査し、95の自治体から寄せられた回答を集計しました。
その結果、業界団体の基準に基づいて構造上の安全性を点検していたのは67の自治体で、合わせておよそ9万基の遊具のうち、17%にあたる1万5300基余りが「命の危険や重い障害につながる事故のおそれがある」と判定されていたことがわかりました。
さらに、このうち66%に当たるおよそ1万基は、そのまま使われ続けていました。
こうした遊具では、滑り台の手すりなどの隙間に子どもの首が挟まったり、鉄棒などでコンクリート製の基礎が地面から露出し落下した際に頭を強く打ったりする危険性が確認されました。
使用を継続していた39の自治体にその理由を複数回答で尋ねたところ、「利用者の利便性を考慮した」が67%にあたる26自治体と最も多く、次いで「予算措置が困難」が21自治体、「どのように対応するか決まっていない」「使用禁止にする義務がない」という回答もありました。
国土交通省は、公園を管理する自治体などに示した遊具の安全確保に関する指針の中で「生命に危険を及ぼす、重度又は恒久的な障害をもたらすなどのおそれがある危険は、早急に取り除く」としています。
今回の結果について国土交通省は「危険性に応じて使用中止や修繕など適切な措置を講じるよう求めたい」としています。
遊具重大事故 12年間に133件
公園の遊具で遊んでいた人が死亡、または全治30日以上のけがをした事故やそうした結果を招くおそれがあった事故について、国土交通省はその概要を報告するよう公園を管理する自治体に求めています。
NHKは平成19年度以降、国に報告があったすべての事故について情報公開請求を行い、その内容を分析しました。
その結果、昨年度までの12年間に全国37の都道府県で合わせて133件の事故が起きていたことが分かりました。このうち死亡事故は1件で、平成20年、愛知県豊田市の公園でブランコで遊んでいた小学2年生の女の子が誤って転落し、戻ってきた台座が頭に当たって死亡しました。そして76人が骨折や指の切断といった大けがをしていました。
また事故の内容を見ますと、
▽遊具が倒れたり壊れたりしたことによる事故が52件と4割を占め、
▽露出していたボルトやくぎ、コンクリートの基礎部分に体の一部をぶつけ、けがをした事故が9件ありました。
国土交通省は「不十分な点検が原因とみられる事故も起きていることから、点検が確実に行われるよう指導するとともに、危険な遊具については自治体が撤去したり改修したりするための費用を支援し、事故を防ぎたい」としています。
専門家「自治体は点検結果公表し住民と協議を」
遊具の事故防止に取り組む団体「いんふぁんとroomさくらんぼ」の松野敬子代表理事は「危険な遊具はすぐに撤去すべきだが、子どもの成長のために遊びの中の危険をどこまで許容するのかは保護者や地域によって考え方が違う。ただ、それを判断するために自治体は点検の結果を公表すべきで、そのうえで遊具を撤去するのか使用を続けるのか自治体と住民がきちんと話し合って決めるべきだ」と話しています。