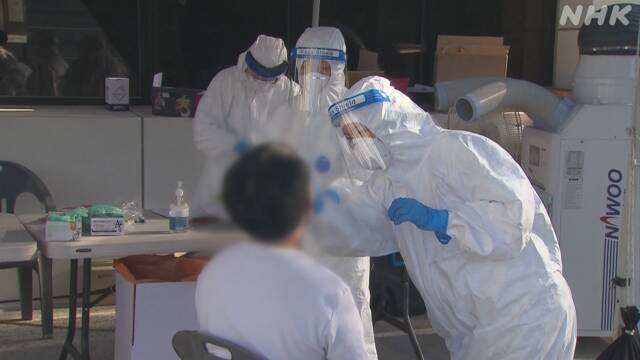中国政府は漁業資源の保護を目的に、東シナ海や南シナ海で5月から続けていた独自の禁漁期間を16日解除しました。
中国政府は漁業資源の保護を目的に、東シナ海や南シナ海で5月から続けていた独自の禁漁期間を16日解除しました。
これを受けて、各地の港では漁船が一斉に出港していて、このうち南部の福建省の港では、多くの漁船が、漁の解禁を祝う爆竹を鳴らしながら、中国海警局の船が誘導する中、相次いで出港しました。
対象となる海域の中には沖縄県の尖閣諸島もあり、4年前には、200隻から300隻程度の中国漁船が周辺海域を航行して、一部の漁船と中国海警局の船が日本の領海に侵入し、緊張が高まりました。
これについて地元の複数の漁師はNHKの取材に対し、「今回は、当局から尖閣諸島からは離れて操業するよう指示されている」などと話していました。
 また、現地では「敏感な海域に行き、魚をとることを厳しく禁止する」という横断幕も掲げられていました。香港や台湾などを巡ってアメリカとの対立を深める中国政府が、日本との摩擦をさけるため、中国漁船の管理を強化するかどうかが焦点です。
また、現地では「敏感な海域に行き、魚をとることを厳しく禁止する」という横断幕も掲げられていました。香港や台湾などを巡ってアメリカとの対立を深める中国政府が、日本との摩擦をさけるため、中国漁船の管理を強化するかどうかが焦点です。
出港に備える漁師たちは
中国南部、福建省石獅の港には中国国旗を掲げた数百隻の漁船が停泊し、漁の解禁を前に漁師たちが出港に向けた準備を行っていました。
この地域では、およそ500キロ離れた尖閣諸島の近くの海域まで漁に向かう船もあり、漁師たちは漁船に魚を冷やす氷や食料などを運びこみ出港に備えていました。
この地域の漁船には「中国版GPS」とも呼ばれる中国独自の位置情報システムが搭載され、中国当局は漁船が操業する場所を把握できるようになっていて、漁船の船長は、「われわれが行ってはいけない海域に入るとすぐに呼び戻される」と話していました。
また、尖閣諸島については「島はわれわれ中国のものだ」と主張する一方「島の近くまでいくこともあるが最近は当局が行かせないようにしている。中国海警局の船があちこちパトロールして行かないように通知するのでわれわれも行かない」と述べ、中国当局から周辺海域での漁を控えるよう指示を受けることもあると説明していました。
一方、別の漁師は、尖閣諸島周辺の海域について「島の周辺海域に行ったことがあるがパトロールしている海上保安庁の船や航空機がいた。島には周辺に魚がいない時には行く」と話していました。
中国にとっての尖閣の重要性
中国政府は、尖閣諸島周辺の海底に石油などの資源が豊富に埋蔵されている可能性が明らかになったあとの1970年代から尖閣諸島に対する領有権を主張するようになり、周辺の豊かな漁場や天然資源の権益を確保するねらいがあるとみられます。
また、尖閣諸島が中国が防衛ラインとみなし、太平洋と東シナ海を隔てる「第1列島線」のそばに位置することから戦略的な観点から重視しているという見方もあります。
さらに、一党支配を続ける中国共産党が求心力を保つためにも一度、領有権を主張した問題で譲歩することは難しく今後も強硬な姿勢を続けるものとみられます。
中国漁船をめぐる過去の問題
尖閣諸島周辺では、これまでにも中国漁船が日本の領海に侵入して問題となるケースがたびたび起きています。
1978年には、100隻以上の漁船が尖閣諸島の周辺に現れ、このうち数十隻が日本の領海に侵入したほか、一部の漁船は機銃で武装していて海上保安庁の巡視船が対応に当たりました。
また、2010年9月には尖閣諸島沖の領海内で中国漁船が海上保安庁の巡視船に衝突する事件も起き、船長が公務執行妨害の疑いで逮捕されました。
中国政府は日本に強く抗議したほか、尖閣諸島周辺の海域に漁船の活動の管理にあたるとする中国公船を派遣するなど強硬な対応を取り続けました。
さらに、4年前の2016年8月には中国政府が独自に設けている禁漁期間が終わったあと、尖閣諸島周辺の海域に200隻を超える中国漁船が押し寄せ、一部の船が中国海警局の船とともに日本の領海に侵入するなど緊張が高まりました。
中国の現状変更の試みとねらい
中国政府は沖縄県の尖閣諸島について、「中国固有の領土だ」として、領有権の主張を強めてきました。
2008年12月には、法執行機関に所属する中国公船2隻が初めて尖閣諸島周辺の日本の領海に侵入し、現状変更を試みる姿勢が明らかになりました。
2010年9月に尖閣諸島周辺の日本の領海で中国漁船と海上保安庁の巡視船が衝突した事件以降は、中国公船が尖閣諸島周辺の海域を航行する頻度が増えるようになります。
2012年9月に日本政府が尖閣諸島を国有化して以降は、活動を一気に活発化させ、領海のすぐ外側の接続水域では悪天候の日を除いて連日、航行するようになり領海への侵入も繰り返し行うようになりました。
ことしに入ってからは活動を一層活発にしていて4月から今月2日にかけては中国海警局の船が過去最長となる111日連続で接続水域内で航行を続けました。
5月には、尖閣諸島周辺の日本の領海で中国海警局の船が日本の漁船を追尾して一時、緊張状態となり、中国政府は「中国の領海で違法に操業していたためだ」などと正当化しています。
中国海警局は近年、大型化した船を投入しているほかおととしの機構改革で政府組織から軍の指揮下にある「武装警察」に編入されて軍の影響力が増し、体制が強化されていると指摘されています。
中国政府としては、尖閣諸島周辺での公船の活動を既成事実として積み重ねることで、領有権の主張を強化するねらいがあるとみられます。
中国の専門家「漁は主権を示す」
中国の海洋政策に詳しい中国海洋大学海洋発展研究院の金永明研究員は「禁漁期間が終われば福建省や浙江省の沿海部の多くの漁民が島の海域に行き集中的に魚を捕る可能性がある」と述べ、中国漁船が尖閣諸島周辺の海域で操業する可能性があるという見方を示しています。
また、中国の漁船や公船が尖閣諸島周辺で活動することについて「漁船がどこに行って魚を捕るかということは、その海域に中国の主権があり、管轄権を持つことを示す実践的な行為だ。また、中国海警局は法律上、漁民を保護し管理する職権を持っている」と述べ、中国の領有権を示すことにつながると指摘しています。
そのうえで中国漁船の操業の範囲について「どのようなエリアに行くのかは、みずから決めるものだが政府や地方機関が導くこともできる」などとして中国当局は一定の影響力を持つと説明しています。
専門家「徐々に支配奪うねらい」
中国の現代政治が専門の東京大学公共政策大学院の高原明生教授は中国が尖閣諸島の領有権を主張する動きを強めていることについて「中国が主権を主張する立場から降りることはありえない。国力の増大とともにみずからの領土だと主張し続けながら周辺でのパトロールを強化し、いつかは自分の実効支配のもとに置きたいと考えているのだろう」と分析しています。
そして中国の戦略についてサラミを薄く、少しずつ切っていくことに例えて「『サラミ・スライシング』、実力をもって少しずつ状況を変えていくのが彼らの全般的なプランだ。
派遣する船や回数を増やし実効支配を徐々に奪っていくのが大きな方針だろう」と指摘しています。
また、日本が取るべき対応については「日本側もできるかぎり、海上保安庁の能力を強化するといった対応が必要だ。日本と同じような状況にある国も多いので他の国々と連携を深めてネットワークを広げていくことも当然やるべきだ」などと話しています。
そのうえで尖閣諸島周辺の海域で今後、日本と中国の船舶が偶発的に衝突する可能性もあるとして「万が一発生した場合にはどう対応するかということを含めて、お互いによく話し合っておく必要がある」として両国の当局間の意思疎通が重要だとしています。