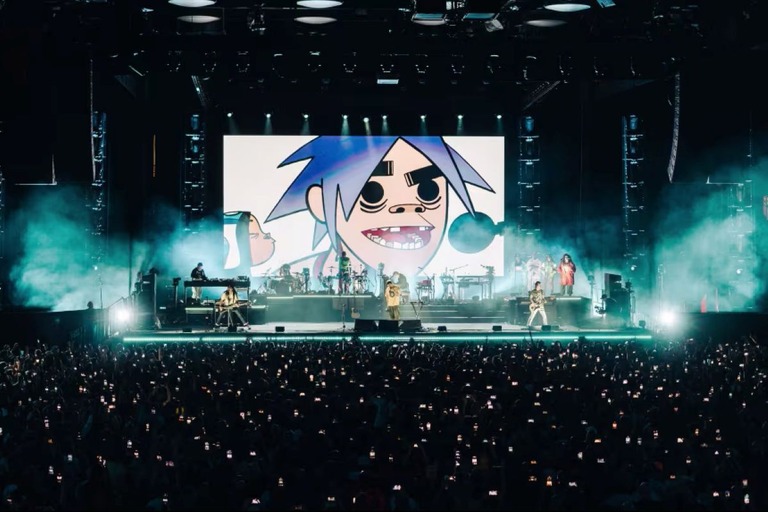文化勲章
文化勲章を受章するのは次の6人の方々です。
大手化学メーカー「旭化成」の名誉フェローの吉野彰さん(71)。
吉野さんは、現在のリチウムイオン電池の原型となる新たな電池を開発しIT機器の普及や、環境問題への解決に貢献したことが評価され、ことしのノーベル化学賞の受賞者に選ばれました。吉野さんは、文化功労者にも合わせて選ばれています。
 東京大学名誉教授で数理工学が専門の甘利俊一さん(83)。
東京大学名誉教授で数理工学が専門の甘利俊一さん(83)。
甘利さんは、世界に先駆けて情報幾何学をはじめ、独創的な研究と後進の育成に貢献したことが評価されました。
 大阪大学栄誉教授で免疫学が専門の坂口志文さん(68)。
大阪大学栄誉教授で免疫学が専門の坂口志文さん(68)。
坂口さんは、免疫による病気の仕組みの解明に取り組み、生命科学の新しい分野を確立したことが評価されました。
 東京大学名誉教授で政治学が専門の佐々木毅さん(77)。
東京大学名誉教授で政治学が専門の佐々木毅さん(77)。
佐々木さんは、政治思想家の研究で、卓越した業績を上げるとともに現代政治の分析で、顕著な業績をあげたことが評価されました。
 写真家で、東京工芸大学名誉教授の田沼武能さん(90)。
写真家で、東京工芸大学名誉教授の田沼武能さん(90)。
田沼さんは、報道写真家として、半世紀を超えて作品を発表し続け、後進の育成にも尽力したことが評価されました。
 能楽師の野村萬さん、本名、野村太良さん(89)。
能楽師の野村萬さん、本名、野村太良さん(89)。
長年にわたり、技や芸の向上にまい進し、狂言の芸術性を広めたことが評価されました。
文化功労者
文化功労者に選ばれたのは次の方々です。
映画評論家の佐藤忠男さん。本名、飯利忠男さん(89)。
照明デザイナーの石井幹子さん(81)。
経済学が専門の猪木武徳さん(74)。
歌人の馬場あき子さん、本名、岩田暁子さん(91)。
 俳人の宇多喜代子さん(84)。
俳人の宇多喜代子さん(84)。
映画監督の大林宣彦さん(81)。
ロボット工学が専門の金出武雄さん(74)。
中国古典文学が専門の興膳宏さん(83)。
 国語史学が専門の小林芳規さん(90)。
国語史学が専門の小林芳規さん(90)。
生物学が専門の近藤孝男さん(71)。
日本財団会長の笹川陽平さん(80)。
 植物科学が専門の佐々木卓治さん(72)。
植物科学が専門の佐々木卓治さん(72)。
日本画家の田渕俊夫さん(78)。
舞踏家の宮城能鳳さん、本名、徳村正吉さん(81)。
 漫画家の萩尾望都さん(70)。
漫画家の萩尾望都さん(70)。
日本障害者スポーツ協会元理事の藤原進一郎さん(87)。
ゲームプロデューサーの宮本茂さん(66)。
 歌舞伎俳優の坂東玉三郎さん、本名、守田伸一さん(69)。
歌舞伎俳優の坂東玉三郎さん、本名、守田伸一さん(69)。
分子薬理学が専門の柳沢正史さん(59)。
音楽プロデューサーの渡邊美佐さん(91)。
文化勲章の親授式は来月3日に皇居で、文化功労者の顕彰式は来月5日に都内のホテルでそれぞれ行われます。
吉野さん「芸術・文化にさらに貢献したい」
 吉野さんは大阪 吹田市出身。
吉野さんは大阪 吹田市出身。
京都大学の大学院を修了後、「旭化成」に入社し、昭和60年、現在のリチウムイオン電池の原型となる新たな充電池の開発に成功しました。
リチウムイオン電池はその後、IT機器の普及に欠かせないものとなったほか、太陽光発電など自然エネルギーの技術にも応用され、環境問題の解決に道を開きました。
文化勲章の受章について吉野さんは「ノーベル化学賞も含めてこれまで頂いた賞は科学技術に関するものだったが、文化全般に対しての貢献ということで今までとは重みが違い、非常にありがたく思っている。リチウムイオン電池で環境問題に対する答えを出していくことで芸術・文化に対してさらに貢献していきたい」と感想を述べました。
そのうえで、ことし12月にスウェーデンのストックホルムで行われるノーベル賞受賞の記念講演について「30分間の講演だが、環境問題に対する道しるべを与えられるようなメッセージを世界に向けて発信したい。忙しい毎日だが、そろそろ講演の資料作りに入りたい」と意気込みを語りました。
坂口志文さん「何かの役に立つと思って続けてきた」
文化勲章を受章する、大阪大学免疫学フロンティア研究センター特任教授の坂口志文さんは、滋賀県長浜市出身の68歳。昭和51年に京都大学医学部を卒業して以来、免疫に関する研究に取り組み、平成7年に過剰な免疫反応を抑えるリンパ球の一種、「制御性T細胞」という細胞が存在することを突き止め、世界的に高く評価されました。
さらに、「制御性T細胞」の数を減らしたり働きを抑えたりすると、がん細胞に対する免疫を強化できることや、逆に、この細胞を増やしたり働きを活発にしたりすると、臓器移植に伴う拒絶反応を抑える効果があることなどを明らかにしました。
こうした業績により、坂口さんはおととし文化功労者に選ばれたほか、平成27年に医学分野の研究で優れた業績をあげた人に贈られるカナダのガードナー国際賞を、おととしにはノーベル賞の受賞者を決めているスウェーデン王立科学アカデミーが選ぶクラフォード賞を受賞しています。
坂口さんは会見で「研究が認められてうれしく思います。研究を始めた頃は、注目されるファッショナブルな分野ではありませんでしたが、いずれ何かの役に立つと思って研究を続けてきました。最近、人への応用も含めて研究が進んできたことが、認められたのではないかと感じています。現役の研究者として受章を励みに頑張りたいです」と話していました。
野村萬さん「これからも精進」
 能楽師の野村萬さんは東京出身。
能楽師の野村萬さんは東京出身。
人間国宝だった六世野村万蔵さんの長男として生まれ、4歳で初舞台を踏んだあと、昭和25年には四世「万之丞」を、平成5年には七世「万蔵」を襲名し、伝統芸能としての正統派の狂言を受け継いできました。
むだのない体の動きと登場人物の深い人間性がにじみ出る演技で高い評価を受ける一方、新作狂言の上演や、NHKの連続テレビ小説「おしん」や大河ドラマ「翔ぶが如く」に出演するなど活動の幅を広げてきました。
平成12年、70歳の時に「万蔵」の名を息子に譲って「野村萬」を名乗り、後継者の育成にも尽力するかたわら、狂言の普及にも努めています。
平成9年には重要無形文化財保持者、いわゆる人間国宝に認定され、平成20年には文化功労者にも選ばれています。
野村さんは「新しい時代の最初の年に文化芸術最高の賞を頂けることは、伝統芸能に携わる身として本当にありがたい。能を大成させた世阿弥の『老木に花の咲かんがごとし』ということばのように、少なくなっても味わいのある花を舞台に咲かせられるように、これからも精進していきたい」と話していました。
佐藤忠男さん「映画を通じ世界全体を見渡せる」
文化功労者に選ばれた映画評論家の佐藤忠男さんは新潟県出身。
高校を卒業後、雑誌に映画批評を次々と投稿し、昭和37年からフリーの映画評論家としての道を歩み始めました。
「小津安二郎の芸術」や「大島渚の世界」など映画に関する多くの著作があり、平成7年には100年以上に及ぶ日本の映画史を20年がかりでまとめた「日本映画史」を発表して、高い評価を受けました。
大衆芸能や演劇などにも評論活動の幅を広げてきたほか、国際映画祭にも積極的に参加して、映画を通じた国際交流にも貢献しています。
平成8年には日本映画大学の前身にあたる映画の専門学校、日本映画学校の校長に就き、みずからも教壇に立って若い映画人を育ててきました。
平成8年に紫綬褒章、平成14年に旭日小綬章を受章しています。
佐藤さんは「受章を聞いて驚いているが、自分のこれまでの功績として、ほかの人が見ないような、世界の小さな国々のいい映画を発見してきたことが公に評価されたことをうれしく思う。いろんな国の映画を見ることでまだ知らない世界を知ることにつながると思うので、これからも映画を通じて世界全体を見渡せることができるということを訴えていきたい」と話していました。
石井幹子さん「景観と調和の取れた明かりを」
 文化功労者に選ばれた照明デザイナーの石井幹子さんは東京出身。
文化功労者に選ばれた照明デザイナーの石井幹子さんは東京出身。
東京藝術大学を卒業したあとヨーロッパにわたって照明デザインを学び、帰国後、建築や都市の照明デザインに携わるようになりました。
日本の照明デザインの第一人者として長年活躍し、平成元年に手がけた東京タワーのライトアップでは、暖かみのあるオレンジ色の光でタワーを浮かび上がらせ、現在まで東京の夜景のシンボルとして親しまれています。
ほかにも、東京のレインボーブリッジや東京駅、浅草寺などのほか、姫路城や長野市の善光寺など、さまざまな建造物のライトアップを手がけています。
また、岡山県倉敷市の町並みや岐阜県の白川郷の合掌集落など各地の名所を光で彩り、町づくりや観光振興にも貢献してきました。
平成12年には紫綬褒章を受章し、去年手がけたフランスのエッフェル塔のライトアップでは葛飾北斎の浮世絵など日本美術の意匠を投影して話題を集めるなど、世界各地で活躍を続けています。
石井さんは「照明デザインという分野を一生懸命つくってきたことがこのように認められて本当にうれしいです。日本人が大事にしてきた明かりは満月の夜の清らかな優しい光ではないかと思います。そうした、柔らかく、周辺の景観と調和の取れた明かりをこれからも目指していきたいです」と話しています。
大林宣彦さん「プロデューサーの妻に感謝」
 文化功労者に選ばれた映画監督の大林宣彦さんは広島県尾道市出身。
文化功労者に選ばれた映画監督の大林宣彦さんは広島県尾道市出身。
10代のころから自主製作の映画を撮り始め、大学を中退後、テレビコマーシャルの世界で活躍し、昭和52年に『HOUSE』で商業映画デビューして、独特な映像美で若者に熱狂的に迎えられました。
昭和57年からは、ふるさとの尾道を舞台に少年少女の情感をみずみずしく描いた『転校生』『時をかける少女』『さびしんぼう』の「尾道3部作」を続けて公開し、地域での映画製作の成功例としても注目されました。
華麗な映像表現で幻想的な作品を数多く生み出し、平成16年には紫綬褒章、平成21年には旭日小綬章を受章しています。
70歳をすぎてからは戦争をテーマにした作品を続けて発表し、平成28年にがんが見つかってからも闘病しながら映画製作を続けています。
大林監督は「妻のおかげでこういう晴れ舞台に立てました。心から感謝しています」と、長年プロデューサーとして二人三脚を続けてきた妻へ感謝を述べたうえで、日本の戦争の歴史を描く最新作『海辺の映画館-キネマの玉手箱-』に触れながら、「戦争からは誰も逃げられないように、私も戦争で殺された人たちの尊い命の記憶から逃げ出すわけにはいきません。死なねばならなかった人たちの記憶を、ひと事ではなくわがこととして描ききろうと思って作った映画です」作品に込めた思いを語っていました。
萩尾望都さん「読者に、編集に、友人に助けられ」
文化功労者に選ばれた漫画家の萩尾望都さんは福岡県出身。
昭和44年に漫画家としてデビューし、昭和47年に発表した「ポーの一族」では永遠に生きる少年の吸血鬼の運命を鮮烈に描いて人気を集めました。
その後も、ドイツの学校を舞台に少年たちの悲しみや純粋な愛情を描いた「トーマの心臓」や、体がつながって生まれた姉妹が主人公の「半神」などを発表し、それまでのファンタジーやSF漫画の領域にとらわれない文学性が高く評価されています。
平成23年からは女子美術大学の芸術学部で客員教授を務め、後進の育成にも力を入れています。
平成24年には紫綬褒章を受章しています。
萩尾さんは「読者に、編集に、多くの友人に助けられ励まされて今があります。そしてたくさんの漫画家の先輩方の切り開いた道をたどってきました。この仕事を選び、この道をたどることができたことをうれしく思います。これからも同じように歩んでいきたいと思います」とコメントしています。
坂東玉三郎さん「これからも舞台芸術のために」
文化功労者に選ばれた歌舞伎俳優の坂東玉三郎さんは東京出身。
昭和39年に五代目坂東玉三郎を襲名し、当たり役となる「桜姫東文章」の桜姫や「助六」の揚巻など古典の大役を次々と演じ、歌舞伎界を代表する女形として活躍を続けています。
美しく品格のある高い演技力で知られ、平成24年には重要無形文化財保持者、いわゆる「人間国宝」に認定され、平成26年には紫綬褒章を受章しています。
海外でも数多くの歌舞伎公演を行い、世界的なアーティストと共演を重ねるなど国際的にも高い評価を得て、平成25年にはフランスの芸術文化勲章の最高章を受章しています。
玉三郎さんは「身に余る光栄でございます。これからも舞台芸術のために、できるだけの事をしてまいりたいと思っております。舞台創りとしての演出や指導などにも最大の力を尽くしていきたいと考えております」とコメントしています。
宮本茂さん「自分たちがおもしろいと思うものを」
文化功労者に選ばれたゲームプロデューサーの宮本茂さんは、京都府南丹市出身の66歳。
金沢美術工芸大学を卒業後、昭和52年に任天堂に入社し、キャラクターデザインなどを手がけながらゲーム制作を始めました。「ドンキーコング」や「スーパーマリオブラザーズ」「ゼルダの伝説」といった数々のヒット作品を発表して国内外でファミコンブームをけん引しました。
情報開発本部長や専務を歴任して任天堂のゲーム開発を率い、「ニンテンドーDS」や「Wii」など新たな遊び方を提案するゲーム機を世に送り出しました。
日本のゲーム文化は今や漫画やアニメと並ぶ世界的なコンテンツとなり、「現代のビデオゲームの父」として、アメリカやヨーロッパでも数々の賞を受賞しています。
宮本さんは「ゲームは大勢で作り、いろんなチームとも仕事をするので、個人で頂くというのがとても照れ臭いです。こういうジャンルにも日を当ててもらえるというのはとても光栄なことですので、謹んでお受けすることにしました」と述べました。
ゲーム制作への姿勢については「世界で売ってやろうとか思ったことはなく、自分たちがおもしろいと思うものを作り続けてきたら世界で売れていった。日本ではやっているものや売れているものが何かよりも、自分たちが作りたいものや何が新しいのか何が面白いのかということだけ考えて作ってきました」と説明しました。
そして「こういう賞をいただくと過去を振り返ってしまいそうですが、あすは何を作るかということにエネルギーを出せるように頑張っていきたい」と抱負を語っていました。