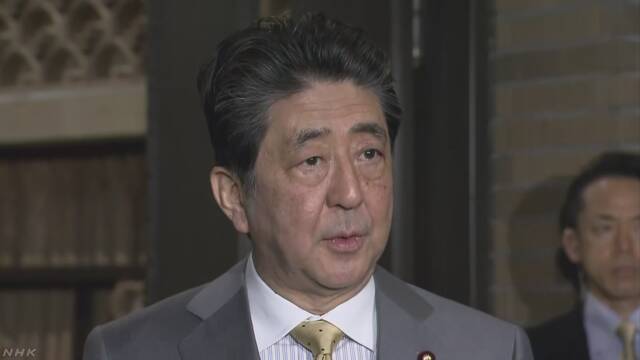福島第一原子力発電所の
事故からまもなく
9年となるのを
前に、
廃炉を
テーマにしたシンポジウムが
福島県で
開かれました。
福島第一原発の
廃炉について、
国や
東京電力は30
年から40
年かかるとしていますが、
廃炉の
形や
発生する
放射性廃棄物の
処分など具体的なことは
まだ示されていません。
これについて26日、福島県楢葉町でシンポジウムが開かれ、日本原子力学会の宮野廣氏が、廃炉の選択肢として施設すべてを撤去しさら地にするケースや、施設の地下部分は残して土で覆うケース、また放射線量を減らすためより長期間施設を保存したのちに撤去するケースなどを説明しました。
そして、それぞれ費用や期間、放射性廃棄物の発生量などが変わるとして、「地域に関わることなので、住民が議論に参加することが重要だ」と指摘しました。
その後地元の高校生などを交え討議が行われ「原子力の話題はタブーのようなイメージがある。議論の門戸をより開いてほしい」とか、「施設がなくなりさら地になってしまうと、事故の教訓を語るよすがをなくしてしまうのではないか」などさまざまな意見が出されていました。
主催した早稲田大学大学院の松岡俊二教授は「情報を地域にしっかり出して、どんな廃炉が日本や世界にとっていいのかもっと議論するべきだと思う」とシンポジウムのねらいを話していました。