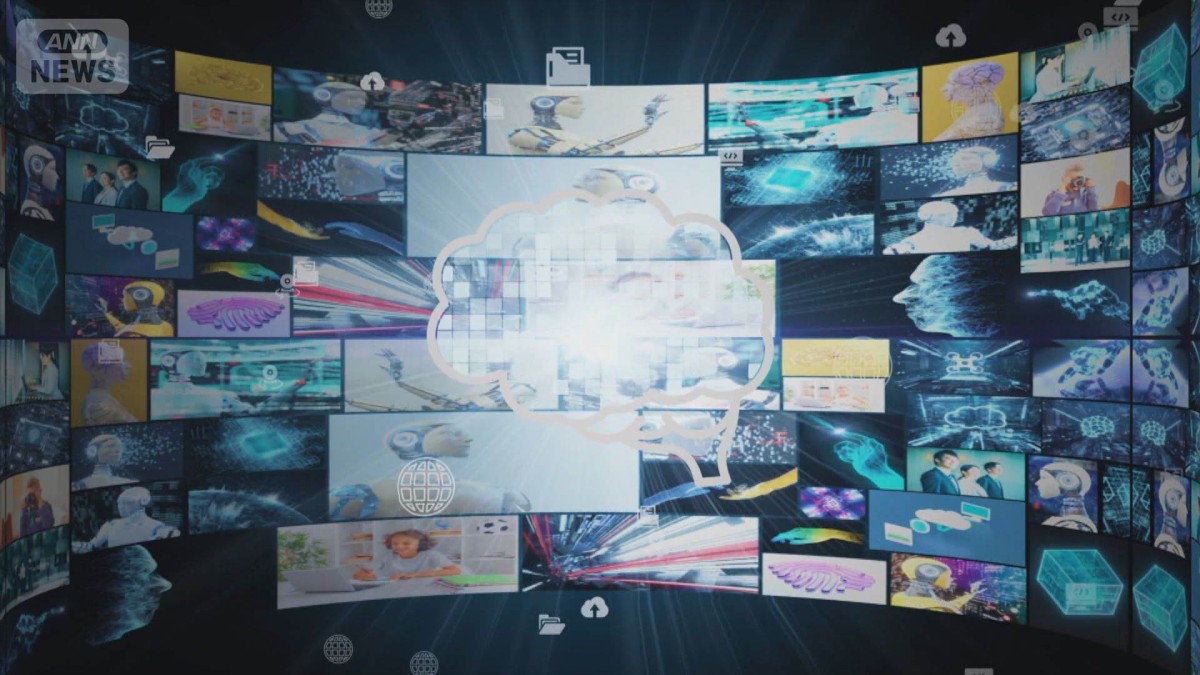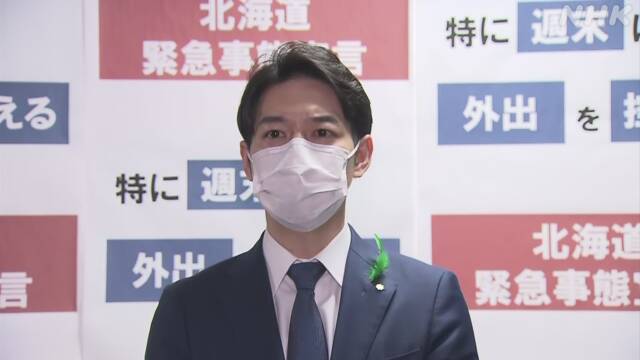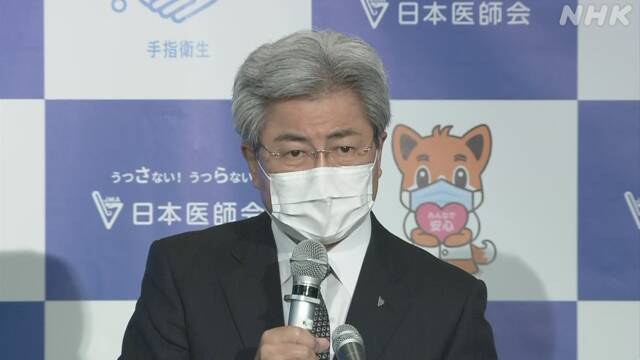また
▽日本陸上競技連盟が初めて行った調査では警察に通報や相談をした関連団体が半数を超えたほか
▽5月にはテレビ番組の画像をアダルトサイトに無断転載したとして関連する事件として初めて立件されました。
こうした中、今月23日、スポーツに関わる法律を研究する団体がシンポジウムを開き実態や対策を議論しました。
元競泳の日本代表で、オリンピックにも2度出場した伊藤華英さんは「胸のあたりや水から上がる瞬間をねらわれて雑誌などに載せられた。SNSで卑わいなメールが送られる被害もありブロックしても別のアカウントから送られるなど怖い思いをした」と経験を語りました。
弁護士からは
▽盗撮を取り締まる法律がなく都道府県の条例も罰則が軽いうえ
▽民事での慰謝料の請求も手続きが煩雑だとして
諸外国に比べ法整備が遅れている日本の現状が指摘されました。
また、指導者の問題も議論され伊藤さんが「親には言えず監督やコーチに勇気を振り絞って相談するので『女性だからしかたない』という対応だけはしないでほしい」と訴えると、2次被害を生まないよう競技を横断した相談窓口や指導者への研修の充実が必要だと意見が出されました。
最後に
▽法整備を早急に行うこと
▽誰もが安心してスポーツができる環境を各組織や競技団体が作る必要があることなどを提言しました。
性犯罪の適切な処罰の在り方を議論してきた法務省の検討会が、先週まとめた報告書にも盗撮や画像の拡散を取り締まる法整備が必要だと盛り込まれています。
京都府の37歳の自営業者はおととし、テレビのスポーツ番組で放送された複数の女性アスリートの画像、合わせて39点をみずからが運営するアダルトサイトに無断で転載したとして著作権法違反の疑いで逮捕され、今月20日に罰金60万円の略式命令を受けました。 警視庁によりますと、運営していたのは9つのサイト。 このうち少なくとも4つのサイトに女性アスリートの画像が卑わいなことばとともに掲載されているのが確認されたということです。 サイトの運営で得た広告収入は、ことし3月までの10年間で少なくとも1億2000万円に上るとみられています。 この自営業者は調べに対し「生活費を稼ぐため話題性のある画像を掲載していた。悪いことだという認識はあったが逮捕されるとは思わなかった」と話していたということです。 アスリートが盗撮されたり、画像がインターネット上に性的な目的で拡散されたりする被害が相次ぐ中、警視庁はJOC=日本オリンピック委員会からこれまでにおよそ1000件の情報提供を受けて捜査を進めてきました。 しかし、立件は難しいのが現状だということです。 まず、刑法には盗撮そのものに関する規定がありません。 このため盗撮行為については都道府県の迷惑防止条例が適用されるケースが多くなっていますが、捜査関係者によりますと盗撮の対象は服で隠されている下着などの部分に限られ、アスリートの競技中の姿は対象にならない可能性が高いということです。 また、画像の拡散についても、わいせつな画像ではないため直ちに取り締まることは難しいとしています。 捜査関係者によりますと、今回はサイトの中にテレビで放送された画像が含まれていたことから著作権法違反の容疑が適用できると判断し、逮捕に踏み切ったということです。 一方、盗撮された画像が卑わいなことばとともに掲載されていた場合は名誉毀損罪や侮辱罪にあたる可能性がありますが、被害者が告訴しなければ罪には問われません。 被害者にとっては「自分と特定されてしまうのではないか」「家族などに知られたくない」という思いが強く、被害の申告をためらうアスリートも少なくないということです。 警視庁の幹部は「アスリートの盗撮画像を扱う悪質なサイトがはびこっているのが分かっていても法律の壁があるうえ、被害者の協力を得られなければ立件はできない。一方で被害を申告することでさらに傷ついてしまうという2次被害の問題も考慮しなければならず、歯がゆい思いだ」と話しています。
このうち、サイト上で陸上や水泳、テニスなどの競技別にアスリートの画像や動画を販売している人物は、20年以上前からサイトの運営だけで生計を立てているといいます。 摘発を逃れるためみずからは撮影せず、第三者から画像などを買い取って販売する形をとっているということです。 撮影の分野はアスリートを対象にした「スポーツ系」やイベントに参加する女性を対象にした「イベント系」などさまざまで、撮影者の多くは複数の分野を掛け持ちして収入を得ているということです。 この人物はみずからの収入は明らかにしませんでしたが、アスリートの画像などを扱うサイトの現状について「かつてはマニアが購入するにすぎない世界だったがインターネットが普及したことで関連するサイトが続々と出現し、マニア以外の人にも広がっていったのではないか。動画サイトなどではかつてとは比較にならないクリック数になっている」としています。 また、法律に違反する可能性については「現行の法律では服を着た状態で撮影した画像などは問題がないと考えている。下着が写りこんでいる場合でも撮影者がその場で逮捕される可能性はあるが、販売者は罰せられないのではないか」としたうえで「世の中は不条理や悪行に満ちており一掃するのは不可能だ。少々なら仕方がない」とみずからの主張を述べました。 一方、別のサイトを運営する人物はアスリートの画像などを扱う理由について「撮影が許可された場所から撮った写真は法律による規制の対象外と考えているからだ」としたうえで「今後、規制が強化されたらサイトを閉鎖するだろう」と答えました。
女性が初めて被害に気付いたのは大学に入ったころで、会場に来ていた友人から「前にいた人があなたのお尻をアップにした写真を撮影していた」と教えられ驚いたといいます。 さらに、大会で成果を出し注目されるようになると写真に卑わいなことばをつけて拡散されたり、自身のSNSに送りつけられたりすることもあったといいます。 当時を振り返り女性は「写真や動画に『お尻が大きくて好き』とか『下着が透けていてエロい』といったことばが貼られていて気持ちが悪かった。大会中も自分がどう切り取られるのか、被害にあうのではないかと意識してしまいます。疲れてひざに手を置く時さえもお尻をカメラに向けないよう意識する現状で常に5%くらい頭の片隅にあるので影響はゼロではないです」と苦痛を訴えました。 その後も、自分やほかの選手へのSNSによる被害が深刻化し、社会人選手だけでなく中学生や高校生にも被害が生じていたことから、女性は去年8月、別の選手と2人で日本陸上競技連盟に被害を訴えました。 しかし、それが報じられるとインターネット上には『そんな格好をしているほうが悪い』とか『陸上みたいなマイナーなスポーツはそうやっていかないと観客が入らない』といったコメントが相次いだと言うことで、女性は「心ないコメントが結構あり、そういう考え方の人がいるとわかってはいたがこんなにも多いのかとショックでした」と振り返りました。 また、日本陸連に伝えるまで何年も被害の相談をできなかった経験から、競技団体側の課題も指摘し「当時、人に言うのはタブーなのかなという雰囲気を感じたし『言ったところで誰が解決してくれるのだろう』という思いもあり、声を上げることも相談することもしなかった。今まで野放しにされてきた部分でもあり最終的に相談した時も『そんなことあるのか』という声が競技団体からあった。これだけ被害が多いのに知らないこと自体、問題ではないかと思いました」と競技団体や指導者にも対処してほしいと訴えました。 そして「中学生、高校生が被害に遭うことも絶対にあると思いますし、自分が目指していた選手が被害にあっているのを見て気持ち悪くて競技自体に嫌悪感を持ってしまうこともあると思います。取り締まるための法整備が進んでほしいという思いがいちばんです」と話していました。
事例としては ▽競技会場でのカメラの望遠機能を使った盗撮や ▽ネット上で画像を加工したり卑わいなことばとともに拡散したりするもの ▽SNSを通じて直接、選手個人に卑わいなメッセージを送るものと 大きく3つがあるといいます。 中には ▽一般の高校生や大学生の加工画像の拡散や ▽選手の個人情報や出身校を書いたものもあったといいます。 工藤弁護士は「盗撮被害は20年くらい前から認知され始めたが最近はSNSや動画投稿サイトの普及によりネット上での被害が非常に増えている。加害者はいずれも匿名で極めて卑劣な行為だ。選手はなぜこんなことをされるのかとショックを受け、それが原因で競技を続けたくないと思ったりベストを発揮できなくなったりした選手もいる」と影響の深刻さを話しました。 法的な対応を検討したものの ▽盗撮は刑法に規定がなく条例での対応も罰則が軽いうえ、ユニフォームの上からの撮影が罪にあたるか判断が難しいといい ▽性的な画像も拡散行為を罰する法律はなく名誉毀損罪や侮辱罪での立件も加害者の特定に時間がかかり、罰則も軽い中で適用されたケースはないといいます。 工藤弁護士によりますとアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、それに韓国などには盗撮を処罰する法律があり、イギリス以外の国では撮影した画像の拡散も処罰の対象になるということで、韓国ではアスリートに対する盗撮で検挙された事例もあるとしています。 工藤弁護士は「世界中で問題になっていて海外ではすでに法律でしっかり規制している国も多数ある。しかし日本では警察に被害を持ち込んでも『ひどい行為だが今の法律では難しい』と言われてしまう。被害が表面化せず救済もされない状態で迅速な立法が極めて重要な課題だ」と指摘しています。
スポーツとジェンダーが専門の明治大学の高峰修教授は「問題は20年以上前から指摘されており、一部の団体を除きスポーツ界全体としては具体的な対策を取るのに時間がかかりすぎている」と対応の遅さを指摘したうえで「これまでスポーツの領域ではむしろアスリートを使って消費者の性的な欲望を刺激してきた、性を商品化してきた側面がある」という見方を示しました。 高峰教授によりますとIOC=国際オリンピック委員会が2018年に公表した「ジェンダー平等報告書」では、ユニフォームが技術的な必要性を反映し、男女間で不当な違いがないよう勧告しているということです。 しかし「例えばビーチバレーのユニフォームは最近でこそバリエーションが増えてきたが、男性はランニングシャツとハーフパンツの一方で女性はビキニタイプなどと規定された時期があった。ルール上の違いはネットの高さだけなのに形状がここまで違うのは、競技に関係ない側面が影響していると考えるのが合理的だ。他の競技も含め本当は露出の多いものを着たくないが、状況的に着ざるをえないアスリートがいることを考えるべきで、中学生の部活などでも特に配慮が必要だ」として、選手自身が選択できることが大事だと話しました。 メディアについても「アスリートの性的な写真を売りにした雑誌が販売され、イケメンとか美女とか『美しすぎる』と言う表現がごく当たり前に使われていて、この20年、一向に変わる気配がない。細かい描写の蓄積が今の状況を作り出しており責任は大きい」と指摘しています。 今後に向けては「被害を防ぐ法的な取り組みはもちろん重要だが、この問題をきっかけにスポーツ界としても性の商品化についてもう一度振り返る必要がある。そして性的な画像の問題に限らずさまざまなハラスメントからアスリートや関係者を守る、人権を守る役割を強く意識してほしい」とスポーツ界にも意識改革を求めています。
警視庁が初摘発 一方で立件には壁も

サイト運営者「一掃するのは不可能」と主張
被害にあったアスリートは

弁護士「SNSや動画投稿サイトの普及で被害増」
法整備が必要な一方でスポーツ界全体の意識改革も