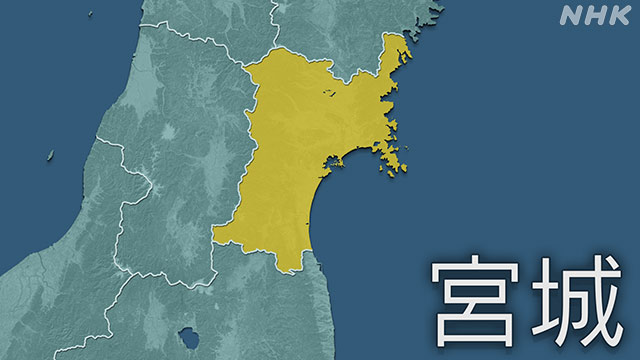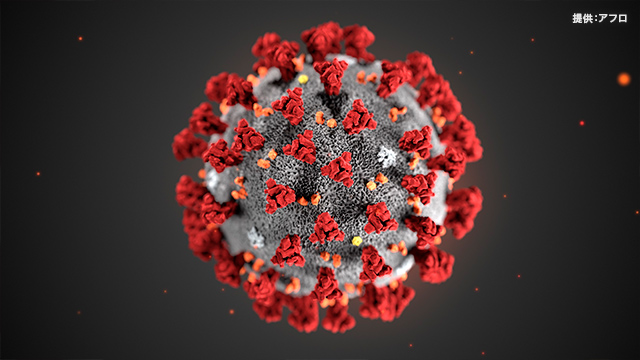その結果、この春、公立高校を卒業した生徒のうち、家族の介護やケアが原因で希望の進路を諦めたケースは少なくとも17%にあたる24の高校で合わせて44人に上りました。
また、家族の介護などが原因で進学や就職に悩んでいることを打ち明けられるなどしたケースは少なくとも46の高校で合わせて126人に上りました。 「ヤングケアラー」をめぐっては埼玉県が行った調査で、高校2年生の25人に1人が該当することが明らかになっていましたが進路への影響はわかっていませんでした。
そのうえで「日本の場合、ある年齢の時にこのステップを踏まければいけないと固定化されているところがありそこにうまく乗れないと社会のメインストリームからこぼれ落ちてしまい、なかなか復活できない現実があり、進路を断念する子どもの存在は、看過できない問題だ」と話しています。 求められる対策については「先生が家庭の内部事情に踏み込めない状況はわかるので、スクールソーシャルワーカーを通じて、福祉分野の支援につないでいくなどの仕組みを作ることや、学校に設ける相談窓口でいつでも相談できる雰囲気作りなど、窓口を明確にしておくことが大切だ」と指摘しています。 さらに、介護の現状の問題点について「社会で支援する体制にまだ不備があり、家族や子どもが行わざるをえない状況になっている。家族のケアがなくても生活できる支援体制を考えていく必要がある」と話しています。
吹奏楽部に入っていましたが、祖父の病院の手続きなどで部活を休む日が続き、目標にしていた高校2年生の夏の大会を目前に辞めざるを得なくなりました。 夜になると認知症の祖母が外をはいかいするようになり、深夜に警察から、引き取りに来るように何度も呼び出され、なぜ見ていなかったのかたびたび怒られたと言います。 夜遅くまで続く介護で通常の授業すらも、次第に遅刻や早退をせざるをえなくなり、学校の先生に状況を説明しましたが、「もっとまともなうそをつけ」と取り合ってもらえませんでした。 それでも環境保全の勉強をしたいという夢を諦めることはできず、祖父母の枕元で必死に受験勉強を進め、第一志望だった国立大学に合格しました。 しかし、両親が共働きで忙しいなど家庭の事情で、祖父母の世話をする人が自分しかいなかったため、諦めざるをえませんでした。 麻衣さんは、当時の心情について、「介護が無ければ合格した大学に行けたという現実を目の前にしてこれまで学校生活が制限されつらかった気持ちから、怒りに変わりました。合格通知書をもう見たくないとシュレッダーにかけボロボロ泣きました」と話しています。 その後、後期試験で地元の大学を受け直し、進学しましたが、当初の希望とは全く違う分野でした。 麻衣さんは、高校卒業から7年たった今でも、合格発表や入学式が行われるこの時期になると、介護が原因で、希望の進路を諦めたことを思い出し、胸が痛くなると言います。 麻衣さんは「高校時代は学校で起きることがすべてで介護していることで、他の子と違う道を歩まざるを得なくなることがつらく怖かった。高校時代にできることは、戻ってこないので、なくした物は大きいと思います」と話しています。
1つは、学校が家庭内の問題にどこまで踏み込んでいいか分からないといった声です。 「生徒や保護者から学校へ相談してくれれば対応できるが家庭内の状況を聞くことが難しい時代になっている」。 「生徒がその悩みを話してくれるとは限らず、話してくれたとしても、教員としてどこまで家庭内のことに踏み込んでよいのか、悩ましい」。 「介護が当たり前になっていて、自分の進路に影響を及ぼしていることを本人が無自覚というケースもある。行政などの支援は充実していても、その情報が本来必要な家庭に届いていないし、家庭にもそういった情報にアクセスする力がない」。 さらに、経済的な問題をあげる声も聞かれました。 「入学金ができなくて進学を諦める生徒が多い。介護やケアで時間とお金が取られる状況だと思います」。 「進路を決める上での金銭的な問題について、市町村の公的ケアとどうつなげていくか、どう援助してもらうかで悩んだ」。 「経済的な状況で(進学などを)諦める生徒がいる。もしかしたら、私たちには見えていないが、その中に「ヤングケアラー」に該当する者もいるのかもしれない」。 また、情報共有の在り方や相談体制についての声も聞かれました。 「民生委員や公的機関との情報共有やどこまで関わってよいかの線引きが難しい」「学校以外に相談できる機関やパンフレット等のお知らせがあると指導しやすいと思った」。 「ヤングケアラーの程度がさまざまであるため、他の機関と相談する必要性を感じている」。
そのうえで、「ヤングケアラーという視点をこれまで教員も持てていなかったというのが事実なので、県教育委員会として教員に研修を行うなど正しい知識を身につけてもらい生徒一人一人が主体的に自分の進路選択ができるよう体制を整えたい」としています。

専門家 “氷山の一角 支援の仕組み作りを”
介護で進路希望を断念した女性
学校現場「どこまで踏み込んでよいのか」悩みも
県教委 「重く受け止めなければならない」



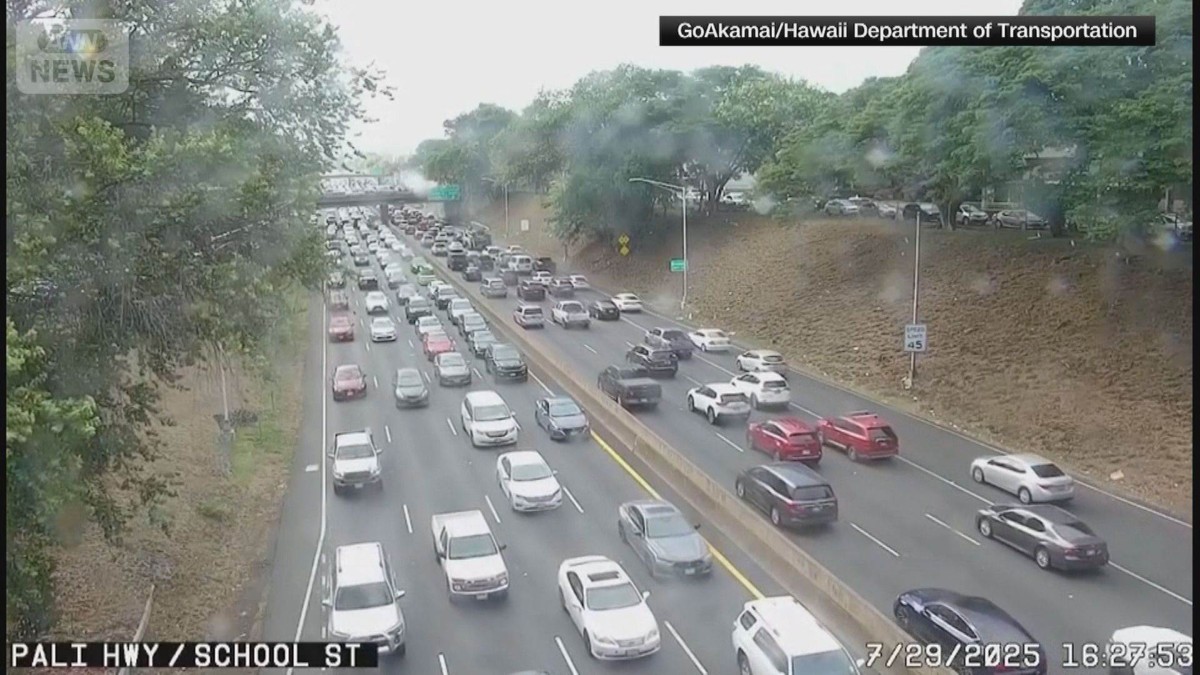






家族の介護などを行う子どもは「ヤングケアラー」と呼ばれていて、専門家は、「家庭状況を打ち明けられない子も多い中、数字は氷山の一角だ。早急な支援の体制作りが求められる」と指摘しています。