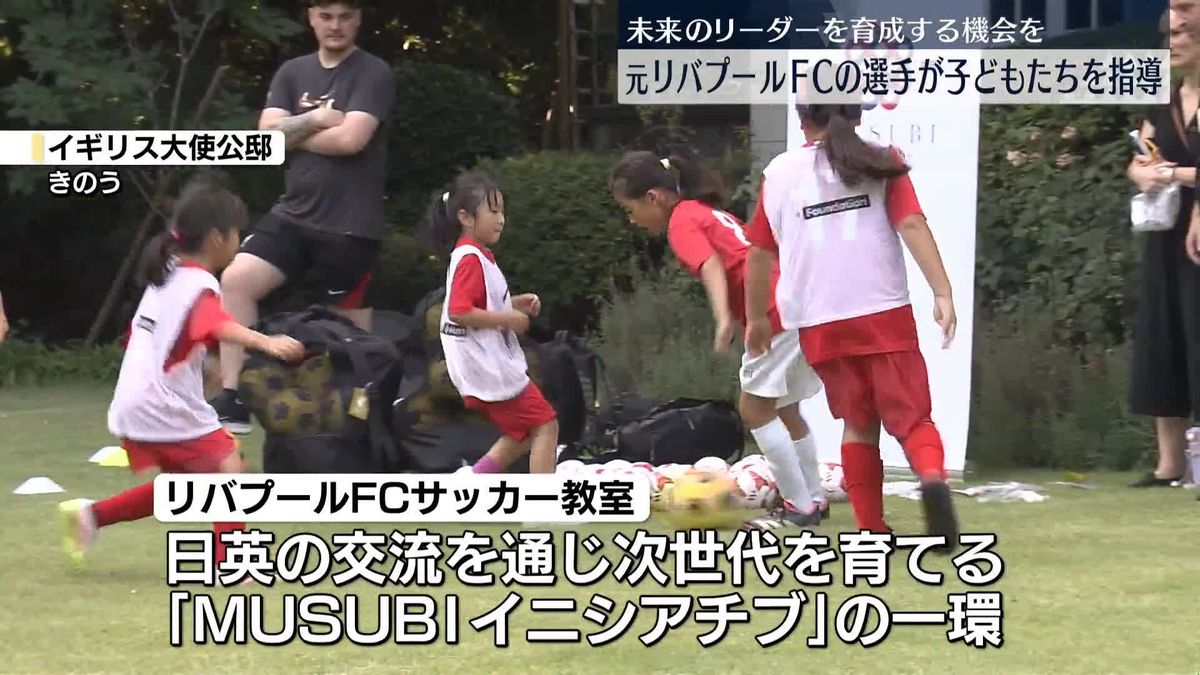それによりますと、ことし3月の時点で認知症の高齢者が保有する金融資産は143兆円に上るということです。
さらに、今後も高齢化が進むことで、2030年度には200兆円以上に達するとしています。
厚生労働省によりますと、認知症の高齢者は全国で500万人を超え、65歳以上の7人に1人が認知症だと推計されています。
老後のために蓄えておいた資産を認知症のため適切に使えなくなっているケースが出ているほか、家族が預金を引き出そうとしても本人の意思確認ができず銀行に断られてしまうケースも少なくないということで、対策が課題となっています。
 第一生命経済研究所は、国がまとめた認知症の人の割合や家計の貯蓄などのデータをもとに、認知症の高齢者が預貯金や株などの金融資産をどれくらい保有しているか推計しました。
第一生命経済研究所は、国がまとめた認知症の人の割合や家計の貯蓄などのデータをもとに、認知症の高齢者が預貯金や株などの金融資産をどれくらい保有しているか推計しました。
それによりますと、ことし3月の時点で認知症の高齢者が保有する金融資産は143兆円に上るということです。
さらに、今後も高齢化が進むことで、2030年度には200兆円以上に達するとしています。
厚生労働省によりますと、認知症の高齢者は全国で500万人を超え、65歳以上の7人に1人が認知症だと推計されています。
老後のために蓄えておいた資産を認知症のため適切に使えなくなっているケースが出ているほか、家族が預金を引き出そうとしても本人の意思確認ができず銀行に断られてしまうケースも少なくないということで、対策が課題となっています。
資産蓄えたのに認知症で生活に支障も
老後のために十分な資産を蓄えたのに認知症のため生活に支障を来す高齢者が各地で相次いでいます。
現在は東京 世田谷区の有料老人ホームで暮らしている76歳の男性もその1人です。
男性は認知症と診断されていますが、世田谷区内のマンションで1人で暮らしていました。独身で長年にわたって食器メーカーの営業職として働き、老後のための資金を蓄えてきました。
ところが認知症のため次第に金銭管理ができなくなり、水道・電気などの光熱費や税金の支払いが滞って督促が届くようになっていたということです。
食事も満足にとれず、おととし自宅近くの道路で倒れているのを近所の人が見つけ、地域包括支援センターに連絡しました。それまで福祉や介護の手は届いておらず、マンションの室内は荒れ果てた状態だったということです。
その後、男性はヘルパーなどの介護サービスを受けて生活してきましたが、1人暮らしがさらに難しくなったため、ことし7月から施設に入ることになりました。
その際に福祉の担当者が男性の資産を正確に確認したところ、残高が1500万円と記載された預金通帳が見つかりました。ほかにも複数の口座があり、預金額は合わせて数千万円に上ることがわかりました。
このうち一部の口座については預金通帳がまだ見つかっていないため、今月も男性の立ち会いの下、マンションの室内を捜し回り、ようやく通帳を発見しました。
この預金について男性は「退職金だったと思うがよく覚えていない」と話していました。
男性は現在、毎月の料金がおよそ30万円の有料老人ホームに入居しています。預貯金の管理は施設がサポートしていて、男性は1日3食きちんと食べ、毎日、缶ビール1本を飲むのが楽しみだと言います。運動もして、健康状態がよくなり、表情が明るくなったということです。
男性は「今の生活は施設の中にみんないるので、孤独を感じなくていいと思います」と話しています。
男性が暮らす有料老人ホーム「らいふ経堂」の松村愛さんは「金銭管理は自分ではできない状態なので、本人としっかり話しをしてご自身のために使えるようにサポートしていきたい」と話しています。
判断能力低下に備え資産活用のサービスも
認知症などで判断能力が低下したときに自分の資産がきちんと医療費などに活用されるように、高齢者が事前に備えておく動きも広がっています。
東京 立川市に住む早川ミツヱさん(77)は、3年前に脳梗塞で倒れて左半身にまひがあり、八王子市の病院に通院してリハビリを続けています。
今後万が一、認知症になったり脳梗塞が再発したりして判断能力が低下した場合にも自分が望む治療を受けられるよう、病院から紹介された新たなサービスの利用を始めました。
このサービスは、信託銀行に口座を作ってあらかじめ預金しておくと、必要なときに病院などに直接口座から入院費や治療費が支払われる仕組みです。資産をどのように使ってほしいかや、判断能力が低下したときの財産管理を誰に任せるかなどを事前に登録することができます。
早川さんは、介護や医療にかかる費用を夫や子どもではなく自分の資産から出すとしたうえで、判断できなくなったときには夫に財産の管理を任せると登録しています。
早川さんは「いつどうなるかわからないので備えておくととても安心です。せっかく貯めたお金が認知症で使えなくなるのはもったいないことです。家族とも相談して元気なうちに決めておくことが大事だと思います」と話していました。
信託銀行とともにサービスを提供する「北原トータルライフサポート倶楽部」の責任者、浜崎千賀さんは「高齢者のお金の問題が年々、深刻化しているのを現場でも実感しています。人生の最期でみずからが望む医療を受けてもらえるようサポートしていきたいです」と話していました。
専門家「早い段階から準備を」
認知症高齢者の資産管理に詳しい慶應義塾大学の三村將教授は「1人暮らしの高齢者が増加し、認知症高齢者の資産管理は最近注目されはじめてきたが、今後、さらに多くの人が直面する問題だ。資産が有効に活用されないことは日本の経済にとっても大きな損失になる」と指摘しています。
そのうえで「家族がいても認知症の高齢者の資産管理を十分にサポートすることは難しく、銀行や郵便局など周囲で支えていく仕組みづくりが必要になる。高齢者自身も早い段階から認知症になったときに備えてどのように資産を使うのか自分の意思を示しておくことが大切だ」と話しています。