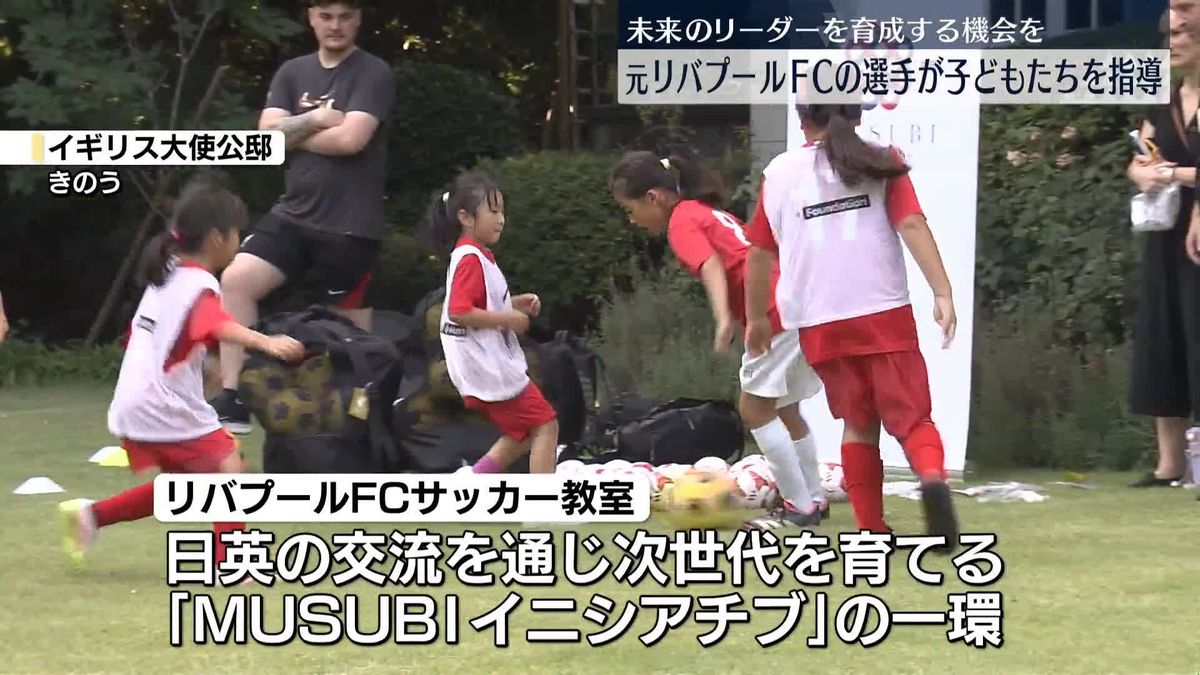調査会社の「富士経済」によりますと、アルコール度数が1%未満のビールやカクテル、それにチューハイなど、ノンアルコール商品のことしの市場規模は986億円で、新型コロナの感染拡大前のおととしと比べて20%近く増加すると見込まれています。
さらに、5年後の2026年には、1163億円まで拡大する見通しです。
こうした中、ビール大手各社の間では、需要の高まりに加え、若者のアルコール離れなどに対応しようと、ノンアルコールや、従来より度数を抑えた低アルコールの商品の投入を強化する動きが出ています。
このうちアサヒビールは、飲料全体の販売数量のうち、ノンアルコールと、アルコール度数が3.5%以下の低アルコールの商品が占める割合を、2025年までにおととしの3倍以上にあたる20%まで引き上げる目標を掲げています。
一方、新型コロナの感染状況が落ち着いて、客足の回復を期待する飲食店の間でも、酒の量を抑えたいなどという客のニーズに応えるため、ノンアルコールや低アルコールのメニューを充実させる動きが出ています。
東京 品川区の焼き鳥店では、レモンなどのサワードリンクについて、アルコールの度数をゼロ%から7%まで、5つの濃さを選べるサービスを導入しました。
その結果、お店によりますと、このサービスでノンアルコールや低アルコールの商品を選ぶ人の割合が、全体の2割近くに上るということです。
焼き鳥店のマネージャー古賀祐太郎さんは「そこまで酔っ払いたくないという人や、健康志向の高い方から注文してもらうことが多い。コロナで飲食店をめぐる環境は大きく変わったが、今後も社会の変化に対応したい」と話していました。