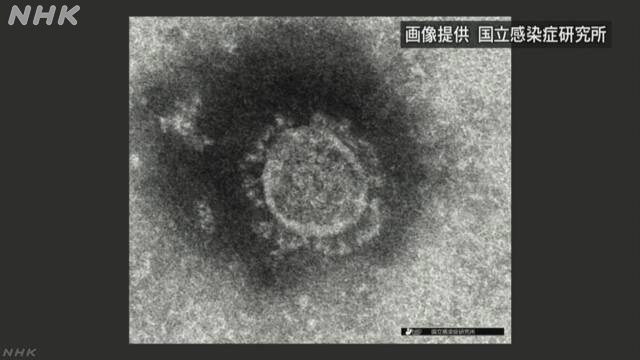「国家安全維持委員会」は、中国から派遣される顧問とともに治安情勢の分析や国家の安全に関わる政策の策定に当たるとしていて、関係機関の運用に向けた動きが本格化しています。
一方、香港では1日、大勢の市民が抗議活動を行い、警察はおよそ370人を違法な集会に参加した疑いなどで逮捕し、このうち「香港独立」と書かれた旗を所持していた男性など10人に香港国家安全維持法を適用したと発表しました。
これについて、市民の間では、法律の施行後、警察の取締りが厳しさを増していることへの不安が広がっています。
30代の女性は「施行後、すぐに逮捕者が出ました。今後、警察はさらに取締りを強めるかもしれません」と話していました。
また、別の男性は「社会的な話題を議論するのは今後、気をつけます。これまでソーシャルメディアで発言できたこともできなくなるでしょう」と話していました。
香港進出の日本企業は
ジェトロ=日本貿易振興機構によりますと、香港に進出している日本企業は去年の時点で1400社余りで、2013年以降、横ばいの状態が続いています。
1300社余りのアメリカ、700社余りのイギリスを上回り、香港に進出する外国企業の数では日本が最も多くなっています。
このうち、およそ半数に当たる750社は、飲食や小売など香港の中でビジネスを行う企業で、香港の経済規模の拡大に伴って、およそ20年で3倍以上に増えました。
一方、中国本土の経済発展に伴って、北京や上海など中国のほかの主要都市と比べた香港の経済規模は相対的に小さくなっていて、2000年代以降、日本企業の中国ビジネスの中心はほかの都市に移っています。
香港の経済は、アメリカと中国との貿易摩擦の長期化や、大規模な抗議活動、それに新型コロナウイルスの影響で、去年後半以降、低迷が続いています。
「香港国家安全維持法」が施行されたことによる日本企業のビジネスへの影響について、ジェトロの担当者は「直ちに影響はないとみられるが、中長期ではどんな影響があるのか、地元企業に聞き取りを行うなどして調べたい」と話しています。
金融センターの機能に懸念も
 香港で反政府的な動きを取り締まる「香港国家安全維持法」が施行されたことをめぐり、香港の金融センターとしての機能の低下につながるという見方が出ています。
香港で反政府的な動きを取り締まる「香港国家安全維持法」が施行されたことをめぐり、香港の金融センターとしての機能の低下につながるという見方が出ています。
香港は、資本の移動の規制が厳しい中国本土とは異なる自由な投資環境が確保され、日本や欧米の大手金融機関が拠点を置き、アジアの金融サービスの中心地となってきました。
日系企業も多く進出していて、中国本土の企業を除くと世界で最も多いおよそ1400社が進出しています。
しかし、香港国家安全維持法の施行で、中国政府の政治的な関与が強まることで、独立した司法を前提とした自由なビジネス環境に影響が出ることも懸念されています。
さらに、アメリカ政府は香港に認めている貿易や金融取引などの優遇措置を一部の例外を除いて撤廃する方針を示していて、実施されれば大きな打撃となることは避けられません。
イギリスのシンクタンクが発表している世界の各都市の国際金融センターとしてのランキングでは、香港は、ことし3月、去年秋の3位から6位に順位を下げていて、法律の施行によって今後、さらに順位が下がるという見方もあります。
香港の金融市場に詳しいみずほ銀行東アジア資金部の原田雄一朗部長は「短期的な影響はいまのところ想定していないものの長期的には大きな影響が出る可能性は否定できない」と指摘しています。
原田部長は、香港の特徴として、英語が通じることに加え、人民元の為替市場や中国本土の市場へのアクセスが便利なことを挙げ、「東京やシンガポールには代替できない機能が備えられていて、これが一晩でひっくり返ることはない」と話しています。
その一方で「去年からのデモなどで香港の経済は相当落ち込んでいて、今回のような政治的要素が強い施策が実施されると一般的に企業はどこで法に触れるか分からず保守的に動く可能性がある。今後、金融センターとしての地位も今までのようにいかなくなる可能性も高い」と分析しています。
今後については「かなり不透明感が強まっているのは事実なので、中国当局や香港政府が香港国家安全維持法をどう運用していくかが焦点となる」と話しています。
金融機能低下なら中国本土も影響か
外国からの投資を誘致することで高い経済成長を続けてきた中国にとって、香港は、海外の資金を受け入れる重要な窓口となってきました。
しかし、香港国家安全維持法の施行を受けて香港の国際的な金融センターとしての機能や地位が低下すれば中国本土の企業の資金調達にも影響が出かねません。
香港の株式市場には、国有企業をはじめ中国の多くの大手企業が株式を上場していて、このところは、中国の大手IT企業も相次いで上場しています。
去年11月には、中国のネット通販最大手、「アリババ」が上場し、日本円で1兆円を超える資金を調達したほか、先月にもネット通販2位の「京東」が上場して4000億円余りの資金を調達しました。
また、中国本土では人民元への両替に上限が設けられるなど、資本の移動に対する制約が多いことから、海外の投資家が上海や深セン※の市場に投資をする場合にも、香港の市場を経由して投資するケースも多くあります。
中国政府は、金融面の規制緩和を段階的に進めていますが、中国本土の金融市場が香港に代わるほどの機能を備えるのは短期的には難しく、香港の金融機能が低下すれば、中国経済への打撃は避けられないとみられます。
※「セン」は土へんに川
「レノンウォール」撤去の動き
 「香港国家安全維持法」が施行された香港では、市民が中国政府への批判などを書き込んで飲食店の壁などに貼った紙を、取締りの対象になることを恐れて撤去する動きが広がっています。
「香港国家安全維持法」が施行された香港では、市民が中国政府への批判などを書き込んで飲食店の壁などに貼った紙を、取締りの対象になることを恐れて撤去する動きが広がっています。
香港では去年夏以降、市民が中国政府と香港政府への批判や、民主化への願いをメモ用紙などに書き込んで壁に貼り、抗議の意思を示そうという活動が広がり、音楽を通じて平和や自由を訴えたジョン・レノンにちなんで「レノンウォール」と呼ばれてきました。
このうち中心部の飲食店では「香港を取り戻せ」とか「香港人頑張れ」などと、常連客などが手書きした紙が店の入り口や壁一面に貼られていましたが、法律が施行された直後の先月30日夜に、すべて撤去したということです。
飲食店の店主は「詳しい法律の内容は分からなかったが、安全のため剥がすことにした」と話していました。
別の飲食店の関係者によりますと、警察から法律に違反する疑いがあり、捜索すると言われた店もあるということで「言論の自由を脅かすものだ」という反発も出ています。