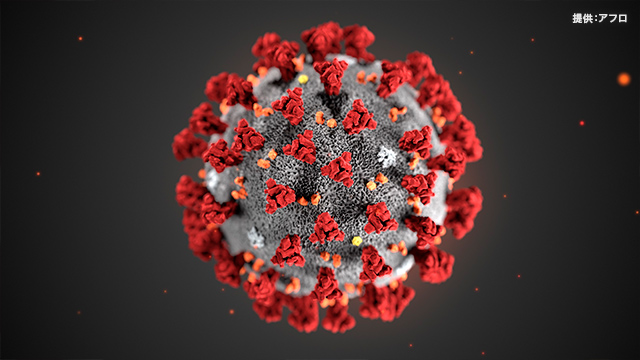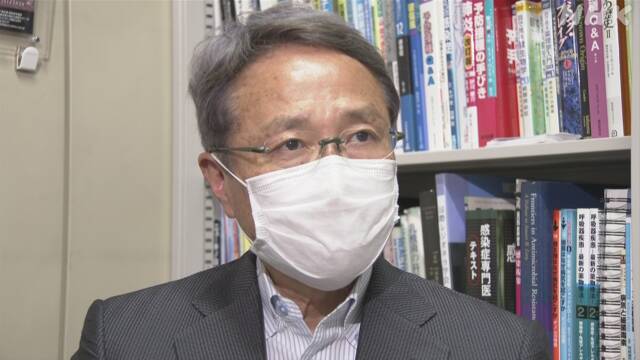宮城県の多賀城駐屯地で1日まで行われた訓練には、「即応予備自衛官」を志願する4人が参加しました。
宮城県の多賀城駐屯地で1日まで行われた訓練には、「即応予備自衛官」を志願する4人が参加しました。
 ふだん会社などに勤務しながら、有事や災害の際に招集される予備の自衛官には、陸上自衛隊の第一線部隊で任務にあたる「即応予備自衛官」と、後方支援にあたる「予備自衛官」があります。
ふだん会社などに勤務しながら、有事や災害の際に招集される予備の自衛官には、陸上自衛隊の第一線部隊で任務にあたる「即応予備自衛官」と、後方支援にあたる「予備自衛官」があります。
このうち、「即応予備自衛官」の採用は元自衛官に限られていましたが、防衛省は去年、人材を確保するため、自衛官経験のない人でも、予備自衛官を経て即応予備自衛官として採用できるよう見直しました。
4人は、ふだん製造業や林業の現場などで働いていて、これまでに、小銃を使った射撃など、即応予備自衛官になるのに必要な36日間の訓練を修了しました。
今後、9月に辞令を交付され、即応予備自衛官に正式に採用されると、年間30日間の訓練への参加が求められ、有事や災害で招集された場合、現役の自衛官とともに第一線で任務にあたることになります。
厳しい採用環境下で任務は拡大
 人手不足は、自衛隊全体にも広がっています。
人手不足は、自衛隊全体にも広がっています。
自衛官のうち、現場の中核を担う任期制の自衛官となる「自衛官候補生」の採用は、6年連続で、計画を下回っています。
厳しい採用の環境を踏まえ、防衛省は、「自衛官候補生」などの採用年齢の上限を、おととし、26歳から32歳に引き上げました。
しかし、採用対象となる18歳から32歳の人口は、今後急速に減少し、平成30年度と比べると20年後には318万人、およそ17%の減少、40年後には640万人、34%の減少と推計されています。
防衛省は、こうした人口減少に高学歴化なども加わり、自衛官の採用環境は今後さらに厳しさを増すとしています。
 その一方で、自衛隊の任務は増加しています。
その一方で、自衛隊の任務は増加しています。
去年から再び活発化している北朝鮮による弾道ミサイルの発射への対応や、中国海軍の活発な海洋進出の動きを背景に、イージス艦などが継続的な警戒監視に当たっています。
さらに、ことしは、日本に関係する船の安全確保に向けた情報収集のためとして、海上自衛隊の護衛艦を中東地域に派遣するなど、新たな任務も増えています。
また、領空侵犯のおそれのある国籍不明機に対する自衛隊機のスクランブル=緊急発進が、昨年度、中国機への対応を中心に過去3番目に多くなるなど、ここ数年、高い水準が続いています。
災害派遣も相次ぎ、昨年度は、合わせて449件、活動した隊員は延べ106万人に上り、2年連続で延べ100万人を超えました。
このうち、去年の台風15号や19号の際は期間中に予定されていた訓練の1割、およそ300件が中止や縮小、延期となりました。
さらに、新型コロナウイルスへの集団感染が確認されたクルーズ船での医療支援に隊員を自主派遣するなど、災害派遣の多様化や長期化、大規模化が、現場に影響を及ぼしています。
大震災災害派遣の自衛官の姿見て志願
 志願した1人、森下佑也さん(39)は、ふだん、岩手県大船渡市にある機械部品の組み立て会社で勤務しています。
志願した1人、森下佑也さん(39)は、ふだん、岩手県大船渡市にある機械部品の組み立て会社で勤務しています。
体を動かすことが好きで、平日は3か所ある会社の工場を忙しく回りながら、休日には、7歳と5歳の子どもたちを連れて公園に遊びに行くのを楽しみにしています。
森下さんが、即応予備自衛官を志願した大きなきっかけは、東日本大震災の災害派遣の活動にあたる自衛官の姿でした。
森下さんは「自分も被災しながらそれでも出動した即応予備自衛官の話を聞いてすごいなと思った。こういうことをしてもらったらうれしいということを、自分が逆にしてあげたい」と動機を語りました。
一方、即応予備自衛官は、災害派遣だけではなく、有事の際に招集されれば第一線で現役の自衛官と同様の任務にあたり当たります。
今回の訓練でも、相手の陣地にほふく前進で近づきながら射撃をする訓練、負傷したときに自分で止血する訓練、銃で撃たれた隊員を待避させ、応急処置をする訓練など、実際の戦闘を想定した動きを繰り返しました。
森下さんは「テレビなどで見るのとは違って、ここまでやるのかというのは確かにあった。もっと練度を上げないと、今はわかっていても、実際その現場になったときに、できるのかという思いもある。会社に戻っても、体力錬成などできることはしなければと思う」と話していました。
背景に深刻な人手不足
 即応予備自衛官の採用を、自衛官経験のない人にも拡大した背景には、深刻な人手不足があります。
即応予備自衛官の採用を、自衛官経験のない人にも拡大した背景には、深刻な人手不足があります。
即応予備自衛官の定員は、およそ8000人ですが、充足率が年々減少し、昨年度は53%と、半分ほどにとどまりました。
ふだんの仕事と年間30日間の参加が義務づけられている訓練との両立が難しいことが背景にあると指摘されていて、人材の確保は容易ではありません。
こうした中、幅広く人材を確保しようと、企業への働きかけも強めています。
ことし2月、東京都内で開かれた電気工事業者の団体の講演会では講師として招かれた自衛官が、テーマの安全管理とは別に、即応予備自衛官の制度を紹介しました。
この中で、災害派遣での実績を示しながら、予備自衛官が持つ民間で培った専門知識や技能が活動に役立っていると強調していました。
講演を行った高橋潤1等陸尉は「予備自衛官の制度は企業の理解がないと成り立たないので、そこを重視して取り組んでいる」と話していました。
専門家「任務を取捨選択する時期にきている」
安全保障政策に詳しい拓殖大学の佐藤丙午教授は、今後の安全保障戦略を考える際、任務と人材のバランスを考えて議論していく必要があると指摘しています。
この中で、佐藤教授は「社会の変動が激しく、安全保障環境の変動も急速に進むので、その中で変化にどう対応していくか、自衛隊は経験したことのない変化の中にある」としています。
そして、「自衛隊が任務を増やしていけばいくほど予算も人員も消耗してしまう。自衛隊の任務について、取捨選択をしなければいけない時期にきているのは確かだと思う」としています。
そのうえで、今後の自衛隊の任務について「国民がどれだけ自衛隊に求めるかということにも左右されると思うし、国会を含めた広い国民的な議論が必要な時期がきている」と指摘しています。
また、イージス・アショアの配備断念によって、安全保障戦略の見直しをめぐる議論が起きていることを踏まえ「新しい安全保障戦略ができるのであれば、その戦略の中で自衛隊の人的資源の最適配分を考えてほしい」と話しています。