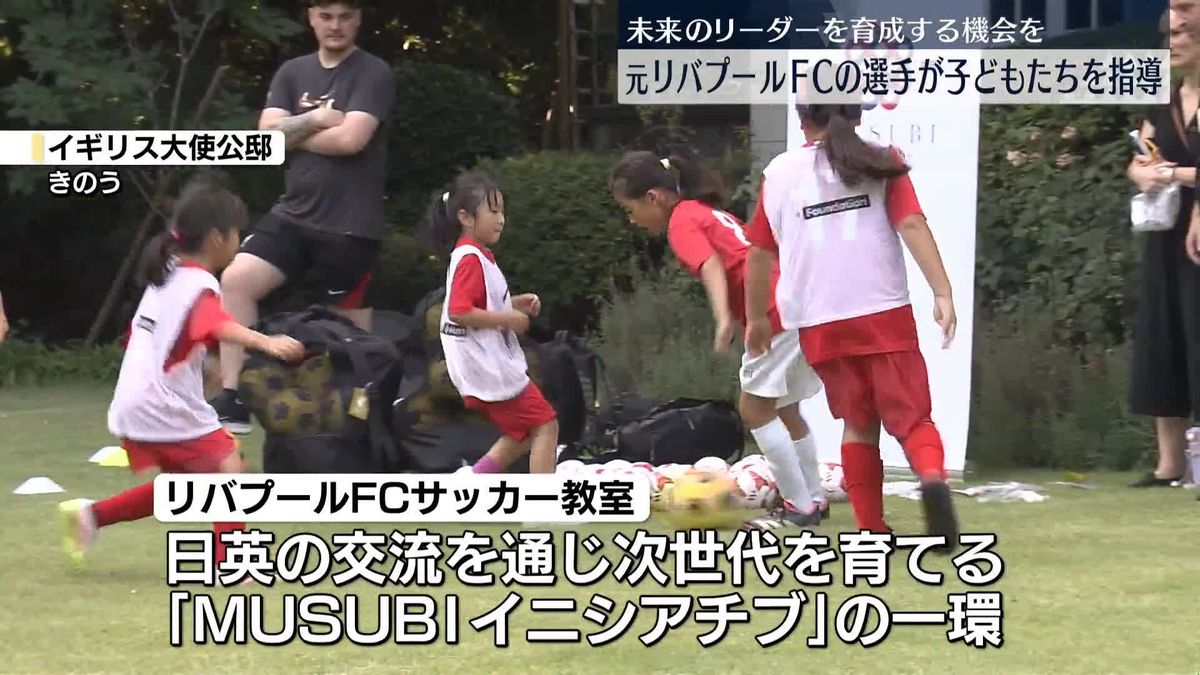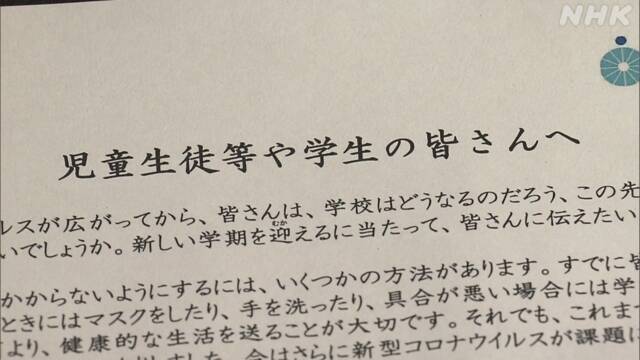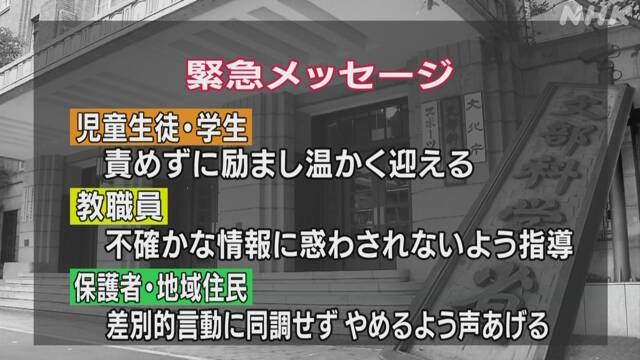JR東日本や、トヨタの自動運転を担う会社などが協力し、新型コロナウイルスを受けた「新しい日常」に対応した働き方や次世代の交通などでサービスの開発に乗り出します。DX=デジタルトランスフォーメーションは、最新のデジタル技術やデータを駆使して新しい製品やサービスを生み出し快適で便利な暮らしを目指す取り組みで、デジタル革新とも言われています。
関係者によりますと、この分野で「JR東日本」と「あいおいニッセイ同和損保」、トヨタ自動車の自動運転などの開発を担う「TRIーAD」、「日本ユニシス」、「出光興産」、「博報堂」の6社が新たなプロジェクトを始めることになりました。
アメリカ・シリコンバレーの投資会社「スクラムベンチャーズ」が呼びかけたプロジェクトで、自動運転や空飛ぶ車などを使った新しい交通システム、オンライン診療などのヘルスケア、それにテレワークなど新型コロナウイルスを受けた「新しい日常」に関連する分野などで、新たなサービスの開発を目指します。
今後、国内外のスタートアップ企業に広く参加を呼びかけるほか、東京・渋谷区や三重県も加わり、渋滞や過疎といった地域の課題を解決する具体策を検討する計画です。
今回のプロジェクトは、大手企業が業種を超えてスタートアップ企業や自治体とも連携する異例の取り組みで、日本のデジタル変革を先導する成果を生み出せるかが焦点となります。
DX=デジタルトランスフォーメーションとは
デジタルトランスフォーメーションは、人手のかかっていたサービスを自動化したり作業を効率化したりするだけでなく、デジタル技術を駆使して地域社会や暮らし全体がより便利になるよう変えていく取り組みです。デジタルの頭文字の「D」、そして変化や変換という意味をもつトランスフォーメーションは英語圏でトランスの部分を「X」と表記することがあるため、「DX」と略されるようになりました。例えば、スマートフォンの普及に伴って生まれた音楽や番組を配信するサービスや、商品を閲覧した過去のデータをもとに関連する別の商品を「おすすめ」として表示するネット通販の機能などが代表例とされています。
日本でも、政府や経済界がDXを促しています。経済産業省は、DXについて「企業が製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織、企業風土を変革し、競争上の優位を確立すること」などと定め、組織や人材育成なども含めた抜本的な見直しが重要だと指摘しています。また経団連もDXに関する報告書をまとめ、グーグルやアマゾンなどを中心にDXが進むアメリカや、国が主導する中国に対抗するため、日本は業界や分野を超えて大企業やスタートアップ企業、自治体などが連携することが必要だと提言しています。
新型コロナウイルスをきっかけにオンライン会議や「脱はんこ」など、これまでの慣習を見直し、「新しい日常」にデジタル技術で対応しようという動きも増えています。こうした流れをてこにして日本発のDXが広がっていくのか、2020年は節目になる可能性があります。