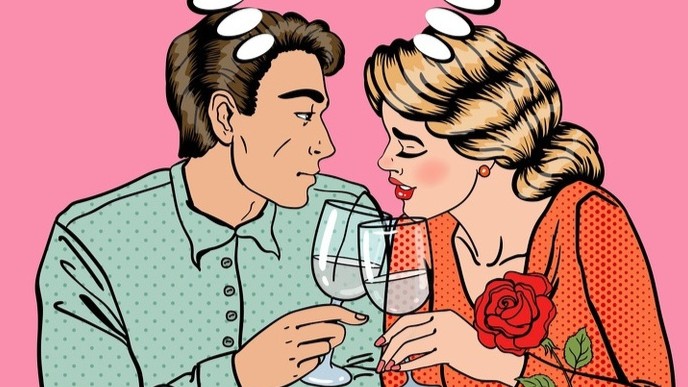相続税などの基準となる土地の価格、「路線価」が3日公表され、全国の調査地点の平均は2年連続で上昇し、上げ幅も大きくなるなど、新型コロナの影響からの回復傾向が鮮明となりました。
商業地や観光地などで大きく上昇した一方、オフィス需要の低迷が続く東京都心では横ばいやわずかな上昇にとどまり、回復傾向に差が出る結果にもなっています。
一方、上昇率2年連続全国最高となった北海道では、札幌市中心部で相次ぐ再開発や、先端半導体の国産化を目指す「Rapidus」の工場建設が決まっている千歳市で、今後、住宅需要が急速に高まると見られています。
令和5年分の「路線価」について、各都道府県データとともに詳しくお伝えします。