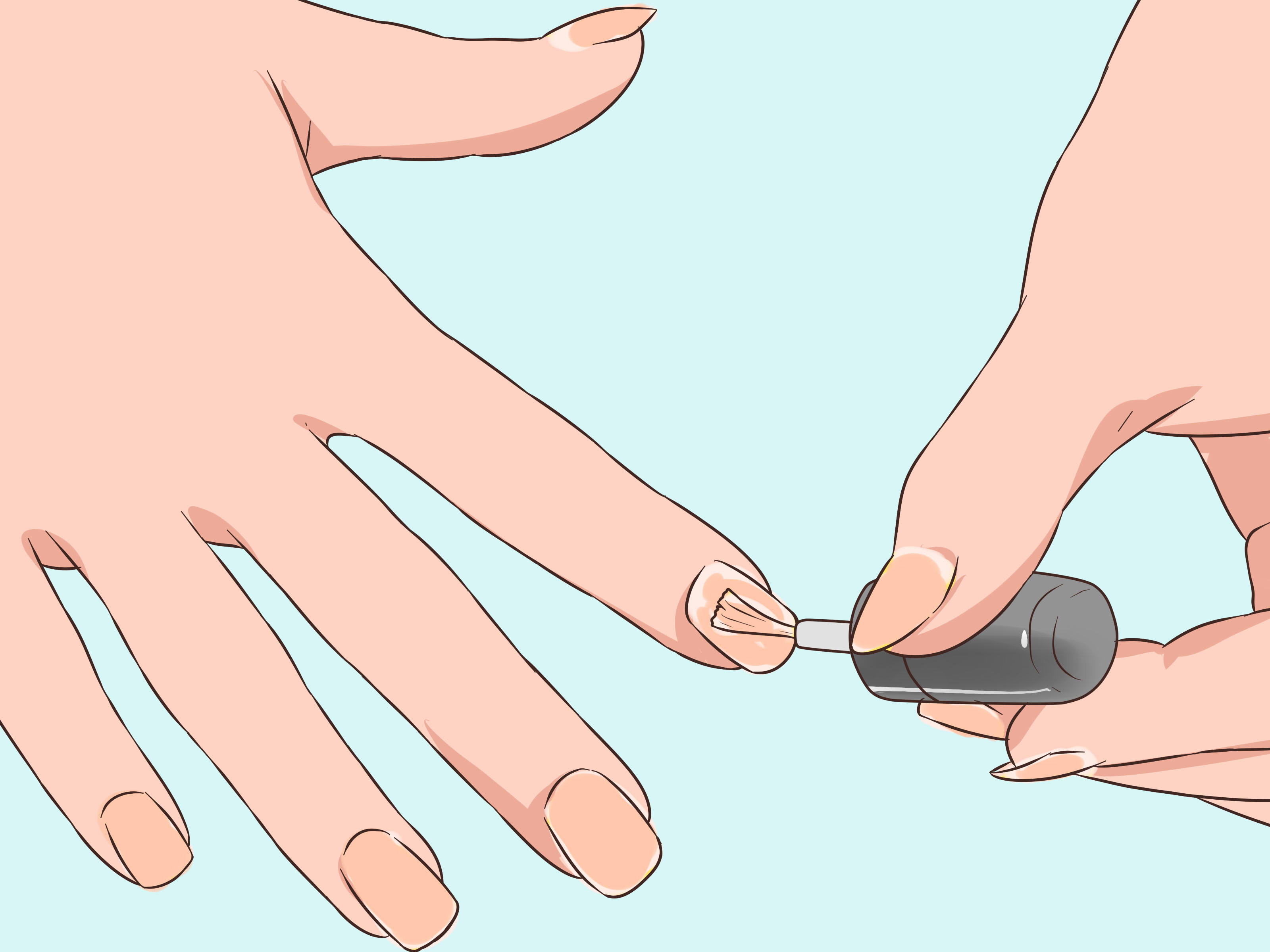昭和24年、東京の三鷹駅構内で無人の電車が暴走して脱線し、駅にいた6人が死亡した三鷹事件では、旧国鉄の組合員など10人が電車転覆致死の罪で起訴され、裁判では運転士だった竹内景助元死刑囚の単独の犯行と認定されて死刑が確定し、ほかの9人は無罪でした。
昭和24年、東京の三鷹駅構内で無人の電車が暴走して脱線し、駅にいた6人が死亡した三鷹事件では、旧国鉄の組合員など10人が電車転覆致死の罪で起訴され、裁判では運転士だった竹内景助元死刑囚の単独の犯行と認定されて死刑が確定し、ほかの9人は無罪でした。
竹内元死刑囚はその後、無実を訴えて再審を求めましたが、昭和42年に45歳で病死したため手続きが終了し、平成23年に長男が改めて東京高裁に再審を求めました。
これについて東京高裁の後藤眞理子裁判長は、31日の決定で、「弁護側が提出した新証拠は、元死刑囚が単独で犯行に及んだと自白した供述の中でも電車の発車方法に関する根幹部分の信用性に重大な疑いを生じさせる証拠とは言えない」と指摘し、再審を認めませんでした。
三鷹事件は、終戦後、GHQ=連合国軍総司令部の統治下で国鉄がおよそ9万5000人の人員整理を進め、労使間の緊張が高まる中、相次いだ「国鉄三大事件」と呼ばれる事件の1つで、元死刑囚の逮捕から来月1日でちょうど70年となります。
弁護団「理解できない」
東京高裁前で弁護団の1人が「三鷹事件不当決定」と書かれた紙を掲げると、集まった支援者たちは静まり返りました。
弁護団の高見澤昭治弁護士は、「新証拠も出したので、弁護団としては再審決定になると思っていたので、どういう理由で認めなかったのか、理解できない。竹内さんの長男とは、『これからも頑張りましょう』と確認した」と話していました。
三鷹事件と裁判の経過
事件発生
三鷹事件は昭和24年(1949年)7月15日、東京の三鷹駅で起きました。午後9時半前、駅構内の車庫に止まっていた7両編成の無人の電車が突然動きだしてホームを通過し、車止めを乗り越えて駅の外まで暴走、電車の下敷きになるなどして駅にいた6人が死亡し、20人が重軽傷を負いました。
事件当時の時代背景
当時、日本はGHQ=連合国軍総司令部の統治下にありました。
日本の経済を安定させるためにGHQの下で進められた経済政策「ドッジ・ライン」を受けて、国鉄がおよそ9万5000人の人員整理を発表するなど、労使間の緊張が高まり、労働組合や共産党が活発に活動していた時期でした。三鷹事件が起きる前日、三鷹電車区では27人に解雇が通告されました。
逮捕・起訴供述の変遷
捜査当局は、解雇に反対する共産党による組織的な犯行として捜査を進め、国鉄労組の共産党員らを次々と逮捕しました。
このうち10人が起訴され、唯一、共産党員ではなかったのが、竹内景助元死刑囚でした。
竹内元死刑囚は、当初、事件の関わりを否認していましたが、その後、単独犯行であると供述を変遷させていきました。
供述を変遷させた理由について竹内元死刑囚は、後に、検察から厳しい追及を受け迎合したことや、共産党員ではなかったことから、単独犯と主張すれば、ほかの被告も死刑から逃れられるなどと、弁護士に説得されたとしています。
裁判の結果
昭和25年(1950年)、1審の東京地方裁判所は、判決で、検察が立証しようとした共産党員による組織的な犯行というストーリーについて、「全く実体のない空中楼閣」と厳しく非難し、ほかの9人の共産党員を全員無罪としました。
一方で、自白に基づいて竹内元死刑囚の単独犯行と認定し、無期懲役を言い渡しました。
翌年(1951年)、2審の東京高等裁判所は、1審を取り消し、死刑を言い渡しました。
竹内元死刑囚は死刑に驚き、このあとは一貫して無実を主張するようになり、最高裁に上告しました。
しかし昭和30年(1955年)、最高裁判所の判決で、裁判官15人のうち8人が上告を退けることに賛成し、8対7で死刑が確定しました。
僅かな差で死刑とされたことに対して、反対の声が上がり、国会議員や著名な作家らも再審=裁判のやり直しの実現などを求める署名運動に加わりました。
竹内元死刑囚の再審請求
その翌年(1956年)、竹内元死刑囚は東京高裁に対し、再審を求める申し立てを行い、無実を訴えました。
再審請求の審理が進み、東京高裁は「本人に話を聞いてから結論を出したい」と弁護団に伝えましたが、竹内元死刑囚の病気が進み実現せず、昭和42年(1967年)1月、脳腫瘍のため45歳で亡くなりました。
このため再審の手続きは打ち切られ、40年余りたった平成23年(2011年)、竹内元死刑囚の長男が再審を申し立てました。
戦後の闇
三鷹事件が起きた昭和24年(1949年)の夏には、当時の国鉄総裁が綾瀬駅近くの線路で遺体で見つかった「下山事件」と、福島県で列車が脱線・転覆し、乗務員3人が死亡した「松川事件」が相次いで起こり、いまだに真相が明らかになっていないとして、「国鉄三大事件」とか「国鉄三大ミステリー」などと呼ばれています。
三鷹事件は、発生直後から共産党や労働組合関係者が関与したと疑われ、事件の翌日に当時の吉田茂総理大臣も「事件は共産主義者の扇動によるものだ」と断定しました。
敗戦直後、日本の民主化が進められ、盛り上がりを見せた労働運動を逆に取り締まるようになった「逆コース」と呼ばれる動きの中で起きた事件でした。
作家の松本清張は、ノンフィクションの代表作「日本の黒い霧」で、下山事件と松川事件を取り上げています。