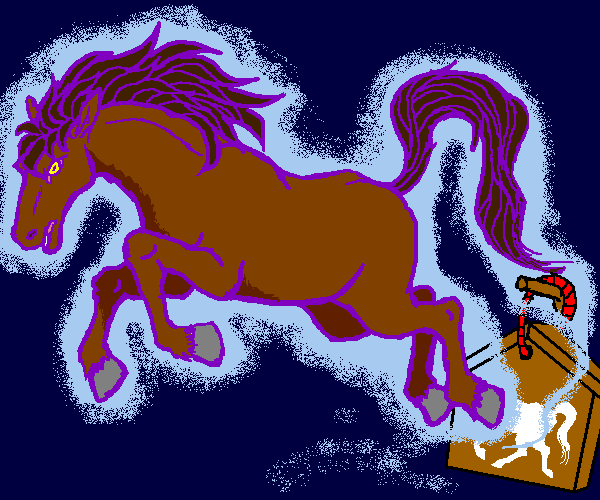国土交通省によりますと、ボルトが折れたりナットが緩んだりしてタイヤが外れる事故は、昨年度は統計を取り始めて最も多い112件発生し、1人が重傷、4人がけがをしています。
実験では時速60キロで走行するトラックを急停止させ、そこから30メートル離れたところにいる人形とベビーカーにタイヤがぶつかったときの衝撃を調べました。
人形とベビーカーは重さがおよそ90キロあるタイヤがぶつかると、およそ4メートルほど移動し体が折れるように曲がって倒れました。
国土交通省は昨年度発生した事故の67%が10月から2月にかけてと冬用のタイヤに交換する時期に多いことから、この実験とタイヤの取り付け方法や注意点を動画にするなどして事故防止の呼びかけを強化することにしています。
国土交通省自動車局整備課の高瀬竜児課長補佐は、「冬は天気予報を見て慌ててタイヤを交換するため作業が不十分になり事故につながるとみられていて、動画で危険性を伝え、事故を減らしていきたい」と話していました。
過去の脱輪事故 傾向と分析
車輪のボルトが折れたりホイールと車軸をつなぐナットがとれたりしてタイヤが外れる事故では過去には死亡事故が起きています。
国土交通省によりますと、平成16年に北海道で走行中のダンプカーから外れたタイヤの直撃を受けた当時3歳の男の子が死亡したほか、平成20年には静岡県でトラックから外れたタイヤが観光バスを直撃してバスの運転手が死亡し乗客7人がけがをしました。
タイヤが外れる事故は、この10年増加傾向で平成23年度は全国で11件でしたが、昨年度は112件で統計を取り始めた平成11年度以降で、最も多くなりました。
このうち昨年度の事故を国土交通省が分析したところ、事故の67%が10月から2月にかけて発生し事故の60%がタイヤを交換して1か月以内に発生していました。また外れたタイヤの96%が負荷のかかりやすい左の後輪、歩道側でした。
国土交通省は、11月から来年2月末までを「車輪脱落事故防止キャンペーン」として、タイヤを交換する際にはナットの締めつけを専用の工具で規定の力で行うことや、50キロから100キロ走行したら再度ナットの締めつけを行うなど注意点を具体的に示すチラシやポスター、ホームページなどで事故防止の呼びかけを強化することにしています。
事故を契機に対策強化した会社
タイヤが外れる事故が起きた会社では、事故防止の対策を強化しています。
埼玉県にある運送会社「清水運輸」では、おととし12月、積み荷を受け取りに行く大型トラックが県内の一般道を走行中に左側の後ろのタイヤが外れる事故が起きました。
外れたタイヤは重さ100キロ、道路脇の茂みで止まってけが人はいませんでしたが、清水英次社長は、「もし人がいたら最悪の場合、命を落とすことになるのでぞっとした」と話します。
原因は事故の前日に冬用のタイヤに交換した際、ナットの締めかたが緩かったことでした。
会社で今週行われたミーティングでは、従業員によって差が出ないよう事故を教訓に作成した手順書に基づいて冬用のタイヤに交換することを確認しました。
ナットを規定の力で締めるとともに、ナットとボルトに油性ペンで線をひいて、走ることによって生じる緩みを視覚で確認できるようにしています。
清水社長は、「まさか、自分の会社でタイヤが外れるとは思ってもみなかった。一歩間違えば大事故につながるので、これから本格化する冬用タイヤの履き替えは緊張感を持って行いたい」と話していました。