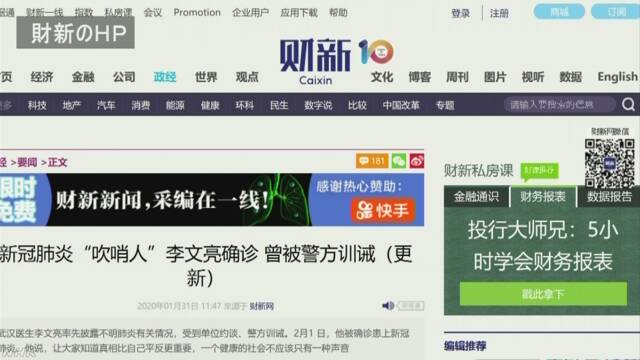松江市の
遺跡から
出土した
弥生時代中期のすずりとみられる
板状の
石に
墨書きのようなものが
残され、
2つの
文字と
判断できることが
分かりました。
調査した
研究者によりますと、
今から2000
年ほど
前のものと
考えられ、
文字だとすれば
国内最古の
例とみられます。
この板状の
石は
松江市の
田和山遺跡から
以前、
出土していたもので、
國學院大学の
柳田康雄客員教授らが
改めて調査を
行いました。
その結果、石は今から2000年ほど前の弥生時代中期にすずりとして使われていたと考えられ、裏側に墨書きのようなものが残されていることが分かりました。
複数の研究者が確認したところ、2つの文字が縦に並んでいると判断でき、上の字は子どもの「子」など、下の字ははっきりしないものの「戊」などの可能性が考えられるとしています。
日本列島では古墳時代の5世紀ごろには確実に文字が使われ、それより前の弥生時代後期にも文字とみられる土器の線刻などが見つかっていますが、今回のものが文字だとすれば国内最古の例とみられます。
柳田さんは「2文字あるので記号とは考えられない。弥生時代中期には西日本の拠点ではすずりとともに文字が普及し、交流などに使われていたと考えられる」と話しています。