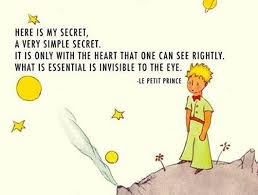現地時間の8月25日に開幕したシンポジウムには、日銀の黒田総裁やFRBのパウエル議長など主要国の中央銀行トップや著名な経済学者、エコノミストなどが集まりました。
最も注目を集めたのは、日本時間の8月26日午後11時に始まったパウエル議長の講演。
市場に冷や水を浴びせたのは、講演が始まって1分半ほどたってから発した次のことば。 「インフレを抑え込むには家計や企業に何らかの痛みをもたらすことになるがそれは避けられないコストだ。ただ、物価の安定を取り戻すことに失敗すればもっと大きな痛みを伴うことになる」 「痛み」という犠牲があったとしてもインフレの抑え込みを優先する。 この強いメッセージに株式市場は大きく反応。 金融の引き締めが長期間継続し、景気が冷え込むことへの警戒感が広がり、ダウ平均株価は1000ドル以上の急落となりました。 これが市場にとってどれほどの“サプライズ”だったのか。 日本のエコノミストやアナリストなど市場関係者10人に聞いたところ、インフレ抑制を優先したことについては、意外なことに10人全員が「想定どおりでサプライズはなかった」との回答でした。 ただ、総じていえば2点、“意外感”をもって受けとめられたところがありました。
事前に公表されていた、シンポジウムのアジェンダでは、パウエル議長の講演時間は30分間とされていました。 しかし予想外の8分50秒で終了。 ジャクソンホール会議でのFRB議長のスピーチ原稿を紙にすると、2012年以降、多いときは19枚(表紙や図表、参照欄を除く)、少ないときでも9枚となっていますが、今回はわずか5枚でした。 私もそうでしたが、「これで終わり?」と驚いた方も多いと思います。 パウエル議長は講演の冒頭、「私の発言はより短く、焦点を絞って直接的なメッセージになる」と発言していました。 市場関係者からは、「あえて講演の時間を短くしてシンプルなメッセージに凝縮することで市場が臆測を生むような状況をつくらせないようにしたのではないか」という指摘もあがっていました。
パウエル議長が例示したのは1970年代の金融政策。 第4次中東戦争に端を発したオイルショックで原油価格が高騰し、アメリカではインフレが急激に進んでいました。 当時、FRBを率いていたアーサー・バーンズ議長も手をこまねいていたわけではなく、1972年2月に3.5%だった政策金利を、1974年の5月にかけて、13%まで引き上げました。
この結果、1974年12月に物価上昇率が12.3%まで急上昇する事態となり、その後、アメリカはインフレと景気後退が同時に起きるスタグフレーションに苦しむことになります。 これについてパウエル議長は、次のように指摘しました。 「1970年代、インフレ率の上昇に伴ってインフレ率が高いという期待が家計や企業での経済的な意思決定に定着してしまった」 将来インフレが高止まりするという見方が定着すると、さらに物価が上がるという悪循環に陥る。 パウエル議長はこうした歴史の教訓を引き合いに出し、1980年代初頭のインフレ抑制は、それ以前の15年間、インフレを抑える試みが失敗したあとに成し遂げられたものだと指摘しました。 そして当時、大胆な引き締め策を断行してインフレの抑え込みに成功したポール・ボルカーFRB議長のことばを引用します。
しかしなぜ当時、アメリカがインフレが収まらないなかで引き締めから緩和に突然政策を転換したのか疑問が残ります。 三菱UFJモルガン・スタンレー証券の藤戸則弘チーフ投資ストラテジストは、この理由を探るうえでは、バーンズ議長のほかに、もうひとりの登場人物の存在が重要だと説明します。 それが、当時のリチャード・ニクソン大統領(在任1969年1月~1974年8月)です。 民主党本部の盗聴未遂事件への関与が取り沙汰された「ウォーターゲート事件」で辞任に追い込まれた、あのニクソン大統領です。 ニクソン大統領は、景気が後退すると選挙に不利だという意識が強く、バーンズ議長に対して金融緩和を強く求めたといいます。 この結果、インフレが進む中での突然の利下げという事態になったということです。 藤戸氏は、パウエル議長の胸の内には、この一連のバーンズ議長の対応のまずさが意識されていたのではないかと指摘します。
「パウエル議長は、去年のジャクソンホール会議で、『物価上昇の動きは一時的なのものにとどまる可能性が高い』と楽観的な発言をしており、金融政策での対応の遅れが批判されていた。このままインフレを退治できなければ、パウエル議長も歴史の審判を受けることになってしまう。だからこそパウエル議長はジャクソンホールの短い講演の中で、『私はバーンズじゃない!』ということを言いたかったのではないか」
それでは1980年代のインフレ抑え込みの「痛み」とは何だったのか。 ボルカー議長のインフレとの戦いで1979年に6%程度だった失業率は10%を超え、アメリカは2回の景気後退局面に陥るという多大な犠牲を払いました。 「やり遂げるまでやり続けなければならない」と言い切ったパウエル議長のもとでアメリカはどのような試練に直面し、これを乗り切ることができるのか。 そして円安ドル高の流れにどう影響を及ぼし、世界経済をどのような形で巻き込んでいくのか、私たちも歴史の教訓をふまえ、日本の針路を見つめていかねばならないと思います。
また、主な産油国でつくるOPECプラスの協議も行われ、原油の生産量を減らす「減産」に踏み切るかどうかが焦点です。 また、ヨーロッパ中央銀行が理事会を開き、政策金利を発表します。大幅な利上げに踏み切るという観測も出ており、発表後のラガルド総裁の会見に市場は注目しています。 また、8日のFRB・パウエル議長の発言にも注目です。

なぜ「8分50秒」だったのか
FRBの失敗の歴史を教訓に


なぜ失敗したのか
パウエル発言の「痛み」が意味するものとは