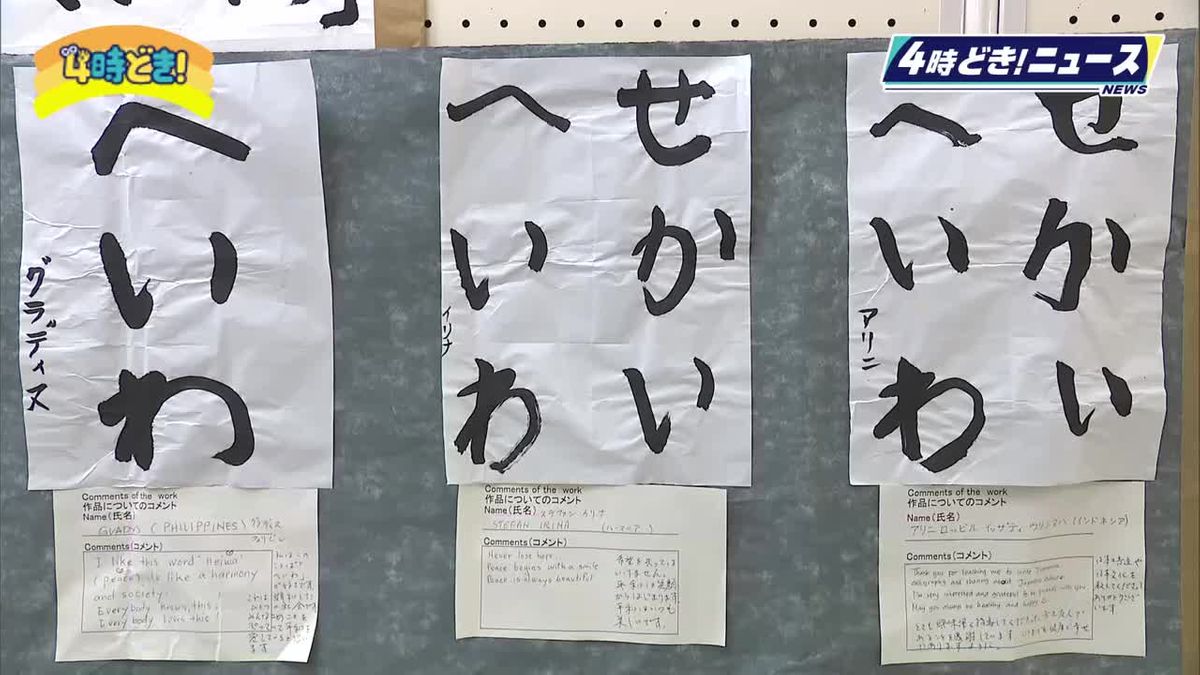旧優生保護法のもとで
不妊手術を
受けた
人たちを
救済するため、おわびや、
一時金として320
万円を
支払うこと
などを
盛り込んだ
法律が、24
日、
参議院本会議で
全会一致で
可決され、
成立しました。
平成8年まで
施行された
旧優生保護法のもとで
不妊手術を
受けた
人たちを
救済するための
法案は、24
日午前の
参議院本会議で
採決が
行われ、
全会一致で
可決され、
成立しました。
成立した法律では、旧優生保護法を制定した国会や政府を意味する「我々」が「真摯(しんし)に反省し、心から深くおわびする」としています。
そのうえで、本人が同意したケースも含め、精神障害や遺伝性の疾患などを理由に不妊手術を受けた人を対象に、医師や弁護士などで構成する審査会で手術を受けたことが認められれば、一時金として、一律320万円を支給するとしています。
一時金の請求は本人が行う必要があり、その期限は、法律の施行から5年以内と定められています。
厚生労働省では、一時金の対象となるのは、およそ2万5000人と見込んでいます。また、国が同じ事態を繰り返さないよう旧優生保護法を制定したいきさつなども調査するとしています。
政府は、24日にも、法律を施行し、一時金の申請の受け付けを始めることにしています。
救済法成立までの経緯
終戦直後の昭和23年から平成8年まで施行された旧優生保護法のもとでは、遺伝性の疾患や精神障害などを理由に不妊手術が行われてきました。
背景には、親の障害や疾患は子どもに遺伝するという考え方があり、法律にも「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」と明記されていました。
これに対し、基本的人権を踏みにじられたとして、去年1月、全国で初めて、不妊手術を受けた宮城県の60代の女性が国に損害賠償を求める裁判を起こしました。
現在、札幌や仙台、大阪、神戸など全国7つの地方裁判所で、合わせて20人が同様の裁判を起こしています。
こうした動きを受けて、去年3月、救済策を検討するために、自民・公明両党の作業チームと、野党も参加した超党派の議員連盟がそれぞれ発足し、議員立法の形式で救済法案を提出することを目指して、検討を進めてきました。
その結果、手術を受けた人たちに一時金320万円を支払うことなどで与野党が合意しました。
これを受けて、衆議院厚生労働委員長が提案する形で法案が国会に提出され、今月11日に衆議院を通過していました。
救済法の内容は
この法律は、昭和23年から平成8年まで施行された旧優生保護法のもとで不妊手術などを受けた人たちを、一時金の支給によって救済することが目的です。
法律の前文では、旧優生保護法のもとで不妊手術などを受けた人が「心身に多大な苦痛を受けてきた」として、法律を制定した国会や、執行した政府を意味する「我々」が「真摯に反省し、心から深くおわびする」としています。
一時金の支給対象となるのは、本人が同意したケースを含め、精神障害や遺伝性の疾患などを理由に不妊手術を受けた人で、およそ2万5000人が見込まれています。
一時金は一律320万円で、手術を受けた本人が、法律の施行から5年以内に、住んでいる都道府県に対して請求する必要がありますが、国や都道府県からは通知されません。
精神障害や遺伝性の疾患を理由に手術を受けたことが記録などから明らかな場合のほか、医師や弁護士などで作る国の審査会が医師の診断資料や治療の記録などをもとに審査した結果、手術を受けたと認められれば一時金が支払われます。
また、強制的に不妊手術が行われる事態が二度と繰り返されないよう、国が旧優生保護法を制定したいきさつなどを調査するとしています。
厚労相「反省しおわび」
根本厚生労働大臣は、国会内で記者団に対し「多くの方が、特定の疾病や障害があることを理由に生殖を不能にする手術を強いられ、心身に多大な苦痛を受けてこられた。旧優生保護法は、旧厚生省が所管し執行していたことから、真摯に反省し、心からおわび申し上げる」と述べました。
そのうえで「対象の方の多くが障害者であることを踏まえ、地方自治体などの協力を得て、一時金の支給手続きについて、十分かつ速やかに周知を行っていく。厚生労働大臣として、着実な一時金の支給に向け全力で取り組みたい」と述べました。
公明 山口代表「一日も早い救済を」
公明党の山口代表は、党の参議院議員総会で「幅広い合意を作り出して解決の道筋をつけた。つらい目にあった方々に対する救済を一日も早く遂げていくことが大切だ」と述べました。