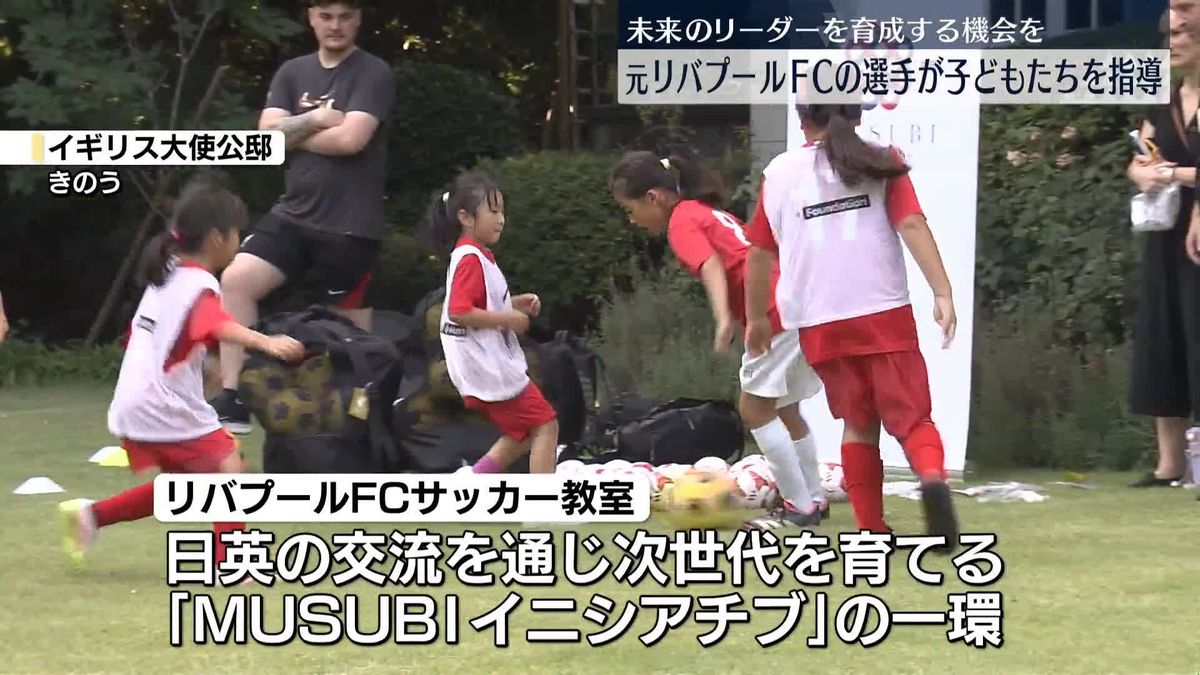具体的にはトヨタはスズキの株式の5%程度を960億円で取得する一方、スズキも480億円を投じてトヨタの株式を取得します。
トヨタとスズキは、おととし2月に業務提携を結び、トヨタのハイブリッド車の技術をスズキに提供することや、スズキの主力市場であるインドで、互いに強みを持つ車を供給し合うことを決めるなど、協力関係を拡大してきました。
こうした中、自動車メーカーの今後を左右する動きとして、自動運転の技術など次世代の車づくりに欠かせないAI=人工知能などを活用した先端技術の開発競争が激しくなっています。
グーグルやアップルなども相次いで参入し、自動車業界は、100年に1度と言われる変革期を迎えています。
このため、両社は株式を持ち合うことで関係を一段と強化し、自動運転など次世代の技術の開発を協力して加速させ、競争力を高めることにしたものとみられます。
“100年に1度”の変革期
自動車業界は、電動化や自動運転技術の発達などを背景に産業構造が大きく変わる節目にあり、100年に1度の変革期とも言われる荒波の中にあります。
世界各国で環境規制が厳しくなり、ハイブリッド車だけでなく電気自動車をはじめ燃料電池車などの開発が加速し、電動化が進むことが見込まれています。さらに、AI=人工知能やセンサーなどを用いた自動運転の技術や、インターネットにつなげてさまざまなサービスを受けられる“つながる車”など、最先端技術の開発競争が激しさを増しています。
また、車を所有せずに使うカーシェアリングなど、新たな使い方への対応も求められています。
こうした変化は、つながることを意味する「コネクテッド」、自動運転の「オートノマス」、「シェアリング」、それに電動化の「エレクトリック」の頭文字をとってCASE(ケース)とも呼ばれていて、この分野にはアメリカのIT企業のグーグルやアップル、配車事業大手のウーバーなどの新たなライバルも参入して競争が激しくなっています。
このため自動車メーカー各社は、次世代の車にかかる巨額の投資を分担し、開発を急ぐために、提携する動きを加速しています。
海外メーカーでも、販売台数で去年まで3年連続で世界首位のドイツのフォルクスワーゲンとアメリカのフォードがことし7月、自動運転と電気自動車の技術を共同で開発していくと発表。ドイツのBMWとメルセデス・ベンツのダイムラーもことし2月、自動運転技術の開発を共同で行うと発表しています。
この大きな変化に対応できるかどうかが大きな分かれ目になろうとしています。
提携の歩み
 トヨタ自動車とスズキが、提携の検討を始めたのは、3年前、平成28年10月でした。
トヨタ自動車とスズキが、提携の検討を始めたのは、3年前、平成28年10月でした。
「(トヨタ自動車・豊田章男社長)同じ志を持った仲間作りがよい車づくりに役立つ取り組みを検討したい」
「(スズキ・鈴木修会長)従来からの伝統的な技術を磨くだけでは危ういと考え、思い切ってトヨタに協力を相談した」
世界の自動車業界は、電気自動車などの次世代のエコカーや、自動運転技術などの開発にIT大手などの異業種も参入。100年に1度と言われる変革期を迎えていることが提携の検討を後押ししました。
2017年の2月には、環境技術や安全技術など幅広い分野で業務提携を結ぶことで合意。両社は、協力関係を深めることになります。
スズキがおよそ50%のシェアを持ち、今後の成長が期待されるインド市場では、2020年ごろに電気自動車を投入することを目指し、トヨタがスズキに技術支援を行うことを決めました。
さらに、インドでの販売を拡大させるため、それぞれが強みを持つ車を相互に供給し合うことや、スズキの小型車をトヨタの工場で生産することでも合意します。
協業の検討は、インド以外にも広がっていきます。ことし3月、トヨタが持つ、ハイブリッド車などの電動化の技術をスズキに供与することや、スズキがインドで生産する小型車を、トヨタのアフリカ市場向けに供給する検討にも入りました。
国内では6月に、自動運転技術を活用した次世代の移動サービスを目指してトヨタとソフトバンクが共同で設立した会社に、スズキが出資することも決めました。国内外で関係が深まっていく中、両社が資本提携に踏み切るのかどうか注目されていました。