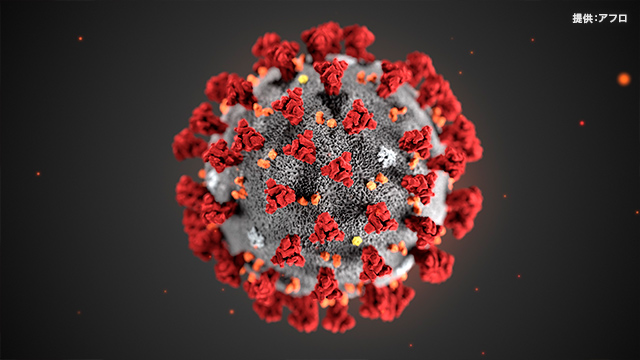東北沖の
巨大地震の
発生から10
年となるのを
前に
地震の
研究者で
作る地震予知連絡会が
会合を
開き、
今月、
福島県沖で
起きたような
比較的震源の
深い場所の
地震活動が、
東北沖では
やや活発な
状況が
続いているといった、
最新の
研究や
観測の
成果が
報告されました。26
日開かれた
地震予知連絡会では、
この10
年の
研究成果や
最新の
観測状況について
報告が
行われました。
この中で、防災科学技術研究所の汐見勝彦総括主任研究員は、巨大地震の余震域での地震活動について、マグニチュード5以上の地震は巨大地震前とほぼ同じ程度まで減っている一方、今月、最大で震度6強の揺れを観測した福島県沖の地震のように、震源が40キロより深い場所で起きる地震活動は、やや活発な状況が続いていると指摘しました。
青森県の東方沖から岩手県沖にかけても、やや活発な状況が続いているということで、注意が必要だとしています。
また、建築研究所の芝崎文一郎上席研究員は、大地震の発生間隔に関するこれまでの研究を説明し、東北大学の中田令子助教の研究成果として、10年前の巨大地震とその前後の大地震を対象としてシミュレーションした結果、マグニチュード7クラスの「宮城県沖地震」の発生間隔が、これまでの30年から40年より短くなる可能性があるという内容を紹介しました。
地震予知連絡会の会長で名古屋大学大学院の山岡耕春教授は「いつ、どこで、どのような地震が起きるかを100%予測することは不可能だが、全く見当がつかないわけでもない。現状でどの程度分かっているのかを理解してもらうための努力を続けていきたい」と話しています。