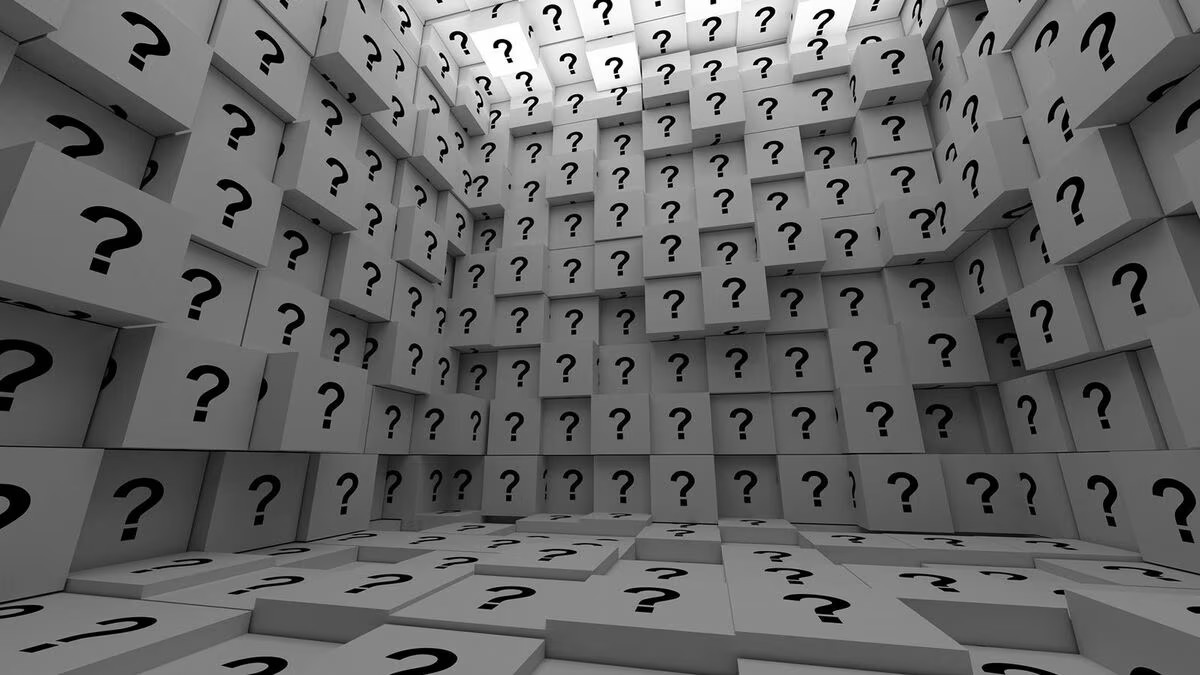「常識を疑ってみる」ということ、実はそれが学問の始まりでもあります。
勉強が「強いて勉める」という受動的な側面を持つものであるならば、学問は「問うで学ぶ」ことであり、極めて能動的な行為です。
如果學習是被動的、是「被強迫學習」的話,那麼學問則是「提出問題並學習」,是一種非常主動的行為。
。
透過自己主動提出疑問,對被視為理所當然的觀點產生懷疑,並嘗試稍微改變視角,尋找其他不同的看法。
。
学ぶこととは、単純に知識を増やすということではなく、ましてやテストで覚えたことを吐き出すことでもなく、それを自分のものとして再編成していくことであり、さらに言えば自分の物差しが変わり、自分自身が変わっていくことなのです。
學習不僅僅是增加知識,也不是為了考試而反覆練習所學的內容。學習是將這些知識重新構築成為自己的一部分,進而改變自己的標準,甚至改變自己本身。
。
而且,也許你能夠發現意想不到的重大發現或獨創性的點子。
。
「人を疑う」と言えば、普通はその人を信用しないというのと同義なわけです。
私も、人を疑って生きるよりも、できるだけ人を信じて生きていたいと思っています。
我自己也希望,與其懷疑他人,不如盡可能相信更多的人來生活。
。
然而,有時我們也需要對社會上被視為理所當然的事情抱持「懷疑」。
。
不要因為那是「理所當然」的事就閉上雙眼,也不要輕易隨波逐流,不妨換個角度看看,或許能發現一些有趣的事物。
。
這並不是導向悲觀的生活方式或什麼都不相信的生活方式,反而是為了編織出更具創造性和豐富性的世界而進行的積極活動。