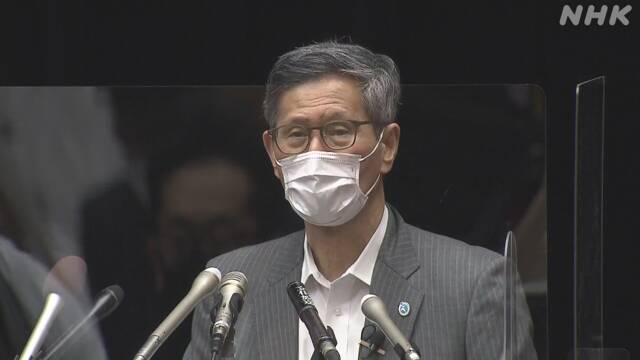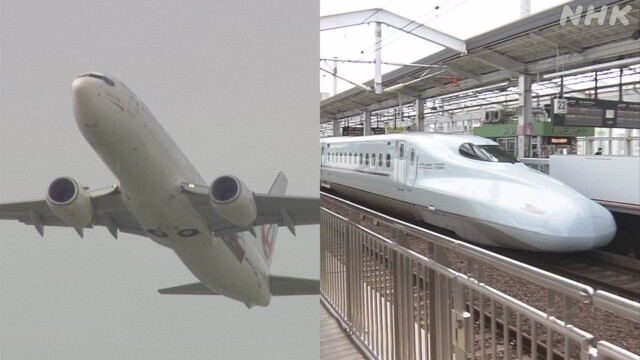しかし、大雨警戒レベルの中で同じ「4」とされていることもあり、自治体へのアンケートでは、「意味の違いが住民に理解されていない」などの声が上がっていました。
このため、21日開かれた内閣府の作業部会では、2つの情報を「避難指示」を基本に一本化する案が示され、了承されました。
また、大雨警戒レベル「5」の「災害発生情報」は、すでに災害が発生、または発生の可能性が極めて高い状況で緊急に身の安全を確保するよう求めるために作られましたが、「住民が何をしてよいかわからない」として位置づけや内容を変える案が出されました。
しかし、専門家から「『避難指示より上の情報が新設される』と受け取られるおそれがある」などという意見が出され、再検討することになりました。
作業部会の座長で東京大学大学院情報学環の田中淳特任教授は「一本化によって情報がシンプルに整理されることになる。一方、「レベル5」はすでに災害が発生している段階だ、という大前提がどうすれば伝わるか、引き続き議論を進めたい」と話しています。
内閣府は今後、災害対策基本法を改正したうえで来年度にも運用を始めたいとしています。
ことしは引き続き、「勧告」と「指示」の2つの情報が自治体から出されることになります。
違いがわかりにくいと繰り返し指摘
 自治体が発表する避難に関する情報は、「避難準備の情報」と「避難勧告」それに「避難指示」があります。
自治体が発表する避難に関する情報は、「避難準備の情報」と「避難勧告」それに「避難指示」があります。
避難勧告がお年寄りなどに限らず、危険な場所にいる人全員の避難が必要だとする情報なのに対し、避難指示は、災害発生のおそれが極めて高く、重ねて避難を呼びかける場合に出されるものです。
しかし、この2つの情報の違いがわかりにくいという指摘は自治体や専門家から繰り返しされていました。
さらに、去年5月から運用が始まった5段階の大雨警戒レベルでは、「勧告」と「指示」はいずれも「危険な場所から避難」を意味するレベル4に位置づけられました。
運用開始直後の10月に起きた台風19号の被害を受け、内閣府が全国の自治体を対象にアンケートをしたところ、「同じ警戒レベル4の中に2つの情報が入っていて分かりにくい」という意見が全体の7割近くに上りました。
また、被災自治体の住民を対象に行った調査では、2つの情報の意味を正しく理解していた人は2割弱にとどまりました。
また、避難を始めるべきタイミングを尋ねたところ「避難勧告」と答えた人は26%余りにとどまり、「避難指示」が40%、「災害発生情報」が12%と、仕組みの理解が十分にされていない実態も浮き彫りになりました。
情報をどう避難に結び付けるか
 災害に関する情報は、近年相次ぐ被害を受け、毎年のように整理や変更が繰り返されています。
災害に関する情報は、近年相次ぐ被害を受け、毎年のように整理や変更が繰り返されています。
災害時の住民の避難行動に詳しい、京都大学防災研究所の矢守克也教授は、現状について、「災害情報自体が非常に複雑化、高度化しているので、関係性の整理や統一ということにエネルギーがかかりすぎ、情報をどう避難に結び付けるかという肝心な部分の検討が後回しになっている面は否めない」と指摘しています。
そのうえで、今後求められることとして、「避難にとって情報は『主役』ではなく、避難を促すための『脇役』だと意識を変え、「どのタイミングで避難するのか」など情報を避難に結び付けるための知恵を住民や自治体に持ってもらうような支援が情報本体の改善以上に重要ではないか」と述べ、情報が活用されるための取り組みに重点を置くべきだと指摘しました。