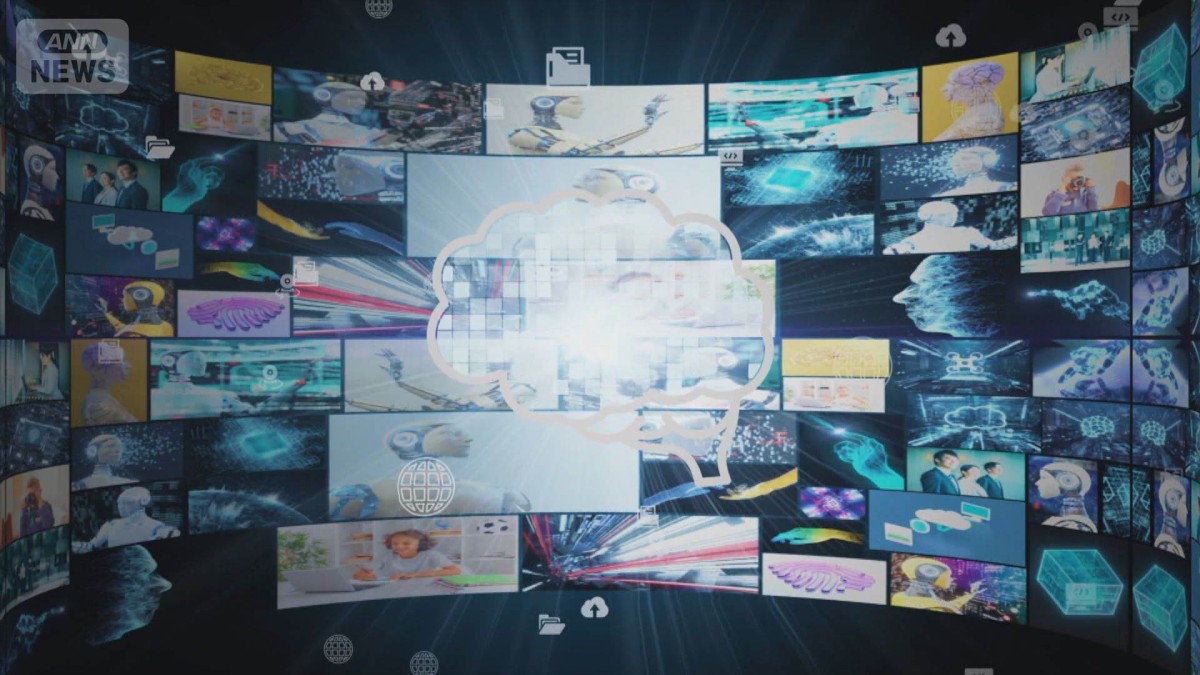厚生労働省によりますと、去年10月の時点で育児休業を取得することができる人のうち、実際に取得した人の割合は女性が83%だったのに対し、男性は7.48%でした。
厚生労働省によりますと、去年10月の時点で育児休業を取得することができる人のうち、実際に取得した人の割合は女性が83%だったのに対し、男性は7.48%でした。
こうした現状を踏まえ、厚生労働省は男性が育休を取得しやすい環境作りに向けた検討を労使の代表などで作る審議会で始めました。
具体的には、女性の負担が大きい出産直後に休みやすい手続きや出産後8週間以内に1回目を取得した場合、2回目を認めた分割取得の回数を増やすかどうか、企業が育児休業の制度について労働者に説明することを義務化するかどうかなどを議論することにしています。
また、企業に対して育児休業の取得率の公表を促す方法も検討することにしています。
厚生労働省は労使の議論がまとまれば必要な法改正を行うことにしています。
男性の育児休業取得率 低い水準続く
育児休業について、法律では労働者が休業を希望する1か月前までに企業に申し出ることで取得できるとされています。
原則として子どもが1歳になるまでに1回取得できることとなっていますが、男性については、1回目を取得して8週間以内に終えた場合は、条件を満たせば2回目の取得が可能となる分割取得の特例が認められています。
また育児休業中、賃金が大幅に減った時の国からの給付金は開始から6か月間は賃金の67%が6か月以降は賃金の50%が支給されます。
さらに社会保険料の支払いも免除されます。
ただ、厚生労働省によりますと男性の取得率は昨年度、7.48%にとどまり、取得期間も8割が1か月未満と、短い傾向があります。
政府は、男性の育休の取得率をことしまでに13%、5年後までに30%とする目標を掲げていますが、それと比べても低い水準となっています。
育児休業を取得しなかった理由としては、「会社で育児休業制度が整備されていない」とか、「収入を減らしたくない」、「職場が取得しづらい雰囲気だった」といった声のほか、業務の繁忙さや休んだ場合に自分の仕事を任せることができる人がいないといった声もあるということです。
中小企業の多く「義務化」に慎重
育児休業は労働者からの申し出を受けて企業が認めることになっていますが、中小企業の多くは取得の「義務化」には慎重な姿勢を見せています。
日本商工会議所は多様な人材の活躍について、ことし7月から8月にかけて加盟する全国の中小企業6007社を対象に調査を行い、このうち48.9%にあたる2939社から回答を得ました。
この中で、女性社員の活躍に関する取り組みについて尋ねたところ、「推進している」と答えたのは81・5%、「推進していない」が12%でした。
そのうえで男性社員の育児休業取得の「義務化」について尋ねたところ、「反対」が22.3%、「どちらかというと反対」が48.6%で70%以上が「義務化」に反対した一方、「賛成」は6.7%、「どちらかというと賛成」が20.6%でした。
「義務化」に反対した割合が高かった業種は、運輸業が最も高く81.5%、次いで建設業で74.6%、介護・看護で74.5%で、人手不足が深刻な中、代わりの人手の確保が難しいことなどが背景にあるとみられています。
調査にあたった日本商工会議所の杉崎友則さんは「仕事と子育てが両立できる環境の重要性を認識する中小企業は多いが、人手不足が深刻な中での『義務化』には慎重になってしまうのではないか。育児休業ではなく有給休暇で対応する男性が多く、男性に育児休業をより取ってもらうには、国民的な機運の醸成や企業向けの政策などが求められるのではないか」と話しています。
「男性社員 育休取得率100%」の会社も
 新潟県長岡市にある建築部品メーカーのサカタ製作所はおととしから育児休業を希望した男性社員は全員取得しています。
新潟県長岡市にある建築部品メーカーのサカタ製作所はおととしから育児休業を希望した男性社員は全員取得しています。
3年前、男性社員から育児休業を取りたいと相談を受けたことをきっかけに、会社をあげて育児休業を取りやすい環境づくりを進めてきました。
この会社は残業を減らすために一人ひとりの社員が積極的に複数分野の業務スキルを身につける「ワークシェア」に取り組んでいて、育児休業で社員に欠員が出ても問題なく対応できているということです。
さらに、育児休業を取った時期や期間によって変わる手取りの金額をシミュレーションして示したり、育児休業で欠員が出ても応援態勢が組める計画を早めに立てたりした結果、おととしからは希望した11人の男性社員全員が育児休業を取得できたということです。休業の期間は最も長かった人は23日間でした。
 ことし6月に出産後5か月で育児休業を18日間取得した大平雅史さん(29)は「最初は育休制度のことが分からず、不安でしたが、会社が丁寧に制度について教えてくれた上、自分が休んでいてもほかの社員が仕事をカバーしてくれる状況だったので、安心して休みを取ることができました。ふだんなかなかできない子どもの世話ができ、よかったです」と話していました。
ことし6月に出産後5か月で育児休業を18日間取得した大平雅史さん(29)は「最初は育休制度のことが分からず、不安でしたが、会社が丁寧に制度について教えてくれた上、自分が休んでいてもほかの社員が仕事をカバーしてくれる状況だったので、安心して休みを取ることができました。ふだんなかなかできない子どもの世話ができ、よかったです」と話していました。
現在の育児休業制度は原則として最長で1年間休業を取得できるため会社では男性社員が1年間休業した場合でも業務に支障が出ないような態勢づくりを目指すことにしています。
 サカタ製作所の坂田匠社長は、「今後は、さらに長期間の育休を取りたいという社員がいた場合に備えたフォロー態勢や職場復帰した時の環境づくりが次のテーマだと考えています。世間で育休のことが話題になっていますが当たり前の権利なので自由に取らせるべきだと思います」と話していました。
サカタ製作所の坂田匠社長は、「今後は、さらに長期間の育休を取りたいという社員がいた場合に備えたフォロー態勢や職場復帰した時の環境づくりが次のテーマだと考えています。世間で育休のことが話題になっていますが当たり前の権利なので自由に取らせるべきだと思います」と話していました。