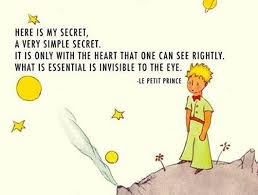2010年、本格的に働き方改革に乗り出しました。
これまでに社内託児所の設置や「朝型勤務」の導入、それにがんの予防や治療を支援する制度の導入などを進めてきました。
特に「朝型勤務」の導入後、午後8時以降に残業している社員の割合が30%から5%に減ったほか、午後10時以降の残業はほぼゼロになるなど、限られた時間で効率的に成果を出す意識が社内で浸透したといいます。
深夜残業も多く、激務のイメージがある総合商社。
「朝型勤務」は2013年から導入された取り組みです。
午後8時以降の仕事は原則禁止した上で残った仕事は翌朝の8時までに出社して行う制度で、早朝に勤務した場合は深夜残業と同じ割増し賃金が支払われます。
さらに早朝に勤務をはじめることで、育児や介護など社員の都合に合わせて早ければ午後3時以降に仕事を切り上げることもできます。
本社の社員では1日に約6割が「朝型勤務」を利用しているということです。
2005年は全国平均が1.26だったのに対し、社内では0.60。 2010年は全国平均が1.39だったのに対し、社内では0.94。 しかし働き方改革に取り組みはじめたあと、急激に上昇。 2021年は全国平均が1.30だったのに対し、社内では1.97でした。
この結果については村木さんは、仕事と家庭の両立の観点で働き方改革を分析したところ、出生率が向上していることがわかったと説明しています。 そのうえで企業が働き方改革を進める背景について、次のように明かしました。 村木厚子さん 「これからの日本は人手不足が目に見えているわけです。ですので、働き方改革に取り組むことと、社員の豊かな暮らしや次世代を産んで育むことを会社として応援するというメッセージが大事だと思います」
小關さんの主な1日は、娘と一緒に出社して会社の託児所に娘を送り届けます。 そして会社が無料で用意している朝食をとったあと午前8時前には勤務を開始。 夕方の娘の迎えは妻が行いますが、娘の体調が悪いときなどは小關さんが仕事を早く切り上げることもあるといいます。
「時間的な制約や金銭的な制約など、各家庭で気にしているポイントは違うと思いますが、娘が発熱したときに迎えに行くことができるなど、柔軟な働き方が認められていることが大きいです」 さらに育児に関わる時間や趣味や自己研鑽など、自由な時間が増えたことで仕事の効率もあがったと実感しているといいます。 小關亮太さん 「必ずしも仕事に取り組んでいる時だけ考えやアイデアが浮かんでくるわけでなく、趣味の時間で生まれて来たものを夜に自分宛にメールで送り、翌朝見直して考えて取り組むことで好循環が生まれています」
繊維を扱う部署で仕事の半分は海外とのやり取りですが、夕方には1度帰宅して子どもの迎えやお稽古事の送迎を行ったあと、午後6時ごろから自宅で電話会議に参加するなど仕事を再開しているといいます。 入社当初は、「商社といえば夜が遅いイメージ」があり、仕事と子育ての両立は難しいのではないかと思っていたということですが、朝型勤務制度の導入後に2人目の子どもを授かり、夫婦で分担しながら2人の子育てができているといいます。 山路梨絵さん 「気持ち的に負い目を感じていないというのが大きいです。仕事の終わりが決まっているからこそパフォーマンスで返さないといけないと逆に良い緊張感にもなっています」
厚生労働省は28日、去年生まれた子どもの数は速報値で79万9728人と1899年に国が統計を取り始めて以降、初めて80万人を下回ったと発表しました。 おととしより4万3000人あまり、率にして5.1%減少。 出生数が減少するのは7年連続です。 国立社会保障・人口問題研究所が2017年に公表した予測では、日本人の子どもの出生数が80万人を下回るのは2030年となっていて、少子化が想定を上回るペースで進んでいます。 厚生労働省は出生数の減少について「結婚や出産、子育ての希望実現を阻むさまざまな要因が複雑に絡み合っているとみられる。社会や経済の基盤が大きく変わる危機とも言え、関係省庁と連携しながら対策に取り組んでいきたい」としています。
その後、上昇傾向が続き、第1次ベビーブーム(昭和22年~24年)にあたる 1949年(昭和24年)には最多の269万6638人に上りました。 そのあとは減少傾向となり、1960年代から1970年代半ばごろにかけて一時、増加に転じ、第2次ベビーブーム(昭和46年~49年)にあたる1973年(昭和48年)には209万1983人に上りますが、その後は再び減っていきました。 1989年(平成元年)は124万6802人、1990年代は120万人前後で推移していましたが、2000年代に入るとさらに減少傾向となり、2016年(平成28年)には97万7242人とはじめて100万人を下回りました。
その後は夫婦のライフスタイルの変化とともに年々増加傾向が続き、2007年(平成19年)には1013万世帯とはじめて1000万世帯を超えました。 さらに去年(2022年)は1262万世帯と統計を取り始めたおよそ40年前と比べると2倍以上に増えています。
▽児童手当を中心とした経済的支援の強化 ▽幼児教育や保育サービスの充実 ▽育児休業制度の強化を含めた働き方改革の推進
労働政策研究・研修機構 樋口美雄理事長 「日本や韓国などの出生率が低下している国をみると、男性は外で働き女性は家庭を守るといった従来の慣習が残っていることが原因の1つだとみられるので、働き方改革は少子化対策にとって不可欠で、男女とも協力して子育てができる環境を企業が作っていくことが重要だ」 「働き方改革は大手企業だけでなく中小企業でも取り組むことができる。多くの企業で広がってきているが、より多くの企業で広げるためには、経営者のリーダーシップや社員の理解の促進のほか、働き方改革に詳しいコンサルタントや社会保険労務士といったアドバイザーにその企業に適した助言をしてもらうことも必要だ」
日本総合研究所 藤波匠 上席主任研究員 「新型コロナの影響で結婚の数が大幅に減少したことが出生数の減少にもつながったのではないか。少子化が進むことで経済成長が止まるだけでなく社会保障制度の負担も重くなり日本の将来を担う若い人たちが将来に対して前向きになれなくなる可能性もある。子どもを望む人や結婚したい人が前向きになれるような支援などを通じて子どもを産むかどうかも含め、自由に選択できるような社会を目指していくことが求められる」
働き方改革 出生率にも好影響



子育て中の社員は?



国内の出生数 初めて80万人を下回る

出生数は減少 共働きは約40年で2倍以上に

国の少子化対策「3つの柱」は
少子化問題 どう考える?専門家たちは