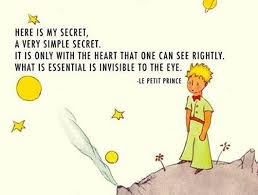幼いころから母親と勧誘活動をしてきたという小松猛さん(40)は、「宗教の取り決めで、人生の選択肢を奪われた人がいることを知ってほしい」として、今回の会見を機に初めて実名で取材に応じました。
小松さんは、幼い頃から母親の勧誘活動に同行するよう教えられ、土日の集会などにも欠かさず参加したということです。集会で落ち着きがなかったり、勧誘活動を笑顔でできなかったりすると、「愛のある懲らしめ」として、ベルトを2重3重に折ってテープで巻いた、手製のむちでお尻をたたかれたといいます。
友達と遊ぶ時間がほとんどなく、中学生になって「部活動をやりたい」と母親に訴えましたが、「聖書を学ぶことが優先だ」と言われ、認めてもらえなかったということです。
小松さんは当時について、「物心がついたときから教団の考えに合わない行動は矯正されるという経験を続けてきたため、疑問があっても親の信仰にあうように生きるしか選択肢がなかった。“自分はこれで生きていくしかない”と思うようになっていった」と話していました。
20歳のころ、アルバイト先で信者ではない同僚と交際したことをきっかけに「エホバの証人」を脱会しました。それ以来、およそ20年間親子の関係が途絶えているといいます。
小松さんは、「母親には『親子の関係を戻したい』と言ったことがあるが、『信仰が戻らないかぎり一切関係は持てない』と断られた。自分も親になったが、孫の顔を見せることすらできない」と話していました。
そのうえで、「信教の自由があるので母親に信仰をやめてほしいとは思っていないが、脱会して親子関係が破綻するのはおかしい。教団がそのような指導をしているならやめてほしいし、子どもに親の信仰を強要することは絶対にやめてほしい。いろいろな世界を見せたうえで、親が信じる宗教を信じるかどうか、子どもが決められるようにしてほしい」と訴えていました。
厚生労働省の担当者は「実態の把握も含めて対応を考えたい。児童虐待防止法では、行政側に宗教団体などに対する指導や監督の権限がなく、その中で何ができるかを考える必要がある」と述べました。 また、警察庁の担当者は「虐待や宗教問題にかかわらず、事実関係に即して、厳正に対処していく。児童の安全が大事で、保護すべきものは関係機関と連携して対応していく」と述べました。
立民が会合「早急に調査すべきだ」