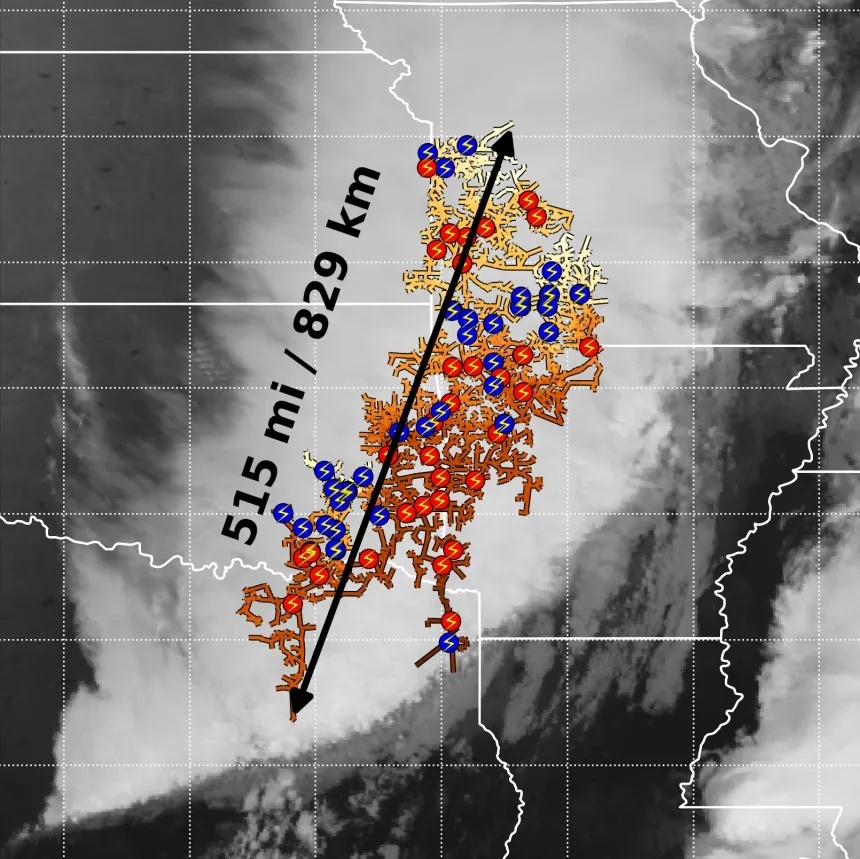生まれつき
子宮がない
女性などに
親族などから
提供された
子宮を
移植して
出産を
目指す「
子宮移植」について、
日本産科婦人科学会などの
学会は、
臨床研究の
指針の
策定を
始めることになりました。
国内で
移植の
検討を
行うグループが
臨床研究の
計画案を
学会に
提出したこと
などを
受けて
始めるもので、
技術的な
課題や
倫理的な
問題について
議論が
本格化することになります。「
子宮移植」は、
生まれつき子宮がない
女性などに
親族などから
提供された
子宮を
移植し、あらかじめ
準備していたパートナーとの
受精卵を
着床させて
出産することを
目指すもので、スウェーデンなどの
一部の
国で
行われ、
世界で10
人余りが
生まれたと
報告されています。
国内では、慶応大学病院のグループと名古屋第二赤十字病院などの2つのグループが、それぞれ臨床研究の実施を検討していて、このうち慶応大学病院のグループは7日、日本産科婦人科学会と日本移植学会に臨床研究の計画案を提出したことがわかりました。
計画案では、子宮が生まれつきないロキタンスキー症候群の女性を対象として、5例程度を実施するとしています。
ロキタンスキー症候群は女性の4500人に1人ほどの割合でいるとされていて、提出を受けた学会は、子宮移植を受ける患者や提供者の条件、それに実施する施設や医師の要件などを指針としてまとめる議論を始めることになりました。
子宮移植をめぐっては、出産のために健康な女性から子宮を取り出すことが許されるのかといった倫理的な問題に加え、これまでに世界で行われた移植では、出産に至らないケースも報告されているほか、移植後に服用する免疫抑制剤の胎児への影響など、技術面や安全面での課題もあり、今後、議論が本格的に行われることになります。
日本産科婦人科学会の倫理委員会の委員長で、徳島大学の苛原稔教授は「子宮移植は病気で子宮がない女性の選択肢の1つとしては考えられると思う。ただし、一般化されていない技術であり、問題点を一つ一つ解決しながら取り組むべきものだ。学会として指針を作り、研究を支援していきたい」と話しています。
移植に課題も
「子宮移植」は、子宮のない女性に親族などから提供された子宮を移植し、あらかじめ用意しておいたパートナーとの受精卵を着床させて妊娠と出産を目指します。
子宮を移植したあとは、拒絶反応が起きないかなどを時間をかけて確認したうえで受精卵を子宮に戻すほか、出産は帝王切開で行い、出産後は移植した子宮を手術で取り除くことになります。
今回の臨床研究では、4500人に1人の割合でいるとされている先天的に子宮がないロキタンスキー症候群の女性を対象に行うとしています。
海外ではこれまでにロキタンスキー症候群のほか、がんなどで子宮を摘出した女性を含めて、およそ50例行われていて、2014年にスウェーデンで子宮移植を受けた36歳の女性が世界で初めて出産するなど、スウェーデンやアメリカ、ブラジルなどで10人余りの子どもが生まれています。
一方、専門家によりますと、トルコやスウェーデンでは流産したケースが報告されているほか、移植した子宮がうまく定着せず、再び取り出したケースも10例以上報告されているということです。
臓器移植は通常臓器の働きが悪くなり、命の危険がある場合などに行われます。しかし、子宮移植は妊娠や出産をするために健康な第三者の体にメスを入れ子宮を取り出すため、提供者の体と心に大きな負担が伴うことになり、倫理的に許されるのかといった課題があります。
また、移植を受けた女性は拒絶反応を防ぐため、免疫抑制剤を使用しますが、この薬が胎児に与える影響についても詳しく検討する必要性が指摘されています。
専門家「当事者置き去りになる可能性も」
生命倫理の問題に詳しい北里大学医学部の齋藤有紀子准教授は、子宮がないために妊娠を諦めていた人たちの気持ちは切実で、その思いは否定されるべきではないとしたうえで、「健康な体にメスを入れる生体移植は、やむをえない場合に例外的に行われるもので、生命の維持に関わらない子宮移植に関しては、当事者の切実さや技術の確立だけですぐに正当化できるものではない。この技術は不妊医療、移植医療としての側面に加え、当事者の親の気持ちや移植という選択肢を示すことで、当事者自身が感じるプレッシャーなどにどのように対応していくのかといった課題もあり、課題の解決なしに見切り発車をすると、当事者の女性やその家族が置き去りとなってしまう可能性がある」と指摘しています。