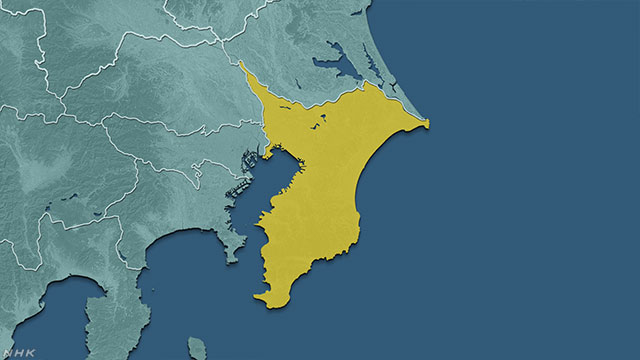突然の
臨時休校によって、
朝から
子どもを
受け入れることになった
学童保育の
現場は、
国や
自治体からの
十分なサポートがない
中、
職員の
確保や
マスクや
消毒液の
不足など困難な
状況に
直面しています。
大阪 東成区で
NPO法人が
運営する「かわせみ
学童保育所」です。
臨時休校に
合わせて
朝8時から20
人ほどの
子どもたちを
受け入れていますが、
大きな困難に
直面しています。
1つ目が「マスクと消毒液の調達」です。
感染防止の対策として、職員はマスクを着用し、机やドアノブなどを1日数回アルコールで消毒していますが、こうしたマスクや消毒液は自分たちで調達しなければなりません。最近は、休みの職員が朝からドラッグストアに並んでいますが、買えないことも多く、消毒用のアルコールはあと2日でなくなってしまいます。
2つ目が「子どもどうしの距離の確保」です。
厚生労働省や文部科学省は、学童保育では子どもどうしができるかぎり接触しないよう、席の間隔を1メートル以上離すことを求めています。しかし、この学童保育所はスペースが限られていて、子どもたちが遊んだり食事をしたりするとき、すぐ近くに座らなければならず、国が求める距離をとるのは難しいのが実情です。
3つ目が「働く職員の確保」です。
職員は最低でも2人が朝8時に出勤する必要があり、5人の職員でやりくりしていますが、突然のことで対応が難しく、1日の勤務が11時間を超える職員も出ているということです。
そして4つ目が「経済的な手当が不十分なこと」です。
国は朝から運営することになった学童保育所に対し、1日につき1万200円の補助を出す予定ですが、運営時間が長くなった分の人件費や光熱費などを賄うには足りず、この学童保育所では今月はおよそ5万円の赤字になる見込みです。
かわせみ学童保育所の職員、中西三保さんは「国はこうした現場の実態が分かっていないと感じています。子どもたちや保護者のことを考えて私たち現場は、何とかして学童保育所を開けようと努力しています。国は現場に責任を押しつけるのではなく、現場の状況を知ったうえで安心して学童保育を開けるよう、努力してもらいたい」と話していました。