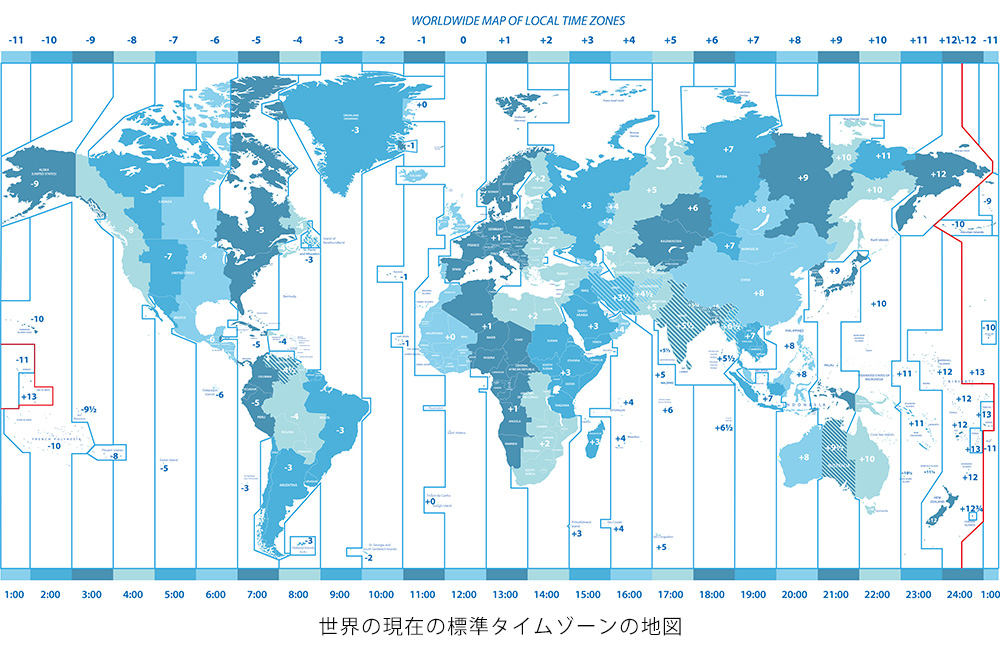初日の討議では、ほとんどの国から激しさを増す米中の貿易摩擦で、世界経済が下振れするリスクが高まっているとして、懸念の声が相次いで出されました。
また麻生副総理兼財務大臣も、記者会見で、貿易摩擦が解決されないと市場からの信頼を損なうおそれがあると指摘しました。
このため2日目の討議は、各国が協調して問題解決に取り組む姿勢を打ち出せるかが焦点となります。
ただ、アメリカは関税引き上げをテコに対立が先鋭化しやすい2国間の貿易交渉で問題解決を目指す姿勢を崩していません。
議長国の日本は9日の討議で、貿易を含めた収支の不均衡は多国間の枠組みで解決する必要があると訴え、対立の緩和につなげたい考えです。
また9日は、国境をまたぐデータのやり取りでばく大な利益を上げる、巨大IT企業への新たな課税ルールをめぐっても議論が交わされる予定で、来年中に具体案を取りまとめることで各国が一致する見通しです。
「新たな課税ルール」 なぜ検討?
新たな課税ルールが検討される背景には、グーグルやアマゾンといった巨大IT企業が利益を伸ばす中で、従来のルールでは十分に課税できないという問題意識があります。今の国際的な課税ルールがビジネスの電子化に追いつけていないためです。
これまでの国際的な課税ルールは、「拠点なくして課税なし」と言われるように、「国内に店や工場といった企業の物理的な拠点があるかどうか」が課税の基準となっています。
この基準を前提に、例えばインターネット上で、音楽の配信サービスを行っている企業の場合を考えます。
本社が海外にあり、日本に支店などの物理的な拠点がなかったとしても日本国内の利用者は、インターネットを使って音楽配信のサービスを受けることができます。
しかし、この場合、今の課税ルールでは日本国内に物理的な拠点がないため、この企業が上げた利益に対して日本は課税することができません。
さらに、この企業が本社をいわゆるタックスヘイブンと呼ばれる税率の低い国に置いていた場合には、結局どこの国も十分な課税ができないという問題も指摘されています。
「新たな課税ルール」とは
世界およそ130か国が作る国際的な枠組みでは、こうしたIT企業にも対応できる新たな課税ルールの具体案を、来年・2020年に取りまとめることにしています。
この中では、各企業が提供するサービスの各国での利用回数や、マーケティング費用などに応じて課税することなどを検討していく方針です。
たとえば、利用者の検索回数などを基準としたり、顧客リストや広告宣伝費などを基準にすることが考えられます。
一方、多国籍企業が、「タックスヘイブン」と呼ばれる税率が低い国に利益を移して課税逃れをした場合には、追加で課税するルールも検討していく方針です。
ただ、G20各国の中でも巨大なIT企業を抱えるアメリカと、ヨーロッパの国々などとの間で立場や意見の違いがあるだけに、今後、どういった企業をルールの対象にするのかや、具体的な税率をどう設定するのかなどをめぐって、調整が難航することも予想されます。
経団連「適用はIT企業などに限定を」
新たな課税ルールに対しては、日本の経済界でも、その議論の行方に注目が集まっています。
大企業が多く加盟する「経団連」は、新たなルールがどういった企業に適用されるのか神経をとがらせています。
現在、国際的な枠組みで検討が進められているルールでは、グローバルにビジネスを展開している企業であれば、IT企業に限らず適用される可能性があるからです。
このため経団連は、海外でも広く製造・販売している日本の自動車メーカーや電機メーカーなどがルールの対象となった場合、税負担が増すおそれもあるとみて、ルールの対象企業をIT企業などに絞るよう求めています。
経団連の井上隆常務理事は、「デジタル革新はこれからもどんどん広がっていくので企業の活動は何らかの形でデジタル経済と絡んでいくが、すべての企業が課税対象になるのは、現実的ではない。デジタルな技術革新が阻害されないことが重要で、G20のリーダーシップに期待したい」と話しています。
IT企業など「幅広く適用を」
一方、楽天やヤフーといったIT企業などでつくる「新経連」は、経団連とは異なり新たなルールを幅広い企業に適用するよう求めています。
経済のデジタル化が進む中、IT企業と伝統的なメーカーなどとの境目はなくなりつつあり、将来にわたって有効なルールとするためにも、IT企業だけに対象を絞るべきではない、と考えているからです。
日本国内の企業の間でも主張が分かれる中、G20各国の間で新たな課税ルールをめぐってどんな議論が交わされるのかも今回の会議の焦点となります。