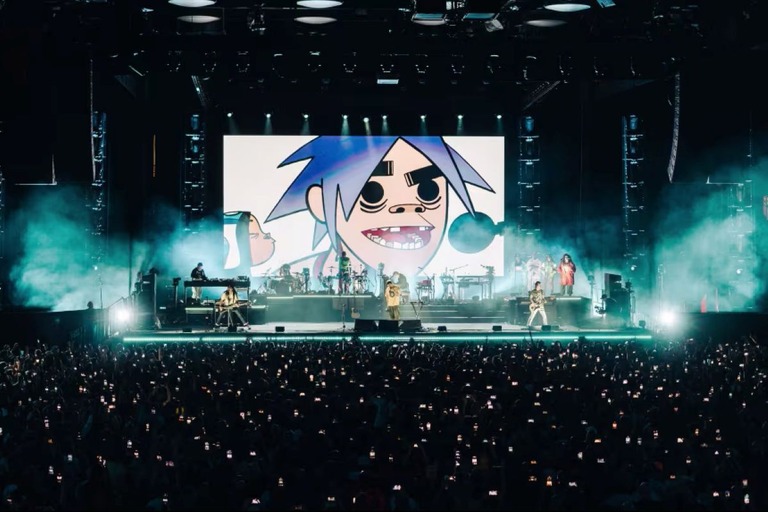これまで国内では報告が無く、和名が無かったため、今回、東京文化財研究所などのグループが和名として新たに「ニュウハクシミ」と名付けました。
この数年、国内の博物館などから害虫を捕まえるトラップで捕獲されたという報告が相次いでいるということで、これまでに北海道から九州までの少なくとも7か所から捕獲の報告が寄せられているということです。
従来のシミは、捕獲されても、1か所で1匹、2匹程度だったのに対して「ニュウハクシミ」は100匹以上捕獲されたケースがあったということです。
また、これまで見つかった「ニュウハクシミ」は体の特徴からすべてメスで、研究のためにメス1匹だけを飼育しても次々と増えたことなどからメスだけで繁殖できる可能性があるということです。
「ニュウハクシミ」は、100年以上前の1910年にスリランカで初めて報告され、2017年にヨーロッパでも初めて確認されたということで、これまでにおよそ20か国で見つかっているということです。
グループによりますと、ヨーロッパなどでは新型コロナウイルスの影響で博物館などが閉館していた間に繁殖した可能性が指摘されているということです。
国内での詳しい実態は分かっていませんが資料の貸し借りなどを通じて「ニュウハクシミ」が広がったとみられるということです。
紙の表面をなめ取るように食べることから古文書の文字などが失われてしまうため一度、被害にあうと復元が難しいとされています。 ただ、これまで国内で知られていた「シミ」は短期間で急速に増えることはなく、温度や湿度の管理や清掃などを適切に行うことで、文化財への被害を防ぐことができていたということです。 東京文化財研究所などのグループでは新たに確認された「ニュウハクシミ」は詳しい生態が分かっておらず、従来の対策だけでは文化財に被害が出るおそれがあるとして、全国の博物館などに注意を呼びかけるほか、殺虫剤など駆除の方法について研究を急いでいるということです。
古文書への影響は