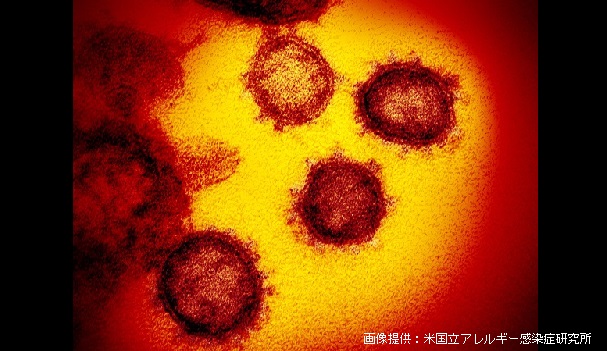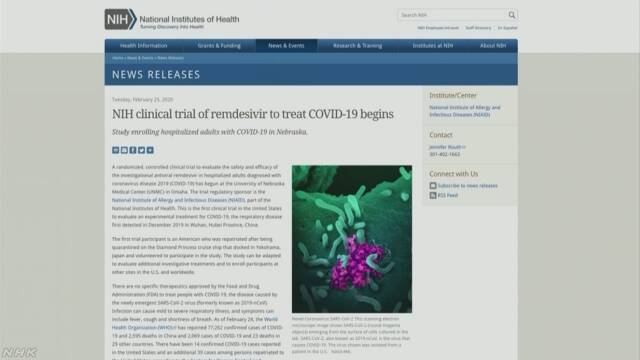昭和20
年代に
ハンセン病の
患者とされた
男性が、
隔離された「
特別法廷」で
死刑判決を
受けた、
いわゆる「
菊池事件」をめぐって、
男性の
無実を
訴える人たちが
再審・
裁判の
やり直しを
求めない
検察の
対応は
違法だと
訴えた
裁判で、
熊本地方裁判所は
男性が
裁かれた
特別法廷はすべての
国民が
法の
下に
平等で
あることを
定めた
憲法に
違反していたという
判断を
示しました。
一方で、
国に
賠償を
求める訴えについては
退けました。
最高裁 特別法廷の憲法違反は認めず
「菊池事件」など特別法廷で行われた裁判について、4年前、最高裁判所は、手続きが違法だったとする報告書を公表し、異例の謝罪をしましたが、特別法廷が憲法に違反していたという外部からの指摘については認めませんでした。
最高裁判所はハンセン病の元患者などで作る団体から申し入れを受け、隔離された療養所などに設けた特別法廷で行われた95件の裁判について検証を始め、4年前、報告書を公表しました。
報告書では、裁判の内容の検証については裁判の独立を侵害するおそれがあるため対象外だとしたうえで、裁判所以外の場所を特別法廷として審理の場に指定した手続きの問題点を検討しました。
その結果、遅くとも昭和35年以降、ハンセン病は確実に治るとされていたにもかかわらず、当時の最高裁が必要性を精査しないまま、各地の裁判所からの申請を受けて原則、特別法廷を認めていたことを問題点として挙げました。
そのうえで、昭和35年以降については差別的に扱った疑いが強く、手続きを定めた裁判所法に違反していたと認め「偏見や差別を助長し、患者の人権と尊厳を傷つけたことを深く反省し、おわび申し上げる」として異例の謝罪をしました。
一方、最高裁とともに検証していた有識者の委員会や、検証を求めた元患者などから「平等の原則を定めた憲法に違反していた」と指摘されていたことについては、「当時の最高裁内部の検討が資料として残っていないので判断できない」として認めませんでした。
また元患者などが「裁判の公開の原則に違反していた」と指摘していた点については、裏付ける資料が確認できなかったとして、「非公開だったとは言えない」としていました。
ハンセン病の患者は「特別法廷」で裁判
ハンセン病の患者は、およそ90年間にわたって国の政策によって隔離され、療養所などに設けられた「特別法廷」で裁判が行われることもありました。
ハンセン病は、感染力が極めて弱く、治療法が確立された病気ですが、国は、平成8年に「らい予防法」が廃止されるまで、患者を強制的に療養所に隔離する政策を続けました。
この間、各地の裁判所も、通常の法廷ではなく、隔離された療養所や刑務所などに設けた「特別法廷」で患者の裁判を行っていて、件数は95件に上りました。
隔離政策について国と国会は、平成13年に誤りを認めて謝罪し、厚生労働省の委託を受けた機関は、平成17年に「ハンセン病を理由とした特別法廷は不合理な差別だ」とする検証結果をまとめました。
しかし最高裁判所は、その後も当時の対応を検証せず、元患者などで作る団体が第三者機関による検証を申し入れた結果、6年前にようやく検証を始めました。
最高裁は、外部の専門家による有識者委員会も設置し、この委員会は、「通常の法廷で裁判を受けられなかったのは平等の原則を定めた憲法に違反していた」という意見をまとめました。
一方、最高裁は、手続きが違法だったことは認めましたが、憲法に違反していたとは認めませんでした。
特別法廷とは
ハンセン病の患者の特別法廷は昭和23年から昭和47年まで95件開かれ、一般の人の出入りがほとんどない療養所や刑務所などで審理が行われていました。
刑事裁判や民事裁判は原則として裁判所にある公開の法廷で開くことになっていますが、最高裁判所が認めた場合、別の場所を特別法廷に指定することができます。
最高裁判所によりますと、ハンセン病患者の特別法廷は、「感染のおそれ」を理由に、昭和23年から昭和47年まで95件開かれ、いずれも一般の人がほとんど出入りしない療養所や刑務所などの1室が指定されました。
最も多かったのは、熊本県合志市の「菊池恵楓園」で、近くに設けられた医療刑務所も含めて35件開かれました。
続いて岡山県瀬戸内市の「長島愛生園」で9件、岡山刑務所で8件、東京拘置所で7件、群馬県草津町の「栗生楽泉園」で4件などとなっていました。
今回の「菊池事件」も含めて特別法廷のほとんどは刑事裁判で、元患者の団体は、「裁判官や弁護士、検察官が予防着と呼ばれる白衣に帽子やマスク、長靴をして審理に臨んだものもあった」と指摘しています。