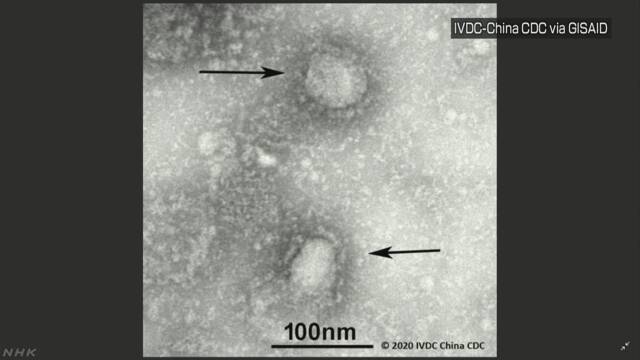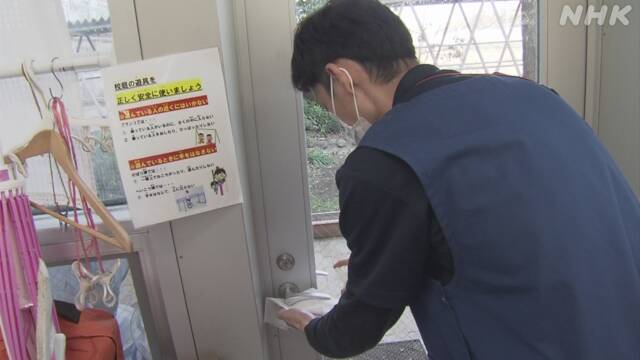そして、21日午前1時10分すぎ、原宿駅の駅員らが1列に並ぶと、「96年間ありがとうございました」とあいさつし、駅のシャッターが閉められました。
21日の始発からは、隣接する新しい駅舎で営業が始まり、午前4時10分に駅のシャッターが開けられると、早速、駅舎の中に入って写真を撮ったり記念に入場券を購入したりする鉄道ファンの姿が見られました。
新しい駅舎は鉄筋の2階建てで、延べ床面積はこれまでの駅舎のおよそ4倍に広がり、これまで1つだったホームは外回りと内回りで2つに分けられ混雑の緩和が見込めるということです。
兵庫県から訪れたという59歳の男性は「先週の高輪ゲートウェイ駅の開業などことしは鉄道ファンにとって例年より忙しい3月となりました。前の駅舎は歴史があって味わい深かったですが、新しい駅舎もきれいでいいですね」と話していました。
新駅舎の特徴は
新しい駅舎は、木造駅舎に隣接する場所に建てられ、鉄筋の2階建てで延べ床面積はこれまでのおよそ4倍と広くなっています。
新駅舎のデザインは、周辺の明治神宮や代々木体育館などとの調和をコンセプトに「主張しすぎないベージュ」を基調とし、ガラス張りで開放感がある空間となっています。
1階部分は改札とコンコースで、出入り口は、竹下通り側と表参道側のほかに新たに明治神宮側にも設けられます。
また、エレベーターを増やし、車いすの人も利用しやすい多機能トイレが整備されたほか、ベビー休憩室も新たに設置されています。
このほか、1階にコンビニエンスストア、2階に東京を中心に展開するコーヒー店がオープンします。
一方、これまで1つだったホームは、外回りと内回りでそれぞれ専用ホームとなり、混雑の緩和が見込めるということです。
原宿駅舎の歴史と特徴
原宿駅は明治39年に開業し、関東大震災のよくとしの大正13年に2代目となる木造駅舎が建てられました。
太平洋戦争では、昭和20年5月の「山の手空襲」で、青山通りや表参道などが焼け野原となる中、原宿駅は奇跡的に焼失を免れ、100年近くにわたって利用されてきました。
2階建ての駅舎は、ヨーロッパの「ハーフティンバー様式」と呼ばれる柱やはりが建物の外に露出するデザインが取り入れられ、白い外壁や屋根の8角形のせん塔の風見鶏が特徴です。
しかし、東京オリンピック・パラリンピックを前に、多くの利用客が見込まれる中、駅が老朽化しているとして、JR東日本は、4年前の平成28年に駅舎の建て替えを発表しました。
その後、駅舎の保存を要望する地元住民などの声を受け、JR東日本は協議の場を設けて対応を検討してきましたが、去年11月、耐火性能の問題などから保存は難しいと判断し、解体することを決めました。
木造駅舎は、東京オリンピック・パラリンピック後に解体されますが、耐火基準を満たした材料で再現した建物が近くに建てられる予定です。