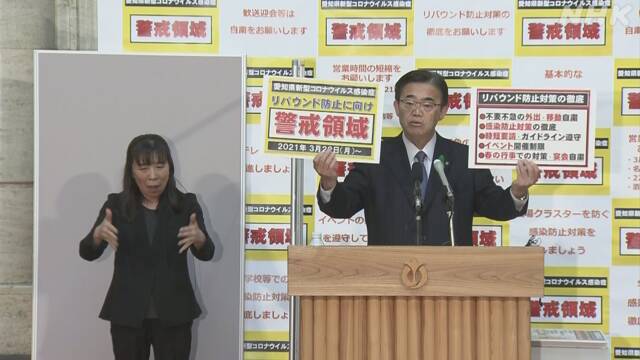“国・地元 双方向の対話機会が少ない”<専門家>
専門家からは地元を含めた関係者との双方向の対話の機会が少なかったことが影響しているとの指摘があがっています。
国は、処分方法について2013年から有識者による委員会などを設けて検討を行い、去年、国の小委員会が基準以下に薄めて「海か大気中に放出する方法が現実的だ」などとする報告書をまとめました。
また、政府は処分方針の決定に向けて去年、地元の農林水産業者や全国の商工団体などから意見を聞く会を開きましたが、出席者はほとんどが組織の代表で割り当てられた時間内に意見を述べる形式のため双方向の対話にはなりませんでした。 合わせて書面による意見募集も行われましたが、方針が決定されるまでの間にこうした意見に対する政府としての見解は示されませんでした。 これについて経済産業省は、なるべく多くの意見を聞くためこの形式を採用したとしていて、処分の方向性が決まらない検討の途中では意見のやり取りができる材料がなかったとしています。
この中で「地元住民などの関係者が十分議論に参加しているか」尋ねたところ ▽「そう思う」は3% ▽「どちらかといえばそう思う」は10.4%だった一方 ▽「そう思わない」は37.4% ▽「どちらかといえばそう思わない」は23.8%で 住民がどのように議論に参加するかが課題になっていたことが伺える結果でした。
そのうえで実際の放出に向けては、関係者の理解を得る努力が長期にわたって必要になるとして「10年の時間を要して十分な納得感が得られていないという声が聞かれる中で政府の責任で決定したのであれば、過去の経緯をきちんと検証し改めて信頼関係を作っていく必要がある」と話しています。
宇宙から飛んでくる宇宙線などによって自然界でも生成されるため、大気中の水蒸気や雨水、海水それに水道水にも含まれ、私たちの体内にも微量のトリチウムが存在しています。 トリチウムは通常の原子力施設でも発生し、各国の基準に基づいて薄めて海や大気などに放出されています。 水素の仲間で水の一部として存在するため、水から分離して取り除くのが難しいのが特徴で、福島第一原発の汚染水から多くの放射性物質を除去する装置を使っても取り除くことができません。
トリチウムが出す放射線はエネルギーが弱く空気中ではおよそ5ミリしか進みません。このため人体への影響は外部からのものよりも体内に取り込んだときのリスクを考慮すべきとされています。 国の小委員会は ▽体内で一部のトリチウムがタンパク質などの有機物と結合し濃縮するのではないかといった指摘があることについては、体はDNAを修復する機能を備えていて動物実験や疫学研究からはトリチウムが他の放射性物質に比べて健康影響が大きいという事実は認められなかったと結論づけています。 また ▽マウスの発がん実験でも自然界の発生頻度と同程度で原子力発電所周辺でもトリチウムが原因と見られる影響の例は見つかっていないとしています。 放射性物質の性質に詳しく国の小委員会の委員をつとめた茨城大学の田内広教授は人体への影響を考える際、濃度の大小がポイントだと指摘します。そのうえで田内教授は「トリチウムが体内に取り込まれてDNAを傷つけるというメカニズムは確かにあるが、DNAには修復する機能があり紫外線やストレスなどでも壊れては修復しているのが日常。実験で細胞への影響を見ているが基準以下の低濃度では細胞への影響はこれまで確認されていない」と話していて、低い濃度を適切に管理できていればリスクは低いとしています。
そのうえで、こうした設備で取り除くことができないトリチウムを海水で薄め基準を大幅に下回るレベルにして放出することになります。 国は放出に当たって放出の前後でのモニタリングを強化し、環境に与える影響を確認しながら少量での放出から開始するとし、モニタリングで異常な値が出た場合などには放出を停止するとしています。 トリチウムの濃度を薄め放出するための設備は新たに作る必要があり、今後、設計や放出までの具体的な計画を東京電力が検討し原子力規制委員会の審査を受けることになります。 国は東京電力に対し、2年後をめどに海洋放出を開始できるよう設備の設置などの具体的な準備を進めることを求めています。
福島第一原発では汚染水の発生量を抑制するため建屋周辺で地下水をくみ上げ海に放出していますが、この中にもトリチウムは含まれています。 こうした水を海に放出する際の東京電力の自主的な基準は1リットル当たり1500ベクレル未満で、国はトリチウムなどを含む処理水の海洋放出にあたっても同様の水準にするとしています。 また、1年間に放出するトリチウムの量については事故の前、福島第一原発が通常の運転をしていた時に目安とされていた22兆ベクレルを下回る水準となるようにするとし、その値は定期的に見直すとしています。
▽関西電力 大飯原子力発電所で56兆ベクレル 高浜原子力発電所で13兆ベクレル 美浜原子力発電所で8600億ベクレル ▽九州電力 玄海原子力発電所で50兆ベクレル 川内原子力発電所で55兆ベクレル ▽四国電力 伊方原子力発電所で16兆ベクレル などとなっています。 経済産業省のまとめによりますと、福島第一原発事故の前の5年間を平均した年間の放出量は、加圧水型と呼ばれるタイプの原発で18兆から87兆ベクレル、福島第一原発と同じ沸騰水型と呼ばれるタイプの原発で0.02兆から2兆ベクレルとなっています。 東京電力福島第一原子力発電所では事故の前の2010年に2兆ベクレル余り放出されていました。
▽中国の大亜湾原発で42兆ベクレル ▽アメリカのキャラウェイ原発で同じく42兆ベクレルが放出されています。 このほか ▽カナダのダーリントン原発で2015年に 液体として241兆ベクレル、気体として254兆ベクレルが放出されています。 ▽またルーマニアのチェルナヴォダ原発では2002年に 液体で85兆ベクレル、気体で286兆ベクレル ▽韓国のウォルソン(月城)原発では2016年に 液体で17兆ベクレル、気体で119兆ベクレル放出されています。 再処理施設では放出量がより多く ▽フランスのラ・アーグ再処理施設では2015年に 液体で1京3700兆ベクレル、気体で78兆ベクレル ▽イギリスのセラフィールド再処理施設では同じく2015年に 液体で1540兆ベクレル、気体で84兆ベクレル放出されています。
タンクにたまった処理水を放出するためにはトリチウムを国の基準以下の濃度に薄めるための専用の設備を作る必要があり、東京電力は今後、福島第一原発の廃炉計画に、新たに作る設備についても反映させ、規制委員会に審査を申請することになります。 規制委員会は東京電力からの申請を受けて、トリチウムを基準以下の濃度に薄める能力が確保されているかや、設備の健全性などを審査の中でチェックします。 審査のほか、建設工事のあとに行われる検査などの手続きもあり、それらに必要な期間について規制委員会の更田委員長は2年程度かかるとの認識を示していて、この審査や検査に合格しなければ設備の稼働は認められません。 また、規制委員会は海洋放出の実施後、福島第一原発周辺の海域で海水に含まれる放射性物質の測定を強化することも検討していて、水質に大きな変化はないか確認するとしています。
去年4月から7回にわたって開かれた地元の農林水産業者や全国の商工団体などから意見を聞く会では、29団体43人のうち半数以上から風評被害対策を示すよう求める意見が出されました。 もともと国はトリチウムなどを含む処理水の処分に伴う風評被害などの社会的な影響について2016年からの国の小委員会の中で議論するとしていました。 しかし報告書では、海洋放出の場合、社会的な影響は特に大きくなるとの指摘があった一方、示された対策は ▽周辺環境のモニタリング強化や ▽測定結果や科学的知見の丁寧な情報発信 それに ▽福島県などが取り組んできた既存の対策の拡充と強化などにとどまり 地元などから具体的な対策が見えないという声が相次ぎました。 経済産業省は理由について処分の方法が決まらない中、仮の話だとしても風評対策について割り切った議論を進めることが難しかったとしています。
また、今後の風評対策については「これまでの風評対策をただ拡充するのではなく水産業や観光など産業の特徴を踏まえてどんな対策は効果があったのか一度、現状を分析するべき。また福島の漁業は本格操業しておらずまだ経営体としてぜい弱なので、流通や消費への対策だけでなく経営体力を強化するような生産基盤に対する支援も必要だ」と指摘しています。
具体的には風評の影響を最大限抑えるためトリチウムの濃度を国の基準の40分の1、WHO=世界保健機関が示す飲料水の基準では7分の1程度に薄めたうえで海に放出するとしています。 また、農林水産業者や地元の自治体の関係者なども加わって放出前後の濃度などを監視するモニタリングを強化するとしていて、IAEA=国際原子力機関の協力も得ながら海洋放出が国際慣行に沿って行われることなどの情報を、科学的な根拠に基づいて発信することにしています。 さらに、水揚げを増やすため漁業関係者の設備導入に対する支援事業を継続するほか、地元や周辺自治体の仲買や加工業者の販路の開拓なども支援します。 このほか、観光業などについても風評被害が懸念されるとして、観光客の誘致や地元産品の販売促進など本格的な復興に向けた対策を講じるとしています。 こうした対策を取っても生じる風評被害には東京電力が賠償を行うよう求めています。 そして、関係閣僚による新たな会議を設けて必要に応じて追加の対策を機動的に実施するとしています。
そのうえで「科学的な理解の醸成と車の両輪のように重要なのは福島県や周辺地域の魚介類の流通経路を決して失わないようにしたり、拡大したりする方策をしっかりと示すことだ。売られているのだから大丈夫だという状況を作り続けていくことが大事だ」と述べ、科学的な理解の醸成に加えて生産・加工・流通・消費の各段階での対策の必要性が盛り込まれたことは評価できるとしています。 一方で、風評被害が生じた場合の賠償については「大前提として風評被害が発生した場合に賠償するのは当然だが、賠償を継続している漁業に後継ぎ世代が未来を見い出せるかどうかや子や孫につがせようと思うかは心配で、賠償が長引くほどこの産業に将来展望を見出しにくくなるのではないか。賠償を支払うだけではなく後継者の育成や他業種からの新規参入の促進など、漁業を中核とした地域をどう作っていくかというビジョンも関係者との対話の中から明確にしていくべきだと思う」と話していました。
さらに最近、東京電力の不祥事が相次いでいることにも触れ「福島第一原子力発電所の事故から10年がたった今、さまざまな問題が出て気の緩みが出ていることを考えると、今は東京電力による処分を信用できる段階ではなく信頼性をどう担保するかも課題だと思う」とも述べて、国民の理解や信用を得ていくことの大切さを指摘しています。 また、国際的に政治問題化している点についても指摘し「この問題に関しては中国、韓国、台湾などでこの数年間、科学的な問題が政治問題化されたまま放っておかれていて課題が逆輸入されている状況もある」と述べ、近隣諸国に向けた情報発信の必要性を訴えました。

“住民の議論参加に課題”<NHKアンケート>
専門家“政府 関係者の理解得る努力 長期で必要”

そもそも、トリチウムとは…?

海洋放出はどう行われるのか?

その基準は?

トリチウム放出量<国内の原発>

トリチウム放出量<国外の原発>

東電の設備能力審査へ 原子力規制委

風評対策 議論深まらず…

政府は“風評対策に万全”

専門家「科学的理解と流通経路の維持を」

専門家「このままでは風評避けられず、対策を」