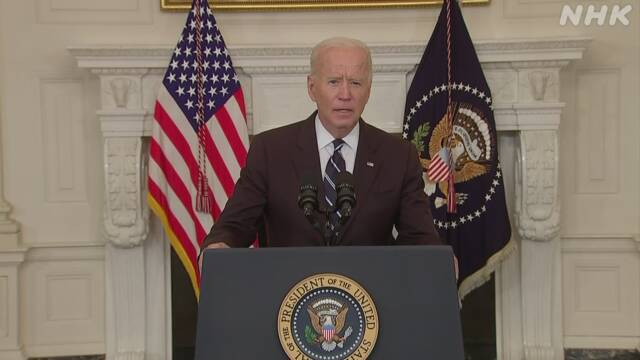授賞式は例年、ハーバード大学で行われますが、新型コロナウイルスの影響で去年に続いて、ことしもオンラインで授賞式が行われました。
ことしは日本から、京都工芸繊維大学の村上久助教らの研究グループによる、歩行者がほかの人にぶつからずに歩ける仕組みを調べた研究が「動力学賞」を受賞しました。
村上助教らは、歩きながらスマートフォンを操作する、いわゆる「歩きスマホ」をした場合としなかった場合で歩行者の動きがどう変わるかを実験しました。
その結果、「歩きスマホ」で注意が散漫になると、周辺の人の動きも乱れてぶつかりそうになったということで、歩行者どうしが相手の動きを「予期」することの重要性が確かめられたということです。
イグ・ノーベル賞の主催者は、授賞理由について「周囲に注意を払うことが重要だということを気付かせた」としています。
日本人がイグ・ノーベル賞を受賞するのは15年連続です。
このほか、9つの分野でも受賞者が発表され、政治家の肥満度と汚職の関連を調べた研究が「経済学賞」を、潜水艦の艦内でゴキブリを駆除する方法の研究が「昆虫学賞」をそれぞれ受賞しました。
まず、27人ずつの2つの集団をつくり、何の制約も与えずにすれ違うように歩かせると、一人一人が衝突を避けて、自然と歩行者の列ができる「レーン形成現象」ができてぶつからずに歩きました。 一方、片側の集団の3人に「歩きスマホ」をさせて、ほかの人たちの動きを「予期」しにくくしたところ、歩きスマホをしていない人たちの「予期」にも影響をもたらしてぶつかりそうになる人がでて、レーンが形成されるまでに最大で2倍近くの時間がかかったということです。 こうしたことから、ぶつからずに歩くには、歩行者どうしが周囲の人の動きを「予期」することが重要で、歩きスマホで一部の「予期」が妨げられると集団全体の秩序が乱れたと分析しています。 イグ・ノーベル賞の受賞について、村上助教は「とても驚きましたが、みんなで頑張った研究なのでうれしいです。バラバラな個体の集まりでしかないものが、なぜ一体となって動くのかを明らかにする研究なので、人間の興味深い相互作用に目を向けてもらいたい」と話していました。
「歩きスマホ」 ぶつからずに歩ける仕組みとは