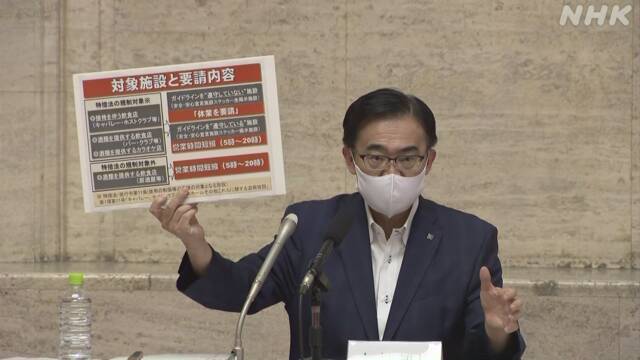撮影が許可されたのは、那覇市の首里城の地下に残る旧日本軍の「第32軍司令部壕」です。
撮影が許可されたのは、那覇市の首里城の地下に残る旧日本軍の「第32軍司令部壕」です。
20万人を超える人が亡くなった75年前の沖縄戦で、旧日本軍が深さおよそ30メートルの地下に全長およそ1キロにわたって構築し、戦況の悪化に伴って沖縄本島南部へ撤退するまで、戦闘を指揮していました。
崩落の危険性が高いため、立ち入りが厳しく制限されてきましたが、今回、管理を行う沖縄県から特別に許可を得て初めて内部の奥深くまで入って撮影しました。
壕の中には、通路に沿って部屋が設けられ、銃やヘルメットなどの装備品が今も残されているほか、壁にはツルハシで掘ったとみられる跡が刻まれています。
入り口から150メートル入ったところでは壁が大きく崩れて先に進めなくなっていて、旧日本軍が撤退した際に爆破した跡とされています。
旧日本軍の沖縄本島南部への撤退により、住民が戦場に巻き込まれる形となり、沖縄県の記録によると、わかっているだけで、軍人や軍属を除いた住民の犠牲者のうち、およそ半数にあたる4万6000人が、撤退後の1か月に命を落としたとされています。
戦跡に詳しい沖縄国際大学の元教授の吉浜忍さんは、「沖縄戦の悲劇は南部に撤退したあとの1か月に集中して起きている。沖縄戦を知る戦跡としては最も価値のある場所で、地上には首里城、地下には司令部壕という両面を見ないと正しい歴史の理解にはつながらない」として、調査や保存、それに公開を求めています。
目立つ老朽化 銃やヘルメットも残され…
 司令部壕の出入り口は、ふだん鉄の扉に鍵をかけて厳重に管理されていて、今回、沖縄県の立ち会いのもと撮影に入りました。
司令部壕の出入り口は、ふだん鉄の扉に鍵をかけて厳重に管理されていて、今回、沖縄県の立ち会いのもと撮影に入りました。
中は暑い沖縄でも23度ほどに保たれていますが、場所によっては、しゃがまないと頭がぶつかるほどの高さしかありません。
目に付くのは内部の老朽化で、ところどころに崩落した岩の塊が落ちています。
旧日本軍の記録で炊事場とされている部屋には、直径2メートルほどの大きな岩が崩れ落ち、天井にはヒビが入っていました。
その先の6畳ほどの部屋には、銃やヘルメット、それに無線機のような機械が残されていました。
崩落を防ぐため、内部の189か所に鉄の柱とはりが設置されているということで、はりと天井の間には発砲スチロールが敷き詰められていました。
さらに入り口から100メートルほど進むと、地下水のため足がくるぶしまで泥に埋まるほどぬかるんでいました。
その泥のようになった地面をよく見ると、トロッコの枕木として使われたとみられる長さ60センチほどの木が確認できました。
そして、入り口から150メートルのところまで進むと、通路を埋めつくす土砂で行く手を阻まれました。
旧日本軍が撤退した際に内部を爆破した跡とされています。
その先にあったとされる参謀室や作戦室などの中枢には立ち入ることができず、司令部壕の全貌は戦後75年たっても明らかになっていません。
沖縄戦の指揮中枢「第32軍司令部壕」
「第32軍司令部壕」は首里城の地下を南北に縦断するように構築されました。
アメリカ軍の艦砲射撃などに耐えられるような地下の地盤があったことや、高台にあったことからこの場所が選ばれたとされています。
当時、およそ1000人がいたとされる沖縄戦の戦闘指揮の中枢で、周辺ではアメリカ軍との激しい攻防が行われました。
5か所確認されている出入り口のうち、守礼門などの近くにある北側の出入り口は崩落のためふさがっていて、首里城正殿の南西およそ300メートルにある出入り口が、当時のものとしては唯一残されています。
保存と公開求める動き
沖縄では「第32軍司令部壕」の歴史的な価値が注目されています。
昭和20年5月、アメリカ軍が首里の包囲を進める中、第32軍は司令部を糸満市の摩文仁に撤退させ、本島南部で持久戦を行うことを決定しました。
これにより、南部に避難していた住民などが戦場に巻きまれる形となったことなどから、沖縄戦の実相を知る上で、重要な戦跡だとして、司令部壕の保存や公開を求める声が出ています。
沖縄戦の体験者などは、ことし3月に市民グループを結成し、今後、SNSなどを通じて公開を求める活動を行うことにしています。
また、沖縄県の玉城知事もことし6月、専門家などからなる検討委員会を設置し、保存や公開の在り方を検討していく考えを示しています。
一方、沖縄県によりますと内部は風化による落盤の危険性が高く、公開にあたっては、いかに当時の姿を残しながら安全を確保するのかといった技術的な課題などが多くあるということです。
市民グループの高山朝光副会長は「沖縄の象徴である首里城の再建とともに負の歴史である司令部の壕を整備して公開したい。そのことで首里城を訪れた人が沖縄の歴史をより深く学ぶことができる」と話していました。