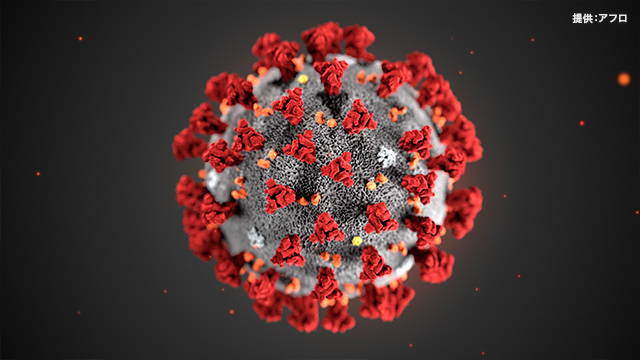その結果、水の事故で死亡した人は確認できただけで、川で18人、海で5人、合わせて23人に上っています。
警察庁の集計では、去年7月と8月に発生した水の事故による死者・行方不明者は、海が121人、川が92人と、海のほうが多かったほか、平成27年から30年にかけても海のほうが多くなっています。
斎藤教授は、お盆の期間だけでみても川の犠牲者が海の3倍以上に上っているのは異例の事態だとしています。
原因について斎藤教授は、新型コロナウイルスの影響で、公共施設のプールや海水浴場が閉鎖されたことや県外への移動の自粛が呼びかけられたことなどで、近場の川に出かける人が増えたためではないかと分析しています。
斎藤教授は「一見すると穏やかな川でも、急に深くなったり、流れが速い場所があったりと危険が潜んでいるので、注意が必要だ。子どもたちだけで遊んでいるのを見かけたら声をかけて注意を促すなど、地域の取り組みも重要になる」と指摘していました。
川での事故 防ぐには…
 川の安全対策に詳しい、河川財団・子どもの水辺サポートセンターの菅原一成主任研究員は、川で遊ぶ際には必ず「ライフジャケット」を着用するよう呼びかけています。
川の安全対策に詳しい、河川財団・子どもの水辺サポートセンターの菅原一成主任研究員は、川で遊ぶ際には必ず「ライフジャケット」を着用するよう呼びかけています。
 川の事故で特に注意が必要だと菅原さんが指摘するのが「フットエントラップメント」と呼ばれるリスクです。
川の事故で特に注意が必要だと菅原さんが指摘するのが「フットエントラップメント」と呼ばれるリスクです。
足がつく深さで遊んでいても、流れが強い場所で足が石や流木の間に挟まれると、水圧で立ち上がれなくなって溺れる危険性があるということです。
このため、川で流れが強いと感じたら無理に歩こうとはせず、足を上げて浮くことが重要で、そのためには「ライフジャケット」が欠かせないということです。
大人も ライフジャケットを着けて
そして、菅原さんが特に着用を呼びかけているのは「大人」です。
河川財団が平成15年から去年までを調査したところ、事故にあった人の4割が、大学生を除く65歳未満の「大人」で、最も高い割合となりました。
グループで行動して事故にあったケースでも全体の4割近くと最も高い割合を占めたのが「大人のグループ」でした。
菅原さんによると、流された子どもを助けに飛び込んだ大人が溺れるケースも発生しているということです。
 菅原さんは「最近は子どもにライフジャケットを着用させているケースは増えているが、大人で着用している人は少ないのが現状だ。周囲の人が着用していない中、自分だけが身につけるのは勇気がいることかもしれないが、大人も必ず着用してほしい」と話していました。
菅原さんは「最近は子どもにライフジャケットを着用させているケースは増えているが、大人で着用している人は少ないのが現状だ。周囲の人が着用していない中、自分だけが身につけるのは勇気がいることかもしれないが、大人も必ず着用してほしい」と話していました。
そのうえで「川は恵も多く楽しい場所なので、リスクを知り、安全対策を整えて楽しく安全に遊んでほしい」と話していました。