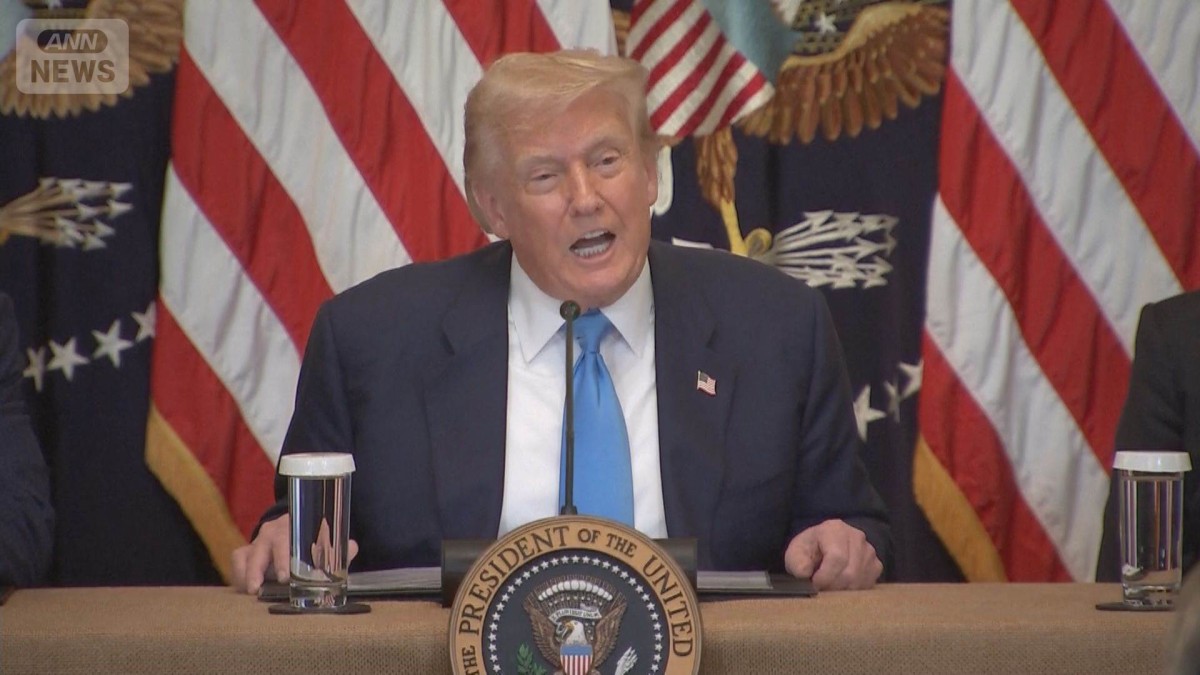これについてパウエル議長は「金利の影響を受けやすい住宅市場などでは需要が落ち込んでいるが大幅な利上げによってインフレが収まったことがはっきりするまでには時間が掛かる。リスクを管理する観点からは金融を引き締めすぎる、また緩めすぎるというミスを犯さないようにしなくてはならない」と述べました。
大幅な利上げを続けることで経済全体に悪影響が広がってしまうリスクは認識していることを示した形です。
一方で、利上げのペースについては「緩める時期はいつかはやってくるがまだ道半ばであり次回12月の会合になるかその後の会合になるかは決まっていない。12月の会合で議論することになる」と述べて利上げ幅をいつ縮小するか明言しませんでした。
そのうえでパウエル議長は最終的な金利の到達点は9月の会合で議論したときよりも高くなるとの見通しを示したうえで、「利上げの停止を考えるのはあまりに時期尚早だ。歴史は早まった金融緩和を強く戒めている。任務が完了するまで現在の方針を続ける」などと述べて記録的なインフレを抑えこむため万全の対応をとる姿勢を改めて強調しました。
そのうえで、吉田所長は「重要なのは利上げがどの水準まで行われるかだ。今のインフレは非常にひっ迫した労働市場が背景にあるので雇用情勢を中心に経済指標を見ていく必要がある」と話していました。
去年12月以降消費者物価が7%以上となりインフレが加速したことからFRBは3月の会合で0.25%の利上げを決めてゼロ金利政策を解除。金融引き締めへと転換します。利上げは3年3か月ぶりでした。 さらに5月の会合で22年ぶりとなる0.5%の利上げと、「量的引き締め」と呼ばれる金融資産の圧縮に乗り出すことも決めました。 しかし、その後もインフレに収束の兆しは見えず6月と7月の会合で2回連続で0.75%という大幅な利上げを決めました。 こうした中、パウエル議長は先月下旬、アメリカ西部ワイオミング州で開かれたシンポジウム「ジャクソンホール会議」で講演を行い記録的なインフレを抑え込むための金融引き締めについて「やり遂げるまでやり続けなければならない」と述べて、利上げを継続する姿勢を鮮明にしました。 そして「インフレを抑え込むには家計や企業に何らかの痛みをもたらすことになるがそれは避けられないコストだ。ただ、物価の安定を取り戻すことに失敗すればもっと大きな痛みを伴うことになる」と述べて強い決意を示しました。 ただ、その後発表された8月の消費者物価指数が市場の予想を上回り前の年の同じ月と比べて8.3%の上昇となりました。 このためFRBは9月の会合で3回連続で0.75%という異例の利上げに踏み切ります。 しかし、10月中旬に発表された9月の消費者物価指数は前の年の同じ月と比べて8.2%の上昇となり、市場の予想を上回りました。 さらに変動の大きい食品やエネルギーを除いた物価指数でも6.6%の上昇と、上げ幅は1982年8月以来、およそ40年ぶりの水準となり、記録的なインフレが続いていることが改めて浮き彫りになりました。
米専門家「金融引き締めに積極的」
日本の専門家「期待感がはがれた」
異例の利上げ これまでの経緯は